はじめに
三島由紀夫『仮面の告白』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
古典主義(ラディゲ、コクトー)。リアリズム
三島由紀夫はラディゲ(『ドルジェル伯の舞踏会』『肉体の悪魔』)、コクトー(『恐るべき子供たち』)といったフランスの古典主義文学に影響を受けています。私淑した二人にも相通じる、作品全体が合理的に構造としてデザインされた戯曲、家庭小説には佳品が多いですが、純文学作品には駄作も多いです。また純文学でいいのは『金閣寺』や本作など初期の作品に多いです。
本作品はラディゲ『肉体の悪魔』に似た私小説、自伝的小説になっているのですが、自分の存在を相対的に捉えるリアリズムが展開されます。
語りの構造
作者本人の分身たる私という等質物語世界の語り手を設定しています。
告白小説として、私の生まれたときから23歳までの青年期の性にまつわる経験が描かれていきます。
自分を徹底的に相対的に客観的に描く筆致が印象的です。
告白文学(芥川龍之介)
三島由紀夫は芥川龍之介からの影響が顕著ですが、芥川龍之介はストリンドベリの告白文学から顕著な影響を受け、とはいえストレートに自伝的な告白文学はなかなかものさず『藪の中』『地獄変』といった告白形式の作品や、『大導寺信輔の半生』『歯車』など自伝的作品を著しました。
本作はそんな芥川龍之介に影響したストリンドベリにも似た告白文学になっています。自身の同性愛的なセクシャリティについての告白が綴られます。
象徴主義、シュルレアリスム的なグランギニョル
本作は三島由紀夫のサディスティック、マゾフィスティックな欲望がうかがえる内容です。男の惨殺のモチーフに性的興奮を覚える心理が描かれます。
この辺りは精神分析などの心理学、コクトー(『恐るべき子供たち』)、サド(『悪徳の栄え』)の他、リラダンなどの象徴主義文学、森鴎外(「阿部一族」)などがグランギニョルなモチーフやプロットの崇高さ(不快かつ快)に着目した表現を展開したのと重なります。
性的不能と性的苦悩
本作はスタンダール『アルマンス』の影響があります。これは主人公の青年オクターヴとアルマンスという従妹の娘の恋愛を描く内容です。オクターブは性的不能の傾向があって、やがてそこから2人はすれ違い、最後はオクターヴは自責の念から自殺してしまいます。
このような性的不能による性的苦悩を描く物語は、ジッド(『田園交響楽』『狭き門』)のような性的マイノリティの作家に着目され、三島由紀夫も同様でした。
本作では私が、園子という女性に精神的に惹かれるものの、同性愛傾向によって肉体的には違和感を相手に感じてしまい、そのために私は悶えます。娼婦と関係を持とうとするものの、やはり性的に不能です。園子ともすれ違い続け、私は結局美男子の残酷な死に性的な興奮を覚えるのでした。
トランスジェンダー、同性愛
本作はトランスジェンダー表象や同性愛表象が見えます。シュルレアリスムはカウンターカルチャー、アウトサイダーアートとしての側面があり、三島由紀夫が愛したシュルレアリストのコクトーも同性愛者でしたので、以後モダニズムにはその表象の影響が見えます。
本作も同様で、同性愛者でありトランスジェンダー的な性的嗜好を抱える主人公の苦悩を描きます。
精神分析
フロイトが考えた同一化(愛する存在との同一化願望)の心理が現れます。
この辺りは精神分析を踏まえる作家のハイスミス『太陽がいっぱい』やヒッチコック監督『サイコ』に重なります。
モデル
作中に登場する草野園子のモデルは、三島の友人の三谷信の妹・三谷邦子で、初恋の相手です。
『仮面の告白』の発表に先駆けて1945年の末、恋人だった三谷邦子(三谷信の妹)が銀行員の永井邦夫(永井松三の息子)と婚約したことを知り、三島はショックを受けています。
『盗賊』などもこの失恋を背景にします。
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』
本作は冒頭にドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』のエピグラフがあります。
「美っていうのは、実に恐ろしいよ!恐ろしいその訳っていうのは、定義できないからなんだが、定義できないその訳っていうのは、神様が謎ばかりかけているせいなのさ。
美のなかじゃ、川の両岸が一つにくっついちまって、ありとあらゆる矛盾が一緒くたになっている。俺はな、アリョーシャ、全く無教養な男だけれど、美のことについては色々と考えたぞ。恐ろしいくらいたくさんの秘密が隠されてるんだ!余りに多すぎる謎が、地上の人間を抑えつけているんだ。だから、その謎を解けというのは、濡れずに水から出ろというのと同じなんだ。
美か!俺がおまけに我慢ならないのは、別の最高の心と最高の知性を持った人間が、マドンナの理想から出発して、ソドムの理想で終わるってとこなんだな。それにもまして恐ろしいのは、ソドムの理想を持った男が、心のなかじゃマドンナの理想も否定せず、むしろ心はまるでうぶなガキの時代みたいに、マドンナの理想に心から燃えているってことなんだ。いやあ、人間って広い、広すぎるくらいだ、だから俺はちっちゃくしてやりたい。それがどんなものか誰にもわからない。その通り!理性には恥辱と思えるものが、心には紛れもない美と映るもんなんだよ。
ソドムに美があるのか?信じてくれてもいい、大多数の人間にとっては、ソドムにこそ美がひそんでいるってことをな。こういう秘密を、お前はわかっていたか、どうだ?恐ろしいのはな、美がたんに恐ろしいだけじゃなく、神秘的なものだってことさ。美のなかじゃ悪魔と神が戦っていて、その戦場が人間の心ってことになる。でもな、それを言うのは痛がっている人間だってことだよ」
このように引用される内容は、美の多様性について言及するもので、『地下室の手記』やその心理劇、保守主義の前提となる、そこに生きる人々の選好や信念の多様性に着目する姿勢が見て取れます。
本著との関連では、マイノリティである語り手の独特の性的アイデンティティ、美学的理想を象徴するものになっています。
物語世界
あらすじ
「私」は、生まれた時の光景を憶えているそうです。赤子の「私」を祖母は溺愛して育てます。「私」は外で遊ぶことも、男子の玩具も禁じられ、遊び相手は、女中か看護婦、祖母の選んだ女の子だけでした。
幼年時、美しい頬の汚穢屋の若者に「私」は惹かれ、彼になりたいという欲求を覚えます。また絵本で見たジャンヌ=ダルクが「女」だと知り「私」は落胆します。また「私」が惹かれたのは、家の前を行進する兵士の汗の匂いでした。そうした官能的な感覚をそそるものは、悲劇的なものを帯び、「私」は殺される王子を愛し、殺される自分を想像すると恍惚とします。クレオパトラや松旭斎天勝の扮装も「私」を魅力します。
「私」は13歳の時、グイド=レーニの「聖セバスチャン」の絵に惹かれ、初めての射精を体験します。やがて「私」は、野蛮で逞しい級友の近江に恋をします。さしてそれと同時に、嫉妬を感じます。「私」の中には、愛する相手になりたいという感情があったのでした。「私」の愛が特異なものだと気づき始めた「私」は苦悩します。
高校卒業間近の「私」は、友人の草野の家で、ピアノの音を聞きます。それは草野の妹の園子が弾くピアノでした。大学生の「私」は召集令状を受け取るも、軍医の誤診で即日帰郷となります。特別幹部候補生で入隊した草野の面会に行った「私」は、そこで園子の美しさに惹かれます。そこから親しくなった「私」と園子は、本を貸し借りするようになり、園子も「私」に好意を持ちます。「私」は、園子を肉欲なしに愛していると感じます。
学徒動員で海軍工廠にいる「私」と、一家で疎開した園子との文通が続きます。園子の疎開先の軽井沢に招かれた「私」は、園子と高原を散歩中、接吻を試みます。しかし「私」には何の快感もありません。「私」は、自分の異常性に悩み傷きます。「私」は、園子から逃げたいと思いました。やがて草野の家から結婚の申し出の手紙が来るも、「私」は婉曲な断りをします。
戦後間もなく園子は他の男と結婚します。「私」は友人と娼家に行くも、やはり「不能」が確定し、絶望します。ある日「私」は偶然、人妻となった園子にばったり出会い、それ以来再び、2人だけで逢うようになります。
プラトニックな関係のまま、人妻の園子と「私」は何度か逢い引きを重ね、園子の気持ちは揺れます。真昼のダンスホールの中庭に出ると「私」は、ある粗野な美しい肉体の刺青の若者に釘付けとなり、彼が匕首に刺され血まみれになる姿を夢想します。「私」は園子を忘れ、彼に見惚れていたとき、「あと5分だわ」という園子の哀切な声を聞きます。その刹那、「私」の内部で何かが2つに引裂かれ、「私」が「不在」に入れかわるのを感じます。






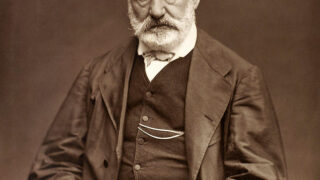















コメント