はじめに
プルースト『失われた時を求めて』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
等質物語世界の語り
本作品は等質物語世界の語り手、「私」を設定しています。パリのブルジョアの家庭に生まれた男性です。父親は高級役人で、母親と祖母の愛情を受けて育ちました。
物語は彼の一人称視点で綴られていきます。この辺りは村上春樹『ノルウェイの森』、谷崎潤一郎『痴人の愛』『卍』『盲目物語』と共通です。
ただ例外的に第一編の第二部「スワンの恋」では、語り手の誕生以前の物語が異質物語世界の語りで綴られます。語り手が誰かから聞いたことを書きとめたという設定になっていて、物語世界外から自分の生まれる前のことを物語ります。
一人称的視点のリアリズム、意識の流れ。プラグマティズム、現象学
モダニズム文学に典型的な手法が意識の流れです。等質物語世界の語り手を複数導入する手法はH=ジェイムズ『ねじの回転』、コンラッド『闇の奥』など、モダニズムの先駆者の作品に見えますが、ジョイス『ユリシーズ』、フォークナー『響きと怒り』、ウルフ『ダロウェイ夫人』などに見える意識の流れの手法は、それに現象学(フッサール、ベルクソン)、精神分析などの心理学、社会心理学、プラグマティズム的な知見を元にラディカルに押し進めたものでした。
プルーストも現象学のベルクソンの親戚であり、その思想から顕著な影響を受けました。ベルクソンの思想とその現象学は一人称的視点の集積として世界や社会を解釈しようとするプラグマティズム、システム論的なものでしたが、本作も一個のエージェントの視点から、社交界における実践を記述しようとします。一人称視点の主観的なタイムトラベルが繰り返される中で、失われた時の中の過去が綴られていきます。
プラグマティックな歴史記述
フレイザー『金枝篇』がT=S=エリオット『荒地』に導入されて以降、作家は語りの手法に民俗学、社会学的アプローチをも積極的に取り入れるようになっていきました。特に本作でも用いられているアナール学派的な、中央の事件史に抗する心性史としての歴史記述のアプローチは、ポストコロニアルな主題を孕みつつ、ガルシア=マルケス『族長の秋』『百年の孤独』などラテンアメリカ文学などへと継承されていきました。
旧来的な中央の事件史としての歴史記述においては、歴史の構造的理解に欠き、そこから捨象される要素が大きすぎましたが、アナール学派は特定のトポスに焦点を当てたり、ミクロなアクターの視点に注目したりして、歴史の構造的把握と、歴史を構成するアクターの単位の修正を図りました。本作も同様に、ミクロな歴史的アクターの一人称的視点に着目しつつ、その集積物として歴史を構造的にとらえようとするプラグマティックな歴史記述のアプローチが見えます。
歴史の中のミクロなアクターの視点、語りを通じて歴史を記述、再構築しようとするアナール学派的アプローチは、小説家にとっても強力な武器となったのでした。本作品はバルザック流の社会リアリズムをそのようなアプローチでもってラディカルに推し進めたものと解釈できます。
バルザックやフローベル流のリアリズム
プルーストはバルザック(『従妹ベット』『ゴリオ爺さん』)の作品を好んでいました。バルザックはブルジョワ社会の中での自己実現をめぐる作品を描きましたが、本作もそれと共通します。
また本作はバルザックと同時代の写実主義のフローベール『感情教育』を思わせる内容で、「時による破壊と至福」をテーマにします。
本作における時間
最終盤、語り手は、ゲルマント大公夫人のマチネに出席し、ゲルマント家の中庭の敷石で躓いた瞬間、ヴェネツィアで同じ体験をしたことを思い出します。ここから語り手は、自分の文学的な天分を発見し、生々しく甦ってきた生の軌跡を描いていくべきだと確信します。それから語り手はゲルマント公妃の開いたパーティの場で、すっかり老いて様変わりした人々の姿を見て、「時の破壊作用」を目の当たりにします。他方で「スワン家のほう」と「ゲルマントのほう」の2つの道が合流していたことを象徴するジルベルトの娘サン=ルー嬢に出会い、時の至福をも実感します。ここから語り手は、自分の死を背後に感じながら、時と記憶を主題とする長大な小説を予告します。
物語のテーマになるのはこの時のもたらす効果です。時は、人や事物を壊してしまいます。しかし、時間の流れの中で人は傷から癒されたり、主観的な時間経験のなかで思いがけない事物のつながりが見出されて発見されたり、気づきがあったりします。
語り手は最後に、この主観的な時間経験の中で沸き起こってくるものを作品の中に描いていこうとする決意を最後に語ります。
意識と時間
本作は意識の流れの手法を用いていますが、ここで意識について説明します。現代の心の哲学では、意識や心というものの機能主義的、道具的定義がいろいろに考えられており、大まかに言ってそれは複数のモジュールの計算、表象の操作を統合し、シュミレーションから推論を立て環境に適応的な行動変容を促すツールであるとの見通しが立てられています。そこではインプットされたさまざまな表象を操作し、過去にインプットされた表象との関連性が発見されたり、環境の構造化にあたって認識が修正されたりしていきます。
本作における意識の流れの手法にも、そのような意識の特性が伺えます。語り手は知覚から得た情報からマインドワンダリングを働かせ、主観的なタイムトラベルの中でさまざまな過去の事実の表象を統合しつつ、時間軸の中で状況を構造化、そのモデルを絶えず改訂していきます。
「スワン家のほう」と「ゲルマントのほう」への2つの道が実は近道で合流していたという事実に象徴される、ある体験から、主観的な時間経験の中で思いがけない事物や経験同士のつながりが発見され、そうした主観的経験の中での記憶の顕れを描くことこそ自分という作家の本分だと、語り手は最後に見出します。
サント=ヴーヴとの論争
プルーストは、実証的伝記研究を重んじるサント=ブーヴが、スタンダール、バルザック、フローベールなどを軽視したことについて、サント=ブーヴに対する批判を展開しました。
作家の伝記的背景や思想と作品とを不可分のものと考え、それとの関連のなかでテクストを読み解こうとするサント=ブーヴに対して、プルーストは、そうした外面的な表層の自我と、作品で表現される自己内部の「深層の自我」は別物であるとしました。
実証的伝記研究を重んじるサント=ヴーヴに対して、プルーストは、実証的研究で示せる作家の心理には限界がある旨を述べ、それでは捉えきれない深層の自我がテクストの背景にあるとしました。
プルーストを好んだ「作者の死」で知られるロラン=バルトも、実証的伝記研究に対するカウンターとしての読者論を展開しました。
物語世界
あらすじ
第一編 『スワン家のほうへ』
第1部「コンブレー」
語り手はベッドの上で過ごしながら、自分がかつて過ごした様々な部屋を回想します。
そして回想は、語り手が幼年時代にバカンスで過ごした田舎町コンブレーでの出来事に移り、そこで母親に寝る前のおやすみのキスをせがんだ思い出を語ります。一家と親しい近所のスワンが訪問すると、応対で母親は2階の部屋になかなか来ないため、幼い語り手には耐え難いのでした。
そして熱い紅茶を一さじ掬った時に混じった一片のプチット=マドレーヌを食べた時の感覚で、コンブレーでレオニ叔母が入れた紅茶かハーブティーで味わったのを思い出し、そこから、コンブレー全体の光景がティーカップの中から広がり、コンブレーの自然情景、人々、見聞きした物事を語ります。
コンブレーでは、幼い語り手の家族はレオニ叔母の家の別棟に滞在し、そこからよく散歩に出かけていました。散歩のコースの一方は「スワン家のほう」で、散歩の途中でスワンの娘ジルベルトを見かけました。もう一方は「ゲルマントのほう」で、ゲルマント家のゲルマント公爵夫人に語り手は憧れています。
第2部「スワンの恋」
15年ほど時を遡り、語り手の誕生以前の物語が三人称で綴られます。語り手が誰かから聞いたことを書きとめたという設定になっています。
語り手の一家の友人であるユダヤ人の仲買人スワン(フェルメールを研究している美術品蒐集家)が、高級娼婦オデットに恋をするようになった経緯、彼女への恋が冷めるまでが描かれ、ヴェルデュラン邸のサロンを舞台として首都パリの社交界の様子も描かれます。
スワンがオデットに誘われて、初めてヴェルデュラン夫人のサロンに行った際、そこでピアノ演奏されたソナタに感動するものの、それは前年にある夜会で聴いて惹かれていたヴァイオリン演奏のソナタと同じ曲でした。スワンはその作曲者が、ヴァントゥイユという人物と知ります。
このヴァントゥイユ作曲のソナタは、スワンとオデットの恋を記念する「恋の国歌」となります。スワンは、ヴァントゥイユがいかなる苦悩から音楽を創造したのか考えるものの、やがて次の女との出会いを求めます。
第3部「土地の名、名」
ヴェネツィア、フィレンツェ、パルマ、ノルマンディーのバルベック(架空の町で、カブールがモデルの地)など、まだ行ったことのない土地の名前についての語り手の憧憬などが描かれます。
高熱を出して旅行を禁じられた幼い語り手が、シャンゼリゼ公園に出かけてジルベルトに出会い、そこから2人の淡い恋が始まったことが回想されます。
スワンはオデットと別れたかと思われたものの、彼らは既に結婚し、スワン夫妻の間には娘ジルベルトがいます。
第2篇『花咲く乙女たちのかげに』
第1部「スワン夫人をめぐって」
まずジルベルトとの間の恋が描かれます。語り手はスワン家に出入りするようになるものの、ジルベルトとは気持ちのすれ違いが増えます。
スワン夫人(オデット)のサロンに出入りを続け、そこでピアノ教師ヴァントゥイユが作曲したソナタを聞き、やがて語り手は少年の頃から愛読し憧れていた作家のベルゴットにも出会いました。
第2部「土地の名、土地」
前章から2年。ジルベルトとの恋の痛手も癒えた語り手は、祖母とその女中フランソワーズとノルマンディーの避暑地バルベックにバカンスに出かけます。
美術に明るいスワンの説明から思い描いていたノルマンディー風ゴシック建築の教会は、期待外れで想像より劣っていました。
語り手はここで、祖母の旧友でゲルマントの一族の出であるヴィルパリジ侯爵夫人(ゲルマント公爵の叔母)と出会い、ゲルマント公爵夫妻の甥である貴公子ロベール=ド=サンルー侯爵、ゲルマント公爵の弟シャルリュス男爵とも知り合いになります。
堤防の上でブルジョワの娘たちの一団(「花咲く乙女たち」)を見かけ、後に画家エルスチールの紹介で彼女たちとも親しくなり、この中の1人であるアルベルチーヌ=シモネに恋します。
ある晩、アルベルチーヌにキスしようとするが、語り手は拒否されます。
第3篇『ゲルマントのほう』
第1部「ゲルマントのほう I」
語り手の一家はヴィルパリジ侯爵夫人の勧めで、パリのゲルマント邸の館の一角(アパルトマン)に引っ越します。
日常のゲルマント公爵の様子を目にすると、今までの高貴なイメージが萎えることもあったものの、語り手はオペラ座のボックス席のゲルマント公爵夫人の艶やかさを眺め、自分に手を振り合図した公爵夫人に夢中になり、彼女に挨拶するために毎日待ち伏せをします。
そして、彼女に紹介されることを願いつつ、その甥である隣人のサン=ルーとの交友を深めていき、その後には彼とその愛人ラシェルとの関係も知ります。
実在のドレフュス事件の話題も登場し、ヴィルパリジ侯爵夫人邸でのマチネのシーンのあと、語り手の祖母がシャンゼリゼで軽い発作を起こします。
第2部「ゲルマントのほう II」
まず祖母の病気と死が語られます。これよりそれから、語り手とアルベルチーヌとの間の関係が再燃し、初めて彼女とキスをします。
語り手はゲルマント公爵夫人邸の晩餐会に招待され、シャルリュス男爵に会います。その後、シャルリュス男爵を訪れ、そこで男爵の尊大な振る舞いに困惑するものの、その頃にはゲルマント公爵夫人に対する熱は冷めています。
その2か月後、語り手は、公爵夫人の従姉であるゲルマント大公夫人のサロンへの招待状を受け取ります。
第4篇『ソドムとゴモラ』
第1部「ソドムとゴモラ I」
語り手は、ゲルマント家の館の中庭に面した場所に店を持つ仕立屋ジュピヤンとシャルリュス男爵が中庭で、蘭の花とマルハナバチのような求愛の仕草を取り合っている光景を目撃します。そこから女としての特徴を持つ男について考えます。
第2部「ソドムとゴモラ II」
最初は語り手が招待されたゲルマント大公夫人の夜会の場面に始まり、その夜会の後でアルベルチーヌが語り手を訪ねます。その後、語り手は2回目のバルベック滞在に向かうが、そこのホテルの部屋で靴を脱ごうとした瞬間、不意に祖母の思い出が「心の間歇」として甦り、その死を実感します。
また、語り手にアルベルチーヌに対する同性愛の疑いが兆し、彼女への愛情と嫉妬が語られます。他方、バルベックで再会したシャルリュス男爵と、ヴァイオリニストのモレルとの間の同性愛関係も語られます。
語り手は、アルベルチーヌに疎ましさを感じるます。しかし、アルベルチーヌから、同性愛者であるヴァイントゥイユ嬢の女友達との関係を告げられると嫉妬に駆られ、彼女をパリに連れて行き自宅に住まわせます。
第5篇『囚われの女』
語り手はアルベルチーヌと暮らし始めたものの、病弱で家からなかなか出られず、監視役としてつけたアンドレと一緒に出かけていくアルベルチーヌに嫉妬を募らせます。
その後、語り手はヴェルデュラン家の夜会に赴きます。そこでシャルリュス男爵の後ろ盾でモレルを称える音楽会が催されるものの、客に無視されて気分を害したヴェルデュラン夫人のためにシャルリュス男爵とモレルは仲違いします。
その音楽会で、語り手は「七重奏曲」に聴き入り、それがヴァントゥイユの遺作だと気が付きます。そして音楽の与える喜びに匹敵する作品を自分が創造できるのか考えます。
一方、語り手はアルベルチーヌへの嫉妬に苦しみ、諍いが起こります。そして彼女と別れることを考えますが、それをほのめかしたところ、アルベルチーヌは語り手の家から立ち去ります。
第6篇『消え去ったアルベルチーヌ』
語り手は、アルベルチーヌが身をよせたトゥーレーヌのボンタン夫人(アルベルチーヌの伯母)の元へサン=ルーを密使として送り、また夫人の気を引くために手紙を送って、彼女を自分の元に戻らせようとします。
しかし、そのうちにボンタン夫人から、アルベルチーヌが乗馬中の事故で死亡したという知らせが届きます。「自分をもう一度受け入れて欲しい」「戻りたい」という内容のアルベルチーヌからの手紙が届いたのは、その後でした。
語り手は、彼女を失った悲しみに加え、その死後も彼女の同性愛趣味への嫉妬に苦しみます。しかしその苦しみを他人に語り時間が経つにつれ、少しずつ和らぎます。
そして、母オデットの再婚によってフォルシュヴィル嬢となっていた初恋のジルベルトと語り手は再会します。その後、念願だったヴェネツィアに語り手は旅行するとき、アルベルチーヌへの想いはほとんど消えています。パリへの帰途で、語り手は、ジルベルトとサン=ルーの結婚を知るのでした。
第7篇『見出された時』
語り手は、コンブレーのジルベルト邸に滞在し、ここでジルベルトから、それまではまったく別の方向だと思っていた「スワン家のほう」と「ゲルマントのほう」の2つの道が、ある点で合流して、近道で繋がっていたことを知らされます。それからゴンクール日記(引用はプルーストによる模作)を読んで、文学の価値や自身の才能に疑念を持ちます。
その後、語り手は病を治療するために数年の療養所生活を送ります。やがて語り手は一時、第一次世界大戦下のパリに戻ります。コンブレーはドイツ軍に占領されて、敵国のドイツ贔屓になっていたシャルリュス男爵は社交界での地位を失っています。語り手は、空襲に晒されたパリの灯火管制下の町のホテルで、自分を若い男に鞭打たせている血だらけのシャルリュスを見かけ、またサン=ルーもこの宿に出入りしていたらしいことを知ります。その後、まもなくサン=ルーは戦線で死に、語り手は療養所生活に戻ります。
さらに数年経ち、語り手はまたパリに戻ります。語り手は、ゲルマント大公夫人(大公と再婚した元ヴェルデュラン夫人)のマチネに出席し、ゲルマント家の中庭の敷石で躓いた瞬間、ヴェネツィアで同じ体験をしたことを思い出します。
この体験から語り手は、自分の文学的な天分を発見し、時勢や特定の観念ばかりでなく、生々しく甦ってきた生の軌跡を描いていくべきだと確信します。語り手は、ゲルマント公妃の開いたパーティの場で、すっかり老いて仮面を被っているかのように様変わりした人々の姿を見て、「時の破壊作用」を目の当たりにします。そして「スワン家のほう」と「ゲルマントのほう」の2つの道の合流を象徴するジルベルトの娘サン=ルー嬢に出会い、時の至福をも実感します。
語り手は、自分の死を背後に感じながら、時と記憶を主題とする長大な小説を予告します。
参考文献
・エドマンド=ホワイト『マルセル=プルースト』
・戸田山和久『哲学入門』(筑摩書房.2014)『恐怖の哲学 ホラーから人間を読む』(NHK出版.2016)

















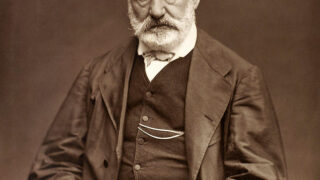




コメント