始めに
横光利一「機械」解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
モダニズムと新感覚派
横光利一は川端(『眠れる美女』『みづうみ』)と並んで、文藝時代の新感覚派を代表するモダニズム作家です。
モダニズムとはジョイス(『ユリシーズ』)やプルースト(『失われた時を求めて』)、フォークナー(『アブサロム、アブサロム!』『響きと怒り』)に代表される前衛的な文学運動で、意識の流れなどを特徴とします。また、同時期の前衛文学にシュルレアリスムがあって、そうした潮流と連動しつつ展開されていきました。
川端もモダニズム、シュルレアリスムの影響が大きく、『眠れる美女』『みづうみ』などを展開しました。シュルレアリスムはまた、映画とも連動して展開されていったのですが、川端康成や横光利一も衣笠貞之助監督の『狂った一頁』に協力しています。
横光利一は芥川龍之介から大きな影響を受けましたが、芥川風の形式主義的実験が本作も特徴的です。本作も特に芥川『歯車』を思わせる一人称的視点のリアリズムと、語り手の狂気にも似た強迫観念で締めくくるラストが印象的です。
意識の流れによる心理劇
本作は「私」という等質物語世界の語り手を設定し、その意識の流れを独自の文体で展開していきます。
本作の文章は『ユリシーズ』の18章や、谷崎『春琴抄』に似て、記号や改行などを極力排したスタイルで、意識的な経験の時間的な全体性を再現せんとしています。
意識の流れというデザインで描く人間の意識の特性というのは、時間軸の中での全体論的特性です。
例えば、人間は一人口笛を吹いている自分を発見したとき、その曲がその日目にしたドラマや映画、CMを聴いたことに由来したりするものだったりします。また、人間はコミュニケーションにおいて、相手の現在の振る舞いを観察しながら、過去の振る舞いと示し合わせてそれを解釈し、未来に相手や自分が取りうる、取るべき行動を予測し、現在の行動にフィードバックします。
このように人間の意識的経験やそれにドライブされる行動は、時間軸の中で全体性を持っています。主観的な時間の中で過去と現在と未来とは、相互に干渉し合って全体を形作っていきます。
過去の経験や知覚が因果になり、さながら一連の流れとも見えるように、意識的経験は展開されます。こうした時間論的全体性を描くのが意識の流れの手法です。
「純粋小説論」とドストエフスキー、それからバフチン
横光利一はジッド(『田園交響楽』『狭き門』)が「贋金つくり」にて実践しようとした純粋小説に刺激された「純粋小説論」において、心境小説や私小説に代表される近代文学のリアリズムを補完するものとして、ドストエフスキー、バルザック(『従妹ベット』『ゴリオ爺さん』)、トルストイ(『戦争と平和』『アンナ=カレーニナ』)のリアリズムを称揚し、『罪と罰』などに言及しています。
ドストエフスキーに関して、ミハイル=バフチンはポリフォニーという概念でもって、作品を分析しました。バフチンは社会学、哲学(新カント学派)、現象学(フッサール、ベルクソン)から顕著な影響を受けましたが、バフチンの文芸批評はそこから影響がみえます。
バフチンがドストエフスキーの文学について解釈していたのは、そこに描かれる物語が、物語世界内の関係性や慣習伝統といった制度にコミットする、選好や信念の異なる一人ひとりのエージェントの戦略的コミュニケーションの集合の帰結として展開されているということでした。
『罪と罰』は主人公であるラスコリニコフだけではなく、スヴィドリガイロフやドゥーニャ、ソーニャなど、他のサブキャラクターもさまざまな目的を持ち、戦略的コミュニケーションを展開していきます。その集積の中で物語が紡がれていくのです。このようなプラグマティズム的な発想が、ドストエフスキーのリアリズムの特徴です。オースティン『高慢と偏見』にも重なりますが、制度や慣習のなかでそれぞれのプレイヤーが合理性を発揮する中で展開される心理劇のデザインが卓越しています。
他の作品では例えば冨樫義博『HUNTER×HUNTER』、ハメット『マルタの鷹』『血の収穫』、谷崎潤一郎『卍』、エドワード=ヤン監督『エドワード=ヤンの恋愛時代』などに近いですが、物語は偏に特定のテーマや目的や結末に従うべくデザインされている訳ではなく、エージェントがそれぞれの選好、信念のもと合理性を発揮し、これが交錯しそれが時間的に蓄積する中でドラマが展開されていきます。
このようなデザインは、現実社会における政治学・社会学(システム論、エスノメソドロジー)や国際関係論におけるリアリズム/リベラリズム/ネオリベラリズム/ネオリアリズムが想定する人間関係や国際関係に対するモデルと共通しますが、つまり経験的な根拠の蓄積に裏付けられたモデルに近似しているといえます。バフチンがドストエフスキーに見出したのもまさにこのようなデザインが現実社会における実践の正確な再現である点だと思います。
長くなったので、ここでこれを「純粋小説論」と「機械」との関係から整理します。
「純粋小説論」の理想の四人称と「機械」
「純粋小説論」が、ドストエフスキーを参照しつつ、伝統的な日本の日記文学風のリアリズムを批判的に捉えようとしたのはまさにこのような視点からだったと評価できます。
ここで少し私は自分の純粋小説論を簡単に書いてみたい。今までのべて来たところの事は、誰にでも通じることであったが、以下書くことは、現代小説を書こうと試みた人でなければ興味のない部分に触れると思う。――今までの日本の純文学に現れた小説というものは、作者が、おのれひとり物事を考えていると思って生活している小説である。少くとも、もしそれが作者でなければ、その作中に現れたある一人物ばかりが、自分こそ物事を考えていると人々に思わす小説であって、多くの人々がめいめい勝手に物事を考えているという世間の事実には、盲目同然であった。もしこのようなときに、眼に見えた世間の人物も、それぞれ自分同様に、勝手気儘
に思うだけは思って生活しているものだと分って来ると、突然、今までの純文学の行き方が、どんなに狭小なものであったかということに気づいて来るのである。もしそれに気がつけば、早や、日記文学の延長の日本的記述リアリズムでは、一人の人物の幾らかの心理と活動とには役には立とうが大部分の人間の役には立たなくなるのである。前にものべたように、人々が、めいめい勝手に物事を考えていることが事実であり、作中に現れた幾人かの人物も、同様に自分一人のようには物事を思うものでないと作者が気附いたとき、それなら、ただ一人よりいない作者は、いったいいかなるリアリズムを用いたら良いのであろうか。
上記の通り、従来の志賀直哉『城の崎にて』などに代表される私小説、心境小説の実践ではそれは一人称的視点のリアリズムでありつつも、語り手や焦点化がされる主人公のモノローグに終始し、物語世界における一人の存在者として人間関係の網の目の中でのエージェントのコミットメントを描けていないことから、現実世界における社会的実践の美学的再現としては不十分と捉えました。
そこにおいて、語り手などは世界や一人称視点の記述者に終止し、世界のなかの関係性の網の目のなかで、観察者として、また行為者として存在し、またそのなかで自己の振る舞いを客観的に相対化して調整する存在者としてのエージェントの美学的再現に欠いていると考えたのでした。
この「自分を見る自分」という新しい存在物としての人称が生じてからは、すでに役に立たなくなった古いリアリズムでは、一層役に立たなくなって来たのは、云うまでもないことだが、不便はそれのみにはあらずして、この人々の内面を支配している強力な自意識の表現の場合に、幾らかでも真実に近づけてリアリティを与えようとするなら、作家はも早や、いかなる方法かで、自身の操作に適合した四人称の発明工夫をしない限り、表現の方法はないのである。
しかし、現代のように、一人の人間が人としての眼と、個人としての眼と、その個人を見る眼と、三様の眼を持って出現し始め、そうしてなお且かつ作者としての眼さえ持った上に、しかもただ一途いちずに頼んだ道徳や理智までが再び分解せられた今になって、何が美しきものであろうか。われわれの最大の美しい関心事は、人間活動の中の最も高い部分に位置する道徳と理智とを見脱みのがして、どこにも美しさを求めることが出来ぬ。「われら何をなすべきか」と能動主義者は云う。しかし、いかに分らぬとはいえ、近代個人の道徳と理智との探索を見捨てて、われら何をなすべきであるのか。けれども、ここに作家の楽しみが新しく生れて来たのである。それはわれわれには、四人称の設定の自由が赦されているということだ。純粋小説はこの四人称を設定して、新しく人物を動かし進める可能の世界を実現していくことだ。まだ何人なんぴとも企てぬ自由の天地にリアリティを与えることだ。新しい浪曼主義は、ここから出発しなければ、創造は不可能である。しかも、ただ単に創造に関する事ばかりではない。どんなに着実非情な実証主義者といえども、法則愛玩の理由を、
そこで「純粋小説論」の理想として、「四人称」を唱えて、心境小説的な一人称的な視点と『罪と罰』的な三人称的な視点の綜合を目指しました。
つまるところ、従来の私小説や心境小説風の心理リアリズムを継承しつつも、そこにドストエフスキー『罪と罰』のような群像劇における心理リアリズムを摂取して批判的な乗り越えを図りました。人間関係の網の目や社会の中にエージェントをコミットさせて、各々のエージェントが、世界の中における存在者の一人に過ぎないことを踏まえて自分を相対的に捉え、相互的な役割期待の中で物語を展開するという理想を構想し、そこからこの「機械」は起こりました。そのあとで「純粋小説論」をものしたのでした。
「機械」の心理劇
本作は語り手の私と、軽部、それから屋敷という三人のキャラクターの三角関係を描く心理劇になっていて、このあたりは終盤の展開も含めて谷崎潤一郎『卍』と重なります。
本作では製作所に勤める私、製作所主人の信奉者である軽部、別の製作所から来た応援の屋敷の三人が、それぞれ違いに戦略的コミュニケーションを展開するなかで互いや自分への疑心暗鬼を強めていき、ラストの屋敷の死という出来事へと繋がります。
タイトルになっている「機械」というのは、さながら機械やメカニズムのように、複数の要素の相互的作用の中で展開される、人間関係の実践の中での秩序やその背景になるシステム的なものを象徴するものになっています。
物語世界
あらすじ
私は、ネームプレート製作所で働いています。この製作所の主人は、無邪気な男です。人体や脳に影響がある薬物を扱う仕事を任され、辞めたく思いつつも耐えています。前からここで働く軽部は、私を間者だと勘違いし、嫌がらせをします。
やがて主人に信頼された私は、黒色を出す研究を一緒にやるように誘われます。主人から信用されていたことに感謝し、軽部のように主人第一の信徒のようになります。私は、地金に薬品を試練していくうち、無機物内の有機的運動の急所を読みとります。ここから、いかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実体を計っていることに気づきます。
私は、主人以外は入ることが許されなかった暗室へ出入りする権利を得ます。しかし、そんな私に軽部の憎しみが増し、暴力を振るわれます。私は、軽部を暗室へ連れていき、化学方程式を細かく書いたノートを示し、これが読めない軽部に無理なことを納得させると、軽部は私に逆らわなくなります。
ある市役所からの注文で、ネームプレート5万枚を10日で作ることとなり、主人の友人の製作所から応援の職人・屋敷がきます。私は屋敷を産業スパイでないかと疑うものの、言葉を交わすうちには親しみも感じます。
作業5日目頃の夜中、目を覚ました私は、暗室から出てゆく屋敷を見ました。しかし夢だったのかもしれません。けれども屋敷への疑念を強めます。
あるとき、私は、屋敷に自分が軽部に間者と思われて暴行されたことなどを打ち明け探りを入れます。屋敷は、私に疑われていることを知っていて笑います。私は屋敷の優秀さに惹かれていき、馬鹿にされているような気もします。
仕事も終わりかけたある日、軽部が屋敷に暴力を振るいます。私はしばらくして、軽部に止めるように言います。軽部は、屋敷が暗室へ入ったのを怒り、屋敷は弁解します。軽部は、私も屋敷と共謀していると言って殴りかかります。屋敷は、その隙に軽部を殴り反撃するものの、軽部に倒されます。私を警戒した軽部が、今度は私に向かい、軽部にされるがままにさせていたものの、起き上がった屋敷は、軽部を殴らずに私を殴ります。やがてみんな疲れて収束します。
屋敷は、ああしなければ収まらなかったと私に謝るものの、私は、屋敷の智謀を揶揄し、暗室の方もうまくいったのだろうと言います。屋敷はこれを笑います。やがて屋敷が私を殴ったのも私と軽部が共謀したからだと思われ、疑心暗鬼になります。
翌日、主人が私たちの仕上げた製品の代金を帰り道で紛失してします。軽部が酒を飲もうと言い出して、その夜3人は仕事場で車座になって酒を飲んだ。目が覚めると屋敷が死んでいた。重クロム酸アンモニアの溶液を水と間違えて土瓶の口から飲んだのだった。疑われたのは軽部だった。しかし、全く私が屋敷を殺さなかったとどうして断言できよう。私はもう私が分からなくなって来た。私はただ近づいて来る機械の鋭い先尖がじりじり私を狙っているのを感じるだけだ。誰かもう私に代って私を裁いてくれ。私が何をして来たかそんなことを私に聞いたって私の知っていよう筈がないのだから。
参考文献
・荒井惇見『人と作品 横光利一』
・桑野隆『バフチン』
・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』




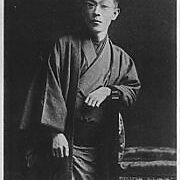
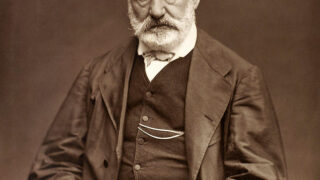













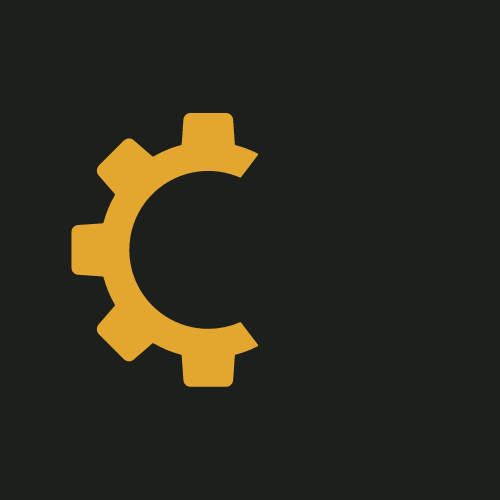
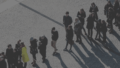

コメント