始めに
三島由紀夫は大学の学部の先輩です。また大学で法学を学んだことが創作にプラスになったと語っています。ここで、三島由紀夫が法学から学んだ創作のエッセンスとはなんであったのか、考えていきます。
語りの構造、背景知識
ジャン=コクトー、ラディゲ流の新古典主義。シュルレアリスム
三島由紀夫は私淑したラディゲ(『ドルジェル伯の舞踏会』『肉体の悪魔』)、コクトー(『恐るべき子供たち』)流の新古典主義が特徴です。端正な線で対象を流離に描く姿勢はここでも発揮されています。
またコクトーはシュルレアリスムの中心的な作家ですが、サド(『悪徳の栄え』)という作家はシュルレアリスムの祖の一人であるアンドレ=ブルトンによって重要視され、ひいては運動全体において重視された作家です。
ラディゲはコクトーなどのモダニスト、シュルレアリストと親交があって、前衛的な文学的潮流と接触していたものの、本人はフランスの心理小説(コンスタン『アドルフ』、ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』)やロマン主義文学(ミュッセ)に習いつつ、古典的な小説スタイルでもって小説を展開していきました。『ドルジェル伯の舞踏会』もクラシックな心理小説『クレーヴの奥方』の翻案として、王宮文学としてのメロドラマを展開します。
『サド侯爵夫人』も『クレーヴの奥方』『ドルジェル伯の舞踏会』に似た、王宮文学として展開されています。
理想化された対象との関係(行為の抽象的なレベルでの解釈)
この作品は、理想化された対象(ルネにとってのアルフォンス)との関係をめぐる作品で大江『取り替え子』、宇佐美りん『推し、燃ゆ』、マン『トニオ=クレエゲル』を思わせますし、また三島の『金閣寺』も連想します。
三島由紀夫はアクションやモチーフ、象徴、状況の設定が上手いです。また『音楽』「憂国」や本作品など、特定のモチーフや状況からの心理やプロットの広げ方が巧みです。この辺りは谷崎潤一郎(『卍』『痴人の愛』)に似た強みを感じさせます。こうした対象に対する観察の感性は、行為の類型を抽象的に理解する法的思考が背景にあるのかもしれません。また意図について行為の客観的態様や一般的な感覚から解釈しようとする法的思考は、三島の心理劇のプロットの礎かもしれません。
規範と実践の関わりへの眼差し
本作が描くのは規範と人との関わりで、これは法学、法社会学が対象とする領域です。本作においてはフランス革命前後が描かれており、古い規範が崩れて新しい規範が生まれる中でその中に生きる母娘であるモントルイユ夫人とルネが描かれます。この辺りは天敵(?)の太宰治『斜陽』やチェホフ『桜の園』とも重なります。
ルネは母を批判し、古い道徳やモラルに安住するばかりの父母を非難しましたが、結局自分自身も夫であるアルフォンスが作ろうとする規範やモラルに迎合するばかりで、美徳を守る『美徳の不幸』のジュスティーヌと変わりがなかったと悟ります。そして夫たるアルフォンスに対しても、規範の破壊者ではなく新しい規範の創造者でしかなかったことを発見します。最後も、アルフォンスと会おうとしないルネの姿が印象的です。
法の全体論的構造、プラグマティックな訂正プロセスに新古典主義者としての姿勢を見る
三島由紀夫はT.S.エリオット的な新古典主義者です。アートワールドの伝統という制度、建築物の中に、解釈や創作という形で新たなピースを付け加え、その全体論的構造の絶えざる訂正を図ります。
法もテクノロジーや倫理学、法哲学の発展や時間的展開の中でその全体論的構造を絶えず修正していきます。三島は法の全体論的構造や、そのプラグマティックな修正プロセスに、新古典主義者としての示唆を受けたのではないでしょうか。
また、法が持つ体系として機能する全体論的構造は、三島由紀夫文学の、それぞれのモチーフやプロットが有機的に機能する特性に影響しているのかもしれません。
現実の社会、事件への関心
三島由紀夫は『金閣寺』『宴のあと』『絹と明察』『青の時代』など、実際の事件に題材をとる作品が多いです。本作も、歴史的題材を下敷きにします。
現実の事件への関心も、法学由来で培われたものかもしれません。
物語世界
あらすじ
第一幕
サド侯爵夫人・ルネの母親であるモントルイユ夫人は、娘婿であるアルフォンス(サド)の無罪を勝ち取るため、シミアーヌ男爵夫人と、サン・フォン伯爵夫人の2人に工作を依頼します。アルフォンス(サド)は、娼婦虐待事件(マルセイユ事件)により追われる身でした。
母・モントルイユ夫人は娘に離婚を勧めますが、ルネはそれを聞きません。ルネの妹・アンヌもイタリアから帰って来て、イタリアでアルフォンス(サド)と一緒だったこと、性的関係を持ったこと、そして、そのことは姉・ルネも知っていると母に話します。
これに激怒した母・モントルイユ夫人は、2人の夫人に依頼した件を取り消す手紙を家政婦・シャルロットに託し、国王にはアルフォンスの居所を教え、逮捕・投獄を嘆願する手紙を自身で届けます。
第二幕
ルネは妹・アンヌから、アルフォンス(サド)を罰金刑で済ます高等法院の再審の結果に喜びます。ところが、夫はその場で今度は王家の警官に捕らえられ、牢獄へ入れられたそうです。それをルネはサン・フォン伯爵夫人から聞き、モントルイユ夫人の申請によるものと知ります。
ルネは母・モントルイユ夫人を責め立て、争います。母はルネに、夫が牢屋にいれば嫉妬もせずにすむのに、どうしてと尋ねます。それは母から学んだ「貞淑」のためだとルネは言います。ルネは、父と母は偽善と慣習の愛で道徳に迎合するばかりだ、そしてアルフォンスは自分自身だ、と言います。
第3幕
フランス革命から9ヶ月。革命で王族や貴族には危険が迫りました。アンヌが一緒にヴェニスへ逃げようと誘うものの、モントルイユ夫人は、牢屋のアルフォンス(サド)が身内にいるから、自分たちは安全だと考えていました。裁判での決定は無効となり、アルフォンス(サド)は戻ってきそうです。しかしルネはシミアーヌ男爵夫人の修道院へ入ると決めます。
なぜかと問う母にルネは、サドが獄中で書いた小説『ジュスティーヌ』を読み、かつて自分が、アルフォンスは自分だと言ったのが思い違いだったとし、美徳を守るジュスティーヌを自分に重ねます。悪の掟を築こうとする夫は、自分の手の届かない領域にいると言います。自分たちが住む世界は、そのアルフォンスの創った世界だと言います。
ルネは残りの人生を、修道院の中で神に伺おうとします。物乞いの老人のようになったアルフォンスが訪ねて来たと聞いても、ルネは会おうとせずに家政婦・シャルロットに、侯爵夫人はもう会うことがないと伝言を伝えます。
関連作品、関連おすすめ作品
・松本大洋『ピンポン』、中上健次『軽蔑』、トーマス=マン『トニオ=クレエゲル』:理想化された他者との関係をめぐるドラマ。
参考文献
・安藤武『三島由紀夫の生涯』(1998,夏目書房)
・Mark Polizotti”Revolution of the MInd:The Life of Andre Breton”(Black Widow pr,2009)
















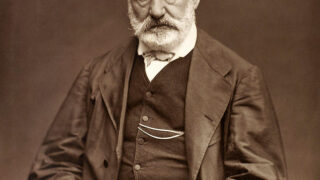





コメント