始めに
オースター『鍵のかかった部屋』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
オースターの作家性
オースターはモダニズムの作家です。
ベケットからは大きな影響があります。ミニマリズム、書くことに対するこだわりなどを継承します。またカフカの幻想文学における不条理やナンセンスからも影響が見えます。またアイデンティティを巡る主題にも共通性があります。
ポーの影響も大きいです。オースターの作品にはしばしば「探偵」が登場しますが、それはポーから続くゴシックの伝統でもあります。『ウィリアム・ウィルソン』的な実存的テーマも多いです。
他にもホーソーン、ソローのロマン主義、クヌート=ハムスンの影響も見て取れます。
形而上学的探偵小説
本作は形而上学的探偵小説のバリエーションと言えます。
形而上学的探偵小説は20世紀の実験小説の文学ジャンルで、形而上学的思弁とミステリー、サスペンスを合わせたものです。ポー『群衆人間』が先駆とされ、他にも発表時期の早いものにチェスタトン『木曜日の男』などがあります。ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』なども、一部この様式が見て取れます。1930年代から1940年代にかけて、ボルヘス、フラン=オブライエン、ウラジーミル=ナボコフ、フェリペ=アルファウなどのモダニズムが展開され、そうした作家の作品にはこのジャンルとされるもの、ジャンルの生成に寄与した作品がいくつかあります。
さらにあとの時期だとピンチョンのサスペンス色の強い作品のほか、ウンベルト=エーコ『薔薇の名前』が特に有名で、ジョルジュ=ペレック、ポール=オースターもこのジャンルの作家です。
タイトルの意味
この物語の最大の特徴は、主人公(「私」)が失踪した旧友ファンショーの人生をなぞるのではなく奪ってしまう点にあります。
主人公はファンショーの未発表原稿を出版し、彼の妻と結婚し、彼の子供を育てます。他人の人生の欠落を埋めることで、自分のアイデンティティを形成しようとします。ファンショーは、主人公にとって自分がなりたかった自分あるいは自分の影のような存在です。他者を追ううちに、自分と他者の境界が崩壊していく過程が描かれます。
ファンショーは、物語のほとんどにおいて姿を見せません。しかし、物語のすべては彼を中心に回っています。人がそこにいないことが、残された人々の人生を縛っています。
タイトルの「鍵のかかった部屋」は、古典的な本格ミステリへのオマージュでありながら、極めて心理的な意味を持っています。それが人の心、あるいは記憶という誰にも踏み込めない場所を指します。物語の終盤、赤いノートが登場しますが、そこには理解できない言葉が並んでいます。真実は、どれだけ言葉を尽くしても結局は鍵のかかった部屋の中にあり、他者が完全に理解することは不可能であるという断念がテーマとなっています。
物語世界
あらすじ
主人公の僕は、失踪した友人ファンショーの妻から、ファンショーの書いた原稿を読んで、価値があれば出版してほしいと依頼を受けます。その依頼に協力しているうちに、二人は魅かれ合います。
ある日、僕のところに、「僕を探さないでほしい」という内容の手紙が届き、ファンショーは生きてるということを知ります。しかしその頃はソフィーを愛するようになっていたため、手紙の通り、ファンショーはいないこととして、ソフィーと結婚します。
その後、ファンショーの本が出版され、一定の評価を得ると、僕にファンショーの伝記を執筆してほしいとの依頼があります。
迷うものの、依頼を受けた僕は、ファンショーの人生を追いかけます。調査していくうちに、僕はファンショーに自分を重ねていくようになり、やがて、自分を見失い始めます。
物語の終盤、ついに「私」はボストンのある家で、ドア越しにファンショーと対峙します。しかし、ファンショーは決して姿を見せず、ドアの向こう側(鍵のかかった部屋)から声を出すだけでした。
ファンショーは語り手にある赤いノートを渡します。そこには彼が隠し持っていた「真実」が書かれているはずでしたが、そこに記されていたのは、およそ理解不能な、意味をなさない言葉の羅列です。
語り手はそのノートを駅のホームで破り捨て、ファンショーという呪縛から逃れようとして、物語は幕を閉じます。




















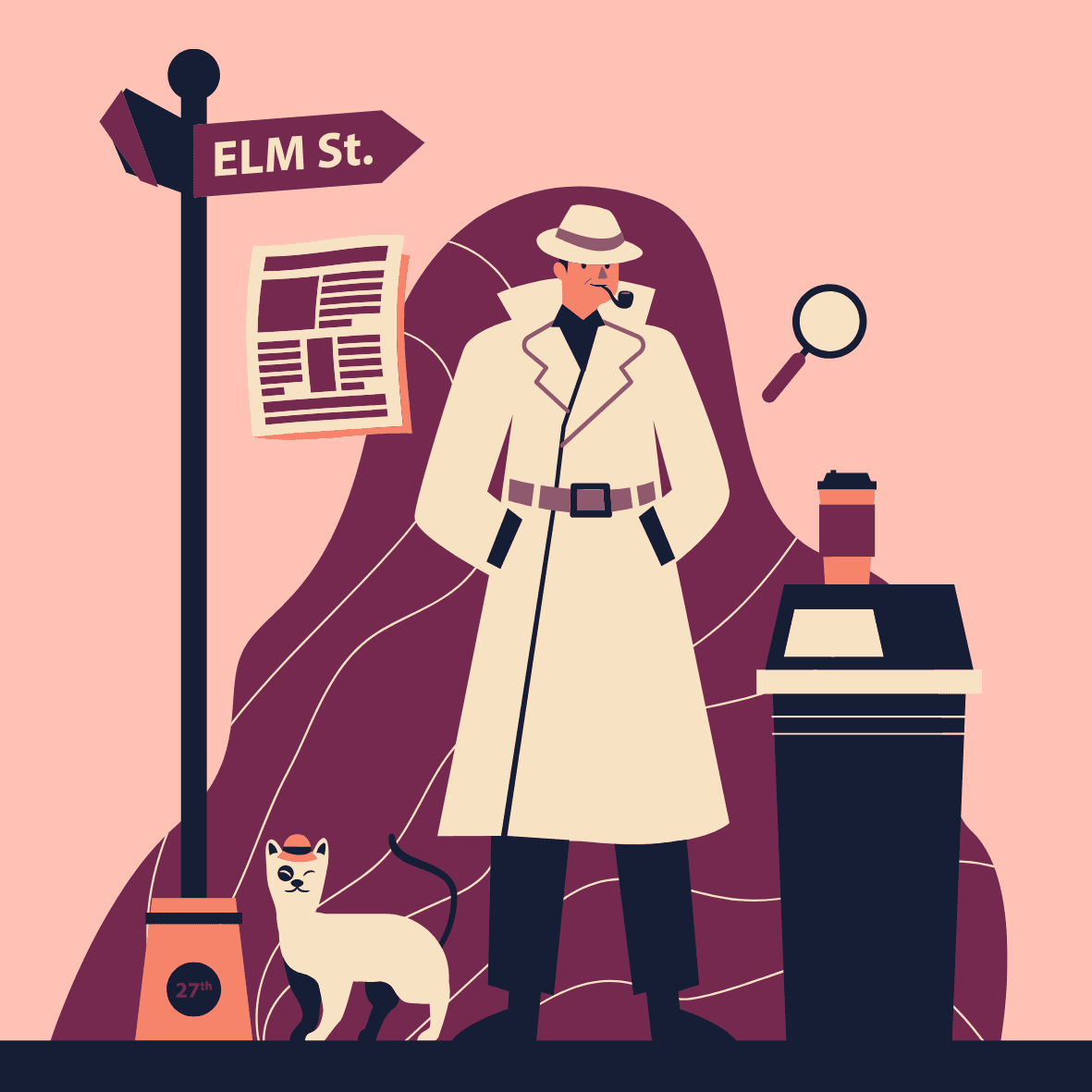


コメント