始めに
三島由紀夫『金閣寺』についてレビューを書いていきたいと思います。若書きですが、才気が迸ります。
語りの構造、背景知識
等質物語世界の語り手・溝口の心理の展開
本作品は実際の「金閣寺放火事件」から構想を得ているものの、例えばフローベール『ボヴァリー夫人』のような感じで、実際の事件に緻密に取材してそれに則って書いたものというより、そこから着想を得て自由な空想で膨らませた感じの内容です。『仮面の告白』とも似て、三島由紀夫の自伝的作品としての色合いも濃く、作家の価値観を体現するものと言えます。
本作の語り手は溝口という男で、幼い頃から「金閣寺」の空想に取り憑かれそれを理想化しつつ、一方で現実の「金閣寺」に対して理想とのズレを感じ、けれどもそんな「金閣寺」へ大戦中に炎が迫り、崩壊の危機を迎えるとその悲劇性のうちに理想の「金閣寺」を感じました。理想のうちの「金閣寺」と現実の「金閣寺」の不一致に悩み、それに異性との関係に悩む性的コンプレックスや、仏教的コミュニティへの幻滅などが絡んで、理想の「金閣寺」を現実で実現させるための「行動」へと至ります。
古典主義(ラディゲ、コクトー)。リアリズム
三島由紀夫はラディゲ(『ドルジェル伯の舞踏会』『肉体の悪魔』)、コクトー(『恐るべき子供たち』)といったフランスの古典主義文学に影響を受けています。私淑した二人にも相通じる、作品全体が合理的に構造としてデザインされた戯曲、家庭小説には佳品が多いですが、純文学作品には駄作も多いです。また純文学でいいのは『仮面の告白』や本作など初期の作品に多いです。
本作はラディゲ『ドルジェル伯の舞踏会』に似た、宮廷文学になっています。ラディゲはコクトーなどのモダニスト、シュルレアリストと親交があって、前衛的な文学的潮流と接触していたものの、本人はフランスの心理小説(コンスタン『アドルフ』、ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』)やロマン主義文学(ミュッセ)に習いつつ、古典的な小説スタイルでもって小説を展開していきました。『ドルジェル伯の舞踏会』も、クラシックな心理主義文学のラファイエット夫人『クレーヴの奥方』の翻案です。
本作では、金閣寺という王宮文学を彷彿とさせる古典的な美が中心的モチーフになっていて、スタンダール『パルムの僧院』などを連想させられます。
シュルレアリスム(アウトサイダーアート、堀辰雄)、郡虎彦(ニーチェ)
本作品はシュルレアリスムの流れをくむ作品で、シュルレアリスムの祖アンドレ=ブルトンも、ブルジョワ社会に対するアンチテーゼとして実際の犯罪者に着目しましたが、同様に本作も実際の犯罪者に取材して書かれています。三島由紀夫のフォロワーであり、永山則夫という少年犯罪者に惹かれた中上健次など、シュルレアリスムの方面で実際の犯罪者に着目するモードがあります。
また、三島由紀夫は堀辰雄からの影響も知られ、本作のラストにおいて「金閣寺」が炎に包まれるのを見て生きる意志の起こる展開は、堀辰雄『風立ちぬ』におけるヴァレリーからのエピグラフを連想させられます。
シュルレアリスムは精神分析などに依拠し、人間の本性的性質や原始的な計算モジュールに注目するという点で身体的運動と言えますが、三島由紀夫にとって、そのような身体性を代表するのは、早逝した郡虎彦経由で取り込んだニーチェでした。本作は観念的な語り手の溝口が、美を実現するための身体的な「行動」へとドライブされる様が描かれます。
モデル
モデルは金閣寺放火事件です。
金閣寺放火事件は、1950年7月2日未明に鹿苑寺(金閣寺)で発生した放火事件で、同寺の徒弟僧である林承賢が、国宝の舎利殿に放火し、同建築と足利義満像を全焼させました。
林は懲役7年の判決が下り、確定しましたが、その後、収監中に結核と精神が悪化し、釈放されてのちの1956年3月7日、26歳で病死しています。
林は鹿苑寺への入山後、住職の後継者となって金閣寺を支配することを望んでいたものの、住職に冷遇されている、と被害妄想を抱き、舎利殿と足利義満坐像を燃やし、自殺することを決意していました。
吃音など、林をモデルとする溝口の要素は多いものの、理想の金閣と現実の金閣の不一致の苦悩という溝口の心理は三島の脚色が大きいです。
シュルレアリスムの影響。ジュヴナイル。青春残酷物語
三島由紀夫が好んだシュルレアリスムのコクトー『恐るべき子供たち』もティーンの世界を描いたグランギニョルな青春物語です。また、先述の通りシュルレアリストのブルトンは既成の芸術やブルジョア社会へのカウンターとして、実際の若い犯罪者に着目するなどし、モロー(「出現」)の絵画に描かれるファム・ファタル表象に着目しました。シュルレアリスムの影響が顕著な三島由紀夫の本作や『青の時代』、中上健次(『千年の愉楽』)の永山則夫への着目もこうしたモードの中にいて、グランギニョルな青春物語を展開しました。
同様に、ヌーヴェルバーグのゴダール監督もこうしたモードの中で『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』のような青春残酷物語を展開しました。
象徴主義、シュルレアリスム的なグランギニョル
本作はグランギニョルな、滅びの美の醸す崇高さに着目する内容です。崇高さとは、快と不快が入り混じった美的経験や対象です。
太平洋戦争で戦況が激化する中、金閣も溝口も共に空襲で焼け死ぬかもしれなくなり、そんな金閣は溝口の理想の、悲劇的な美をたたえて見えました。やがて、戦争が終わり、金閣と「私」(溝口)とが同じ世界に住んでいる夢想も崩れ、溝口は苦悩し、やがて金閣寺と心中しようとします。
この辺りは精神分析などの心理学、コクトー(『恐るべき子供たち』)、サド(『悪徳の栄え』)の他、リラダンなどの象徴主義文学、森鴎外(「阿部一族」)、ダンヌンツィオなどがグランギニョルなモチーフやプロットの崇高さ(不快かつ快)に着目した表現を展開したのと重なります。
三島由紀夫が好んだ森鴎外にも「堺事件」「阿部一族」「興津弥五右衛門の遺書」といった切腹をモチーフにする物語があり、本作にえがかれる溝口の金閣寺との心中の願いはそれとも重なります。心中の美はダンヌンツィオが『死の勝利』などで描き、三島も『憂国』にも描いています。
理想化された対象と現実の不一致
本作は『サド侯爵夫人』などにも見られる、理想化された対象と現実の対象との間でエージェントが思い悩む様が描かれています。その点で三島にとって重要な作品です。
三島という作家は、常に理想と現実の間で悩み続けた作家でした。そもそも三島由紀夫はどちらかといえば、内向的で観念的な世界にこもるタイプの人間でしょうが、そうした傾向は本作から一貫して否定的に描かれていると感じます。
三島が志向したのは、行為を通じた現実社会へのコミットメントによって自己実現を図るニーチェ的な行動主義者としての自己でした。本作も語り手・溝口が観念の世界より抜け出して現実における行為によって理想を実現する様が描かれます。そんな自己のイメージにおいても理想と現実の間で悩み続けた三島は、『ライ麦畑でつかまえて』のホールデンのような人であり続けました。
溝口は自分の美の理想としての金閣寺を幼少から思い描いていて、それが現実にはないのに悩み、苦悩します。こうした幼少期から抱く青春の幻想としての空虚な金閣寺はフルニエ『モーヌの大将』の影響を伺わせます。
ドストエフスキー『罪と罰』との比較から
本作は、しばしばドストエフスキー『罪と罰』と比較されます。いずれも犯罪者の主人公の心理描写を特徴としています。
けれども異なっているのは、『罪と罰』はバルザック(『従妹ベット』)由来のリアリズム寄りで、殺人を犯してしまった主人公・ラスコリニコフの社会的な規範や法との衝突を喜劇として描くのに対して、本作がテーマにするのはあくまでも理想と現実の間での心理的葛藤の描写です。『罪と罰』は理想に囚われ凶行に走ったラスコリニコフの愚行を社会的規範や法的実践の中で相対的に描くのに比して、本作は理想と現実の差異に思い悩む語り手の葛藤を描き、それを行為で実現するまでが描かれます。
映画化など
本作は市川崑監督『炎上』(1958)、高林陽一監督『金閣寺』(1976)年などとして映画化されています。市川崑は三島由紀夫も好んだ監督で、共にジャン=コクトーが好きという共通点がありました。『炎上』はシャープな線で捉えるフォルマリスティックな内容で、原作よりリアリスティックというか観念的な世界のニュアンスが出ていないです。高林の方が抽象的な主題が出ていて寺山修司などのアングラ演劇(サルトル、ブレヒト、ベケット[『ゴドーを待ちながら』])風味の脚色ですが、完成度は市川のものに劣ります。
また市川崑の熱烈なファン・岩井俊二の『リリィ=シュシュのすべて』が、本作を強く意識した内容です。
物語世界
あらすじ
成生岬の貧しい寺に生まれた溝口は、僧侶である父から、金閣の話を聞かされて育ちます。溝口は金閣を夢想し、理想化して抱いていました。体も弱く吃音のためにいじめられ、引っ込み思案となり、コンプレックスのために美しい短剣の鞘に傷をつけたこともありました。有為子という女に嘲られ、女と自分とのあいだに溝を感じます。
やがて溝口は、父の修行時代の知人が住職を務める金閣寺に入り、修行生活を始めます。実物を目の前にしてやや幻滅した溝口でした。しかし戦況が激化する中、金閣も自分も共に空襲で焼け死ぬかもしれなくなり、金閣は悲劇的な美をたたえて見えました。
同じ徒弟生活で出会った鶴川は、明るい青年で、溝口の吃音を馬鹿にしない唯一の友でした。
やがて、戦争が終わり、金閣と「私」(溝口)とが同じ世界に住んでいる夢想も崩れます。溝口は住職の老師の計らいで入学した大谷大学で、両足に障害をもつ級友・柏木と出会います。柏木は女の扱いに長けていて、障害を逆手にしている男でした。そんな彼に一旦感心しながらも否定的に捉え、とはいえ友人となります。
もう一人の友人の鶴川が死に、「事故」ということでした。溝口はこの頃金閣寺の妄想に囚われて性的不能になり、溝口は金閣に憎しみを抱きます。溝口が女の美を目の前にすると、いつも金閣が現れて相対化してしまいます。
正月のある日、溝口は雑踏の中で、芸妓を連れ歩く老師に行き会い、険悪になります。溝口は老師を試そうと、愛人の芸妓の写真を、老師が読む朝刊にはさみます。写真は無言で溝口の机の抽斗に戻されました。
次第に溝口は学業の成績も落ち、大学も休みがちになります。溝口は将来の望みを断ち切っていきます。父の縁故でゆくゆくは後継にと目されていた溝口ですが、老師から後継にする心づもりはないと宣告されます。
孤独を増す溝口に、柏木は鶴川から死の直前に届いた手紙を見せます。鶴川は、自殺の前に柏木のみに本心を打ち明けていたのでした。鶴川を、翳りのない心を持っていると信じていた溝口には衝撃でした。柏木は溝口に、世界を変貌させるのは「認識だ」と説きます。しかしこれに対し溝口は「行為だ」と反駁します。
溝口は、金閣寺放火を妄想します。そのとき眺めた金閣寺は、幻の金閣と一致し、虚無の美しさにかがやきました。
溝口は金閣寺に火を点け、燃え盛る金閣の中で死のうとするものの、扉は開きません。拒まれていると意識した溝口は、戸外に飛び出し山へ駆けます。火の粉の舞う夜空を、眺めた溝口は「生きよう」と思います。
関連作品、関連おすすめ作品
・松本大洋『ピンポン』、三島由紀夫『サド侯爵夫人』、中上健次『軽蔑』、トーマス=マン『トニオ=クレエゲル』:理想化された他者との関係をめぐるドラマ。
参考文献
安藤武『三島由紀夫の生涯』







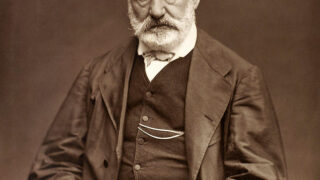














コメント