始めに
始めに
チェーホフ『桜の園』解説あらすじです。
語りの構造、背景知識
トルストイ流のリアリズム、メーテルリンク流のシンボリズム
チェーホフはトルストイ(『戦争と平和』『アンナ=カレーニナ』)流のリアリズム、メーテルリンク流のシンボリズムの影響が強いです。
よくジェイムズ=ジョイスと作風が似ているとも指摘されますが、ジョイスは『ダブリン市民』を著したとき、チェーホフは読んでいなかったといいます。ジョイスの場合、イプセン(『民衆の敵』『人形の家』)のリアリズム演劇や象徴主義の影響が強く、偶然似ている模様です。
日常に見える時代の変遷
『桜の園』は時代の変化に順応できない地主貴族の家族の没落と、俗物的な強かさでブルジョワジーとして自己実現する商人・ロパーヒンが対比的に描かれています。また貴族の家族の内でも、現実を直視せず、過去の栄光に縋り続けるリューボフ=ラネーフスカヤ(リューバ)と、現実を受け入れ、新たな人生へと飛び立つ娘・アーニャも対照的に描かれています。
同様の社会のブルジョワジー化を描くフローベール『ボヴァリー夫人』では、俗物の強かさを描いています。それを代表するのが薬剤師のオメーで、こうありたい自己との乖離に悩むボヴァリー夫人とは対象的に自分の理想に悩むことはせず、黙々と社会のモラルに迎合するかたちで精進し、立身出世を果たします。ボヴァリー夫人のこのような役回りはリューバと重なりますが、ロパーヒンはオメーと比べるとずいぶん思慮深い人間です。
また太宰治の『斜陽』が本作品の影響で書かれていることはよく知られていますが、こちらもペーソスある語り口の中で綴られる貴族の没落と、女性の自立と強かさが対比的に描かれています。
ささやかな生活のデッサン
この作品では特に大きなプロットの起伏があるわけではありません。けれどもささやかな日常をペーソスとユーモアで包み、豊かな表現で体制の変化が描写されています。
日常デッサンの中に、ブルジョワ化という社会の変化を主題として盛り込む手腕が卓越しています。
メロドラマとして
本作では恋愛模様が群像劇として展開されていきますが、いずれもあまり上手くはいきません。
小間使いのドゥニャーシャは事務員のエピホードフにプロポーズされるものの、召使ヤーシャに恋して失恋します。
ロパーヒンとラネフスカヤの養女ワーリャは互いに意識し合うものの、結ばれません。
ラネフスカヤは恋人とよりを戻そうとするものの、うまくいきません。
フィクション世界
あらすじ
第1幕
ラネーフスカヤが娘・アーニャの付き添いでパリから自分の土地へ戻ります。帰還を喜ぶものの、富を失い金に困る一家です。領地の桜の園は借金返済のため売りに出されています。商人・ロパーヒンは土地の一部を別荘用地として貸し出すべきと助言するものの、ラネーフスカヤは真剣に受け止めようとしません。ラネフスカヤの兄弟のガーエフは知人や親戚から借金します。
第2幕
小間使いのドゥニャーシャは事務員・エピホードフにプロポーズされていたものの、召使い・ヤーシャに恋します。
ラネフスカヤの養女ワーリャとロパーヒンは前々から互いを意識しているものの、関係は進展しません。アーニャは進歩的な大学生・トロフィーモフに憧れ、自立を決意します。
第3幕
ラネーフスカヤはパリの恋人とよりを戻すことを考えて、それに否定的なトロフィーモフと口論になります。エピホードフはワーリャと喧嘩になります。
そこへガーエフが帰宅します。ロパーヒンが現れ、自分が桜の園を買ったと言います。アーニャは泣き崩れる母を慰めました。
第4幕
ラネーフスカヤはパリへ戻り、ガーエフ達は町へ移ります。ドゥニャーシャはヤーシャに捨てられました。ロパーヒンはワーリャへのプロポーズを断念します。
老僕・フィールスはひとり屋敷に残され、横たわり身動きひとつしなくなります。
登場人物
- リューバ:地主貴族としての過去の栄光に縋り、現実を直視できない。
- アーニャ:一家の現実を理解している。自立した女性
- ロパーヒン:元農奴の商人。ブルジョワ社会の成功者。リューバに的確な助言をするも受け入れられず。
総評
ささやかな日常デッサンで捉える社会の変動
ささやかな日常デッサンですがそこが良いです。また、移ろい行く時代の変化が滲んでいます。
関連作品、関連おすすめ作品
参考文献
・アンリ=トロワイヤ 村上香住子訳『チェーホフ伝』(中央公論社.1992)
・リチャード=エルマン 宮田恭子『ジェイムズ=ジョイス伝』(みすず書房.1996)
・野原一夫『太宰治 生涯と文学』(筑摩書房.1998)


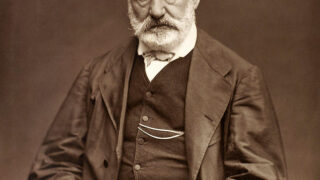

















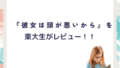

コメント