始めに
三島「花ざかりの森」解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ジャン=コクトー、ラディゲ流の新古典主義。シュルレアリスム
三島由紀夫は私淑したラディゲ(『ドルジェル伯の舞踏会』『肉体の悪魔』)、コクトー(『恐るべき子供たち』)流の新古典主義が特徴です。端正な線で対象を流離に描く姿勢はここでも発揮されています。
ラディゲはコクトーなどのモダニスト、シュルレアリストと親交があって、前衛的な文学的潮流と接触していたものの、本人はフランスの心理小説(コンスタン『アドルフ』、ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』)やロマン主義文学(ミュッセ)に習いつつ、古典的な小説スタイルでもって小説を展開していきました。『ドルジェル伯の舞踏会』もクラシックな心理小説『クレーヴの奥方』の翻案として、王宮文学としてのメロドラマを展開します。
モダニズムと輪廻
T=S=エリオット『荒地』の下敷きとなった文化人類学者フレイザー『金枝篇』が、ネミの森の王殺しの儀式の伝統に対して、自然の象徴である森の王が衰弱する前に殺すことで、自然の輪廻と転生のサイクルを維持するためだという解釈を与えています。ここから以降のモダニズム文学に輪廻や転生のモチーフが現れるようになりました。
たとえばサリンジャー『ナイン=ストーリーズ』などにもその影響が伺えます。中上健次『千年の愉楽』、三島『豊饒の海』シリーズ(1.2.3.4)、押井守監督『スカイ・クロラ』などにも、モダニズムの余波としての転生モチーフが見えます。
三島の師匠の川端も『水晶幻想』や『抒情歌』などで輪廻転生のモチーフがあって、モダニズム文脈や王朝文学への関心などが手伝っています。
本作も輪廻と転生のモチーフが見え、三島『豊饒の海』シリーズ(1.2.3.4)へとつながっていくものが見えます。
また川端『水晶幻想』やプルースト『失われた時を求めて』などと重なる、一人称的視点をうまく生かした映像的なモンタージュの実験が展開されていきます。
語りの構造
本作は「わたし」という、等質物語世界の語り手が設定されていて、これが過去や先祖のことを回想したり、幻想的な経験を追憶したりするなかで物語が展開されていきます。
意識の流れのような手法によって、映像的なイメージのモンタージュが展開されていき、作品は「川」や「独楽」のモチーフをうまく用いて、「輪廻」や「循環」の主題を演出します。
物語世界
あらすじ
この土地へ来てから、「わたし」はよく追想するようになりました。「わたし」はときどき、遠くの池のベンチなどで、微笑し佇んでいる「祖先」と邂逅します。「その人」は、背広を着た青年や、若い女であったりします。「その親しい人」は地味な目立たない身なりをし、快活に走るように、ある距離まで「わたし」に近づいてくると、魚が「水の青み」に溶け入るように木漏れ日に融けて紛れてしまいます。
「わたし」は自身の生まれた家を追想します。祖母、母、父、そして、祖先たちから自分へと川のように続く「一つの黙契」に思いを馳せます。祖母と母においては、川は地下を流れ、父においては、せせらぎになりました。「わたし」において、それが滔々とした大川にならないで何になろう、と考えます。
死んだ祖母の持ち物から、熙明夫人の日記が見つかります。彼女もまた「わたし」の祖先です。夫人の日記を見ると、彼女はある夏の日に、百合の叢のあいだに光る白いものを見ていました。それは一度見たことのあるような女人です。そしてその胸には夫人の母が身につけ、今は自分が付けている十字架が光っていました。それから半年後、熙明夫人は亡くなるのでした。
平安末期、ある女人が情夫の殿上人へ捧げた物語があります。その殿上人も、「わたし」の遠い祖先の1人でした。女人には幼なじみの寺の坊主がいたものの、この男は煩悩が捨てきれず、彼女に手紙をよこします。彼女は殿上人のつれなさや当てつけから、その幼なじみの坊主へ心を傾けます。修行僧の坊主は女人と都を出奔し、ふるさとの紀伊に来ます。女はひとり海辺に立ってから気が変り、密かに男から逃れて京の都へ戻り尼になります。女は、「海への怖れは憧れの変形ではあるまいか」などと書き記していました。
「わたし」は1枚の写真を見ます。それは「わたし」の祖母の叔母です。彼女は幼い頃から海に憧れていました。そして、いつの頃からか彼女の死んだ兄が言っていた「海なんて、どこまで行ったってありはしないのだ」という言葉の意味がわかるようにもなってきたものの、海を見ることは変らず好きでした。彼女は伯爵である夫が死んだのち、或る豪商に求められ再婚します。南の海で仕事をしていた豪商は、東京で住いを営みたいと考えたものの、彼女の希望で夫婦は南の海の島で暮らします。しかし、島での生活に彼女の憧れは満たされず、まもなくこの夫と別れて帰国します。そして彼女は純和風な家を建て死ぬまでの40年間、独り身の尼のように暮しました。
老いた彼女は客人を庭に案内します。竹林を抜けた高台に立つと、そこから海も見えます。毅然と立つ白髪の彼女の顔は涙ぐんでいるのか祈っているのか判らず、客人は、樫の高みが風に揺れた瞬間に眩ゆく白い空を見ます。その時、客人は故知らぬ不安で、死にとなり合わせのような感覚を味わったかもしれません。それは、回転する独楽(こま)が極まって澄むような静謐、生の極み、いわば「死に似た静謐」と隣り合わせに感じたかもしれません。




















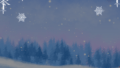

コメント