はじめに
セリーヌ『夜の果てへの旅』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
ラブレー的な伝統
セリーヌはラブレー(『ガルガンチュアとパンタグリュエル』)的な口語的コミュニケーションのフランス文学の伝統の上で作品を展開していきました。
ラブレーは『ガルガンチュアとパンタグリュエル』で知られるフランスのルネサンス作家で、大江健三郎への影響がしられます。生き生きとした口語的語り口に見える生の哲学が印象的です。
本作も、同様にダイナミックな口語的な語りを、セリーヌの分身であるフェルディナンを語り手として設定し、展開します。
実存主義と自伝
本作はサルトルに影響したことで、実存主義を代表する作品となりました。
サルトルの実存主義に関しては、ざっくり話すとハイデガーの実存主義哲学、プラグマティズムや、セリーヌ作品などからの影響を受け、一個のエージェントがその伝記的な背景などを背景に世界にコミットメントするプロセスに関して、構造的な把握を試みたものです。対自存在(自分自身を対象として意識する存在。志向する対象とする存在)としての人間は、世界の中にある他のエージェントからの相互的な役割期待があり、世界の中で自分自身をデザインしていく自由と責任があることをモデルとして提起しました。
またサルトルは実存主義において、未来に向かって現在の自己を抜けでて自覚的に自己を創造していくことをもとめ、さらにそれが社会や世界に対して、そして人類の未来に対して責任を負うアンガージュマン、社会参画を唱えました。
セリーヌの実存主義的文学
セリーヌの文学作品は、そのようなアンガージュマンと実存主義の世界といえます。なぜならばセリーヌの文学作品は自己の伝記的バックグラウンドを背景に、対自存在としての作家が現実社会、世界へのコミットメントを果たす中で紡がれていく表現だからです。
本作もセリーヌの自伝的な内容となっています。
生の哲学と保守主義、反戦思想、レイシズム
セリーヌは、ユダヤ人への差別で知られます。一方でラディカルな反戦思想をも唱えていました。
少しセリーヌの思想は日本人にはわかりにくいですが、ざっくり抽象化すると、セリーヌは保守主義者であって、フランスの民衆の実践を評価し、彼らの生の営みを収奪する戦争に逆らいます。これは『戦争と平和』のトルストイなどと共通です。
一方で、セリーヌはまた、フランス文学に通底する反ブルジョアジー的な潮流にいます。有名なところだとフローベール『ボヴァリー夫人』などですが、ブルジョアジー、成金文化への批判的な視座は、近代フランス文学の特徴です。このブルジョワジー文化を、フランスの民衆の実践を堕落させるものとして捉えるセリーヌには、その権化と映るユダヤ人、ユダヤ系資本は唾棄すべき存在となっていて、ここからレイシズムに繋がってしまっています。
物語世界
あらすじ
語り手フェルディナン=バルダミュは、パリの医学生です。
第一次世界大戦に際して、バルダミュも戦場に赴きます。しかし、戦争の無意味さを感じ、戦場から逃れようとします。
夜間偵察中、バルダミュはドイツに投降しようとしているレオン=ロバンソンと会い、二人でドイツに投降しようとするものの、実現しません。
その後バルダミュは戦場で負傷し、戦線から離脱します。そしてバルダミュは除隊されます。
行く当てを失ったバルダミュは世界を遍歴することにし、フランスの植民地のアフリカに向かいます。アフリカでロバンソンに再開し、植民地支配の欺瞞を見せつけられます。
またバルダミュはアメリカのデトロイトに行き、自動車工場で職を探します。しかし、資本主義の象徴である自動車工場にもなじめずデトロイトを離れます。
バルダミュはフランスで医者となり、貧民の暮らすランシィで医者を開業する。そこでバルダミュは貧民街の過酷さや、義母や夫を亡き者にしようと企む女性アンルイユなど、絶望的な人々に出会う。
アンルイユは、ロバンソンを雇って義母を爆殺しようとするが、失敗しロバンソンは視力をほとんど失う。
バルダミュはランシィも離れて、パリに赴くが、そこでもロバンソンとの腐れ縁は切れず、絶望的な毎日を送ることになります。
参考文献
・Damian Catani ”Louis-Ferdinand Céline: Journeys to the Extreme”








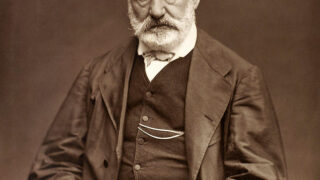



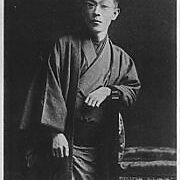









コメント