始めに
イヴリン=ウォー『一握の塵』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ウォーの作家性
ウォーの初期の作風に最も技術的な影響を与えたのは、世紀末デカダンスの流れを汲むロナルド=ファーバンクです。断片的な対話の構成や、ミニマリズムに影響しました。またウォーはP.G.ウッドハウスを師匠と呼び、その完璧な英語の文章を崇拝していました。
H. ベロックとG.K. チェスタトンは、ウォーが1930年にカトリックに改宗する精神的な支柱となりました。ブルジョワ社会への懐疑、保守主義を継承しました。特にベロックの好戦的なカトリシズムと、文明の衰退に対する歴史観から示唆を受けています。
また詩人エリオットが『荒地』で描いた「荒地」のイメージは、戦間期の混乱を生きるウォーの世代に共通の背景を与えました。代表作『一握の塵(A Handful of Dust)』のタイトルは、エリオットの『荒地』の一節から取られます。
ほかにサッカレーも、ウォーの諷刺家としての視点に影響を与えています。上流階級や中産階級の虚飾を剥ぎ取る社会諷刺の姿勢を受け継ぎます。
荒地の悲劇
主人公トニー=ラストは、古い道徳や伝統、そして自身の邸宅「ヘットン=アビー」を心から愛する保守的な紳士です。トニーは騎士道精神や古き良き秩序を信じていますが、周囲の人間、特に妻のブレンダは極めて現代的で、功利主義的です。彼の信じる礼儀や伝統は、現代社会の冷酷な不倫や金銭欲の前では、自分を守る武器にすらならないことが残酷に描かれます。
タイトルの由来は、T.S.エリオットの詩『荒地』の一節(「一握の塵の中に恐怖を見せてやろう」)から来ています。1930年代のロンドン社交界は、享楽的で、他人の不幸に無関心な「精神的な砂漠」として描かれます。
『ブライズヘッド』には信仰という救いがありましたが、本作には救済が一切ありません。息子を事故で亡くした際、妻のブレンダが「死んだのが(息子の)ジョンではなく(愛人の)ジョン=ビーバーでなくて良かった」と安堵する描写は、精神的荒廃の象徴です。
物語の後半、トニーは理想の輝ける都市を求めてブラジルの密林へ向かいます。彼はジャングルの中で行き倒れ、文盲の老人トッドに助けられますが、そこで死ぬまで永遠にディケンズの小説を朗読し続けるという奇妙で絶望的な監禁生活を強いられます。文明的なイギリスで「騎士道」を重んじた男が、野蛮な密林で文明の象徴(ディケンズ)を読み続けさせられるのでした。
物語世界
あらすじ
主人公トニー=ラストは、先祖代々の屋敷「ヘットン=アビー」をこよなく愛する、真面目で保守的な紳士です。彼は妻のブレンダと幼い息子ジョン=アンドルーと共に、理想的な英国貴族の生活を送っていると信じていました。
しかし、都会の刺激を求めるブレンダは、田舎暮らしとトニーの古臭い価値観に退屈しきっていました。ブレンダは、ロンドンの社交界で寄生虫のように生きる貧乏青年ジョン=ビーバーと不倫を始めます。トニーは妻を信頼しきっており、彼女がロンドンで過ごす時間が増えても疑おうとしません。
そんな中、決定的な悲劇が起こります。一人息子のジョン=アンドルーが、乗馬中の事故で急死してしまうのです。
息子の死のあと、報せを聞いたブレンダは、最初、死んだのが愛人のジョン(ビーバー)だと思い込み、動揺します。しかし死んだのが息子のジョンだと分かると、彼女は思わず「ああ、良かった」と口にしてしまいます。この瞬間、彼女の中で息子や夫への愛が完全に枯れ果て、代わりに「塵」のような虚無と身勝手さが支配していることが明らかになります。
ブレンダはトニーに離婚を切り出し、愛人ビーバーと結婚するためにトニーから多額の慰謝料をむしり取ろうと画策します。
当初は紳士的に振る舞おうとしたトニーですが、彼女たちのあまりの強欲さと、愛着ある屋敷ヘットン・アビーを手放さざるを得ない状況に追い込まれ、ついに絶望します。
すべてを捨てて、探検家メッセンジャー博士と共に、伝説の輝ける都市を探すべくブラジルの密林へと旅立ちます。
アマゾンの探検は失敗に終わり、博士は死亡。トニーも高熱にうなされ、ジャングルの奥地で行き倒れます。
彼を救ったのは、その地を支配する文盲の老人トッドでした。命を救われたトニーですが、トッドは恐ろしい条件を突きつけます。トッドは熱狂的なディケンズのファンであり、トニーに対し、死ぬまで毎日、ディケンズの小説を朗読し続けることを強要したのです。
一方、イギリスではトニーは死亡したものと見なされ、ヘットン・アビーは親族の手に渡ります。ブレンダは結局ビーバーにも見捨てられ、別の男と再婚します。
トニーは救助の望みが絶たれた密林の中で、今日も終わりなきディケンズの朗読を続けています。






















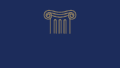
コメント