始めに
ドストエフスキー『悪霊』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
ゴーゴリからバルザック風のリアリズムへ
ドストエフスキーはキャリアの初期には特に初期から中期のゴーゴリ(「鼻」「外套」)の影響が強く、『貧しき人々』も書簡体小説で、繊細かつ端正なデザインですが、次第に後期ゴーゴリ(『死せる魂』)やバルザック(『従妹ベット』)のリアリズムから影響されつつ、独自のバロック的な、アンバランスなリアリズム文学のスタイルを確立していきます。
語りの構造
G(アントン=ラヴレンチエヴィチ)が「わたし」と名乗る物語の語り手で、新聞記者です。自分の経験については一人称、取材によって明らかになったこと等については、新聞記者としての立場から三人称が用いられます。
実際は等質物語世界の語り手ですが、物語世界内からの語りと物語世界外からの語りを併用するデザインで、『カラマーゾフの兄弟』もこれと近いです。
バフチンの指摘。プラグマティックな社会の再現
バフチンはポリフォニーという概念でもって、ドストエフスキー作品を分析しました。バフチンは社会学、哲学(新カント学派)、現象学(フッサール、ベルクソン)から顕著な影響を受けましたが、バフチンの文芸批評はそこから影響がみえます。
バフチンがドストエフスキーの文学について解釈していたのは、そこに描かれる物語が、物語世界内にコミットする一人ひとりのエージェントの戦略的コミュニケーションの集合の帰結として展開されているということでした。本作は主人公であるスタヴローギンだけではなく、ピョートル、キリーロフなど、他のサブキャラクターもさまざまな目的を持ち、戦略的コミュニケーションを展開していきます。その集積の中で物語が紡がれていくのです。このようなプラグマティズム的な発想が、ドストエフスキーのリアリズムの特徴です。
他の作品では例えば冨樫義博『HUNTER×HUNTER』、ハメット『マルタの鷹』、谷崎潤一郎『卍』エドワード=ヤン監督『エドワード=ヤンの恋愛時代』などに近いですが、物語は偏に特定のテーマや目的に従うべくデザインされている訳ではなく、エージェントがそれぞれの選好、信念のもと合理性を発揮し、これが交錯する中でドラマが展開されていきます。このようなデザインは、現実社会における政治学・社会学(システム論、エスノメソドロジー)や国際関係論におけるリアリズム/リベラリズム/ネオリベラリズム/ネオリアリズムが想定する人間関係や国際関係に対するモデルと共通します。バフチンがドストエフスキーに見出したのもまさにこのようなデザインが現実社会における実践の正確な再現である点だと思います。
実践に根ざさない理想と共同体の破綻。ネチャーエフ事件
本作で描かれるのは『罪と罰』とも共通しますが、実践に根ざさない理想や共同体の破綻です。本作はネチャーエフ事件が元ネタで、ペトルーシャの文学サークルを装った革命組織が、スタヴローギンをその中心にしていく中で相互不信がエスカレートしてカルト的なコミュニティとなっていき、やがて破滅的な顛末に至るまでが描かれます。心理的な合理性や信念の変節に関する観察の研ぎ澄まされた眼差しがドストエフスキー文学の見どころです。
セルゲイ=ネチャーエフは、「世界革命同盟」という架空の団体のロシア代表部代表を名乗り、「人民の裁き」と呼ばれる秘密結社を作るのですが、組織内部には相互不信による対立が沸き起こります。ネチャーエフは、構成員の一人でペトロフスキー農業大学の学生であったイワン=イワノフを裏切り者とし、1869年11月21日にペトロフスキー農業大学にて彼を銃殺し、これがネチャーエフ事件です。ネチャーエフは亡命などをへて最終的には獄死します。
ツルゲーネフ批判
カルマジーノフという文豪気取りの俗物作家が現れ、これはツルゲーネフ(『父と子』『初恋』)がモデルです。これをきっかけにドストエフスキーとツルゲーネフは険悪になります。
西洋化主義で進歩的なツルゲーネフと保守主義でギリシャ正教とスラブ主義を重んじるドストエフスキーはもともと相性が悪く、ここで決裂は決定的になりました。
物語世界
あらすじ
1869年。ロシアのとある地方都市と、その郊外にあるスクヴォレーシニキと呼ばれる領地を舞台にします。
ステパン氏は、ロシアを代表する自由主義者でしたが、今はスタヴローギン家の女主人ワルワーラ夫人の世話を受けています。ワルワーラ夫人は、自分の養女であるダーシャとステパン氏を結婚させようとしますが、これに対しステパン氏はスイスにいるピョートルに助けを求めます。スタヴローギン家の一人息子であるニコライは、ステパン氏のもとで教育を受けたあと学習院に進学し、卒業後に放蕩に耽りました。また2度も決闘事件を起こし、町から放逐されましていた。
その後、ワルワーラ夫人は、スタヴローギンとマリヤ=レビャートキナの関係をほのめかす匿名の手紙を受けとり、マリヤを家へ連れ帰り問い詰めようとします。この日は、ステパン氏とダーシャの婚約発表が行われる日でした。ダーシャの兄シャートフやワルワーラ夫人の幼馴染の娘リーザとその婚約者マヴリーキーが集まるなか、ピョートルと一緒にスタヴローギンが帰ります。ワルワーラ夫人は、スタヴローギンに問い質すも、彼は何も答えず、マリヤを家まで送るといって出て行きます。 その間にピョートルは、ペテルブルクにいたころ、マリヤを唯一スタヴローギンが丁重に扱っていたため、マリヤは彼が自分の夫か何かであるという妄想にとらわれてしまったというだけの話だと説明します。次いで、ピョートルは、ステパン氏に、結婚させられそうなので助けてほしいとはどういう意味かと問います。それにワルワーラ夫人は、激昂して、ステパン氏と絶好します。そこへ戻ってきたスタヴローギンを、なぜか突如としてシャートフが殴りつけます。シャートフが去ると同時に、スタヴローギンを秘かに恋するリーザは気絶します。
参考文献
・桑野隆『バフチン』
・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』



















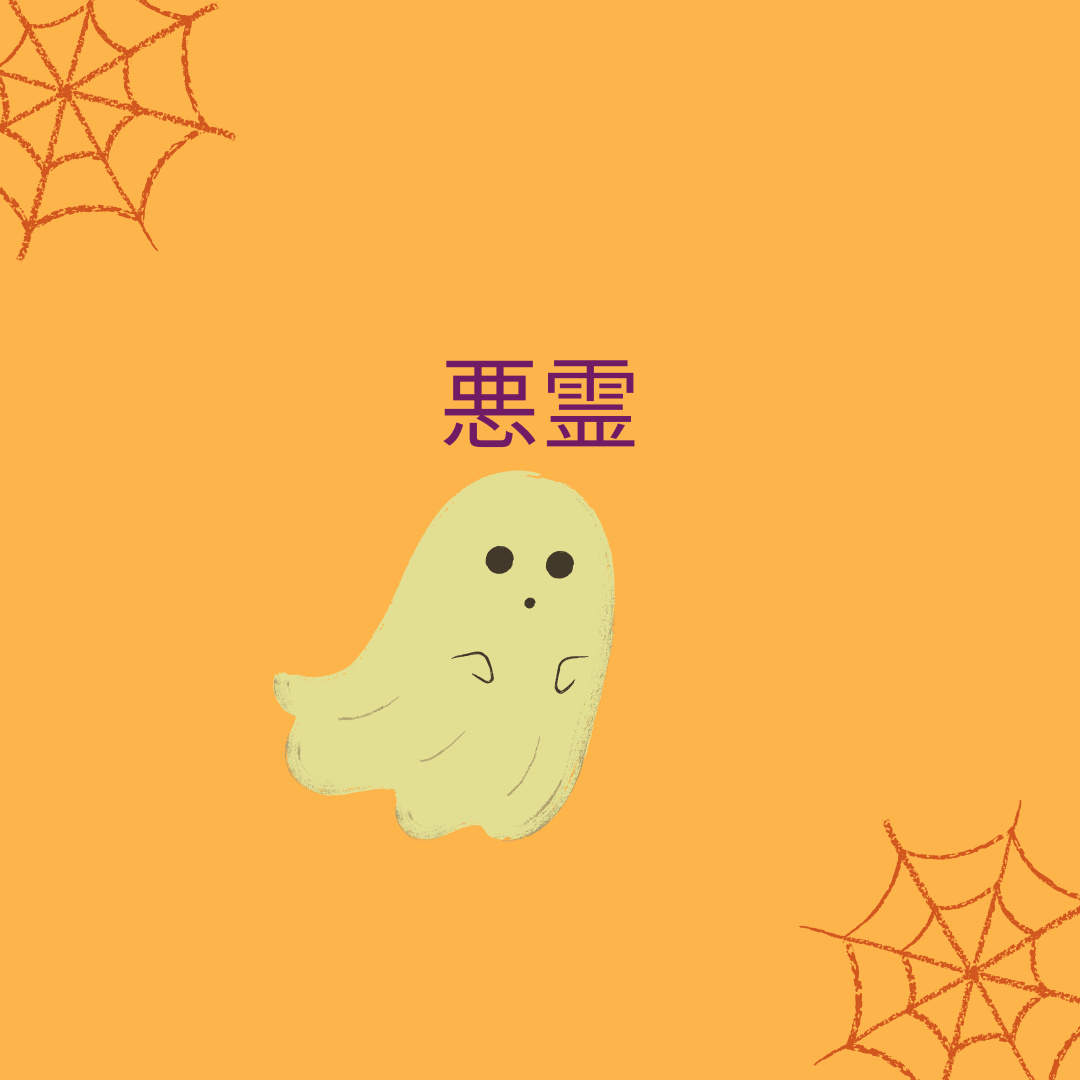


コメント