始めに
ジェイムズ『ねじの回転』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
等質物語世界の語り手、非線形の語り
等質物語世界の語り手・「私」が設定され、「私」はある屋敷に宿泊した一人で、そこで開かれた怪談の集まりに加わっているのですが、そのうち一人(ダグラス)が、かつて自分の家庭教師(ガヴァネス)だった女性について、彼女から来た手紙の朗読などを通じて語ります。最初に現れた「私」はもっぱら聞き手になっています。
コンラッド『闇の奥』などと共通するデザインです。
メリメ、モーパッサンらの影響
ヘンリー=ジェイムズという作家はツルゲーネフ(『父と子』『初恋』)を通じて知己を得たフローベール(『ボヴァリー夫人』『感情教育』)、ゾラ(『居酒屋』)、モーパッサン(『脂肪の塊』『女の一生』)などから影響を受けたことが知られます。モーパッサンも枠物語構造をとりれた作品があって、それが永井荷風の『ふらんす物語』へ影響し、そこで「おもかげ」と呼ばれる作品をものしております。コンラッド『闇の奥』にもモーパッサンの影響があります。本作の非線形の語りはモーパッサン、それからメリメの影響が大きいでしょう。
メリメは『カルメン』のオペラ化が有名ですが、ゴシック文学を広く手がけております。伝聞による語りや翻訳文学のパロディなどを孕んだ、豊かな語り口が特徴の作風で、『カルメン』も枠物語の構造です。
ゴシック文学
ゴシック小説として、シャーロット=ブロンテの『ジェーン=エア』(1847年)の影響がよく言われ、『ジェーン=エア』の女性ヒロインとガヴァネスの物語というモチーフが共通します。
またアン=ラドクリフのゴシック小説『ユードルフォの謎』の影響もうかがえます。この小説は、家庭教師がブライの屋根裏部屋に秘密の親戚が隠れていと疑うものです。オースティン『ノーサンガー・アビー』への影響が有名です。
一人称視点の不確かさ
本作品とコンセプトとして重なるのは漱石『こころ』やロブグリエ『嫉妬』、谷崎潤一郎『卍』『痴人の愛』、芥川『藪の中』、フォークナー『響きと怒り』、リンチ監督『ブルー=ベルベット』と言えます。集合行為における一部のアクターを語りの主体にしたり、または一部のアクターにしか焦点化をしないために、読者も登場人物と同様、作中の事実に不確かな認識しか得られるところがなく、限定的なリソースの中で解釈をはかっていくことしかできません。
本作で主な語り手となるガヴァネスの女性の報告は朦朧としていて、統合失調などによる幻覚なのか、それとも現実なのか、読者には分かりません。なので読者には解釈が開かれています。エイクマン、デラメアへと継承される、一人称視点の不確かさを効果的に恐怖につなげています。
タイトル
慣習的に「ねじの回転」と訳される本作ですが、正直意味が分かりにくいと思います。
原題”The Turn of the Screw”にある「screw」は「turn of the screw」でねじを回すの他、さらに無理を強いる、事態を悪化させること、追い打ち、などの意味があります。冒頭にダグラスの「ひとひねりした効果」(about turn of the screw)という台詞もあって、それともかかっています。
”Roman Holiday”と同じで、原題の多義的ニュアンスがシャープなタイトルで翻訳できないので、「ねじの回転」と訳される翻訳ですが、まだ「捩じれた話」とか「捻った話」の方が意味が伝わると思います。
ガヴァネスの受難
女性家庭教師(ガヴァネス)を主人公とする本作です。
ロウア―ミドルの未婚女性にとって家庭教師は、他の使用人よりは上位ですが、主人の家族から見れば雇い人です。ナニー、ベビーシッターと違い、子供たちの身の回りの世話をするのでなく、専ら教育に従事します。
ガヴァネスはアッパーミドルとかアッパークラスに働きにでることが多いですが、そこでは相手の方が階級が上で、家庭のなかでアウェイなので、心理的負担が大きかったのでした。
本作はそんなガヴァネスの精神的混乱を描きます。
逆に使用者側からの異なる階級の得体のしれなさを描くのがデュモーリア『レベッカ』と言えます。
物語世界
あらすじ
ある屋敷に宿泊した人々が、一人ずつ怪談を語っていて、「私」もそこに混ざっています。
そのうちの一人ダグラスが、かつて自分の妹の家庭教師だった女性からの手紙に書かれた体験談を読み始めます。
20歳の「私」は田舎の古い屋敷で住み込みの家庭教師(ガヴァネス)になります。不安もありつつ、天使のような娘フローラと家政婦のグロースに歓迎されます。しかし、フローラの兄のマイルズの学校から手紙が届き、マイルズが退学処分になったと知ります。数日後、マイルズは夏休みで屋敷に戻るものの、退学になったことは口にせず、「私」も本人に聞くことができません。
間もなく、兄妹と家政婦、使用人しかいないはずの屋敷で、見知らぬ男を見かけます。グロースの話を聞き、使用人だったクイントの幽霊に違いないと解釈する語り手です。クイントは主人が屋敷を出た後、冬に居酒屋からの帰りに転倒し、死亡したそうです。「私」は幼い2人をクイントの霊から守ろうとします。
大きな池の近くでフローラと遊んでいるとき、「私」は喪服を着た女の幽霊を見ます。前任の家庭教師ジェスルと思われます。
2人の霊は兄妹に邪悪な影響を与えているようです。ある日、フローラは1人でボートを使って池の向こうまで行ってしまい、「私」とグロースさんを心配させます。ジェスルのことを尋ねるとフローラは反発し、「私」にはもう会いたくないというのでした。フローラを守るため、屋敷を出てもらうことをグロースに伝えます。
「私」とマイルズは2人で話します。退学になった理由を問い詰めると、学校で口をすべらせたことが原因だといいます。そのとき窓越しにクイントの姿が見えます。私はマイルズを守ろうとします。
「私」はマイルズを強く抱きしめるが、やがて彼の小さな心臓が止まっているのを知ります(私の暴力か、幽霊の呪いか、死因は解釈に委ねられる)。
参考文献
・Fred Kaplan ”Henry James: The Imagination of Genius, A Biography”


















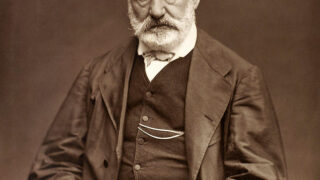



コメント