始めに
ジェイムズ『アスペルン文書』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造
国際性
ジェイムズはアメリカ(ニューヨーク)生まれですが、若い頃からヨーロッパに長期滞在し、フランスやイタリアを旅し、最終的にはイギリスに帰化しました。彼の人生そのものが「アメリカ的背景」から「ヨーロッパ的文脈」への移動であり、その異文化的な距離感・観察者の立場が小説に反映されています。
ヘンリー・ジェイムズのテーマを「国際性(international theme)」と呼ぶのは、まさに批評史のなかでよく言われることです。
影響したメリメも『コロンバ』『マテオ=ファルコーネ』などにも、そのような制度論的な視座があります。
初期から中期にかけての代表作『アメリカ人』『デイジー・ミラー』『ある婦人の肖像』などでは、アメリカの「新世界」的な単純さ・純真さ・エネルギーと、ヨーロッパの「旧世界」的な洗練・伝統・複雑さの価値体系の衝突や交流を中心に物語が展開されます。批評家たちはこれを「国際テーマ」と呼び、ジェイムズ文学の重要な特徴とみなしています。
集合行為における一個のアクターの視点から描く心理劇
本作品とコンセプトとして重なるのは漱石『こころ』やロブグリエ『嫉妬』、谷崎潤一郎『卍』『痴人の愛』、芥川『藪の中』、フォークナー『響きと怒り』、リンチ監督『ブルー=ベルベット』と言えます。集合行為における一部のアクターを語りの主体にしたり、または一部のアクターにしか焦点化をしないために、読者も登場人物と同様、作中の事実に不確かな認識しか得られるところがなく、限定的なリソースの中で解釈をはかっていくことしかできません。
ロシアとフランスのリアリズムの影響。集合行為を追う物語
ヘンリー=ジェイムズという作家はツルゲーネフ(『父と子』『初恋』)を通じて知己を得たフローベール(『ボヴァリー夫人』『感情教育』)、ゾラ(『居酒屋』『ナナ』)、モーパッサン(『脂肪の塊』『女の一生』)などから影響を受けたことが知られます。そうした縁もあってロシアとフランスのリアリズム文学の影響を強く受けたのでした。またバルザック(『従妹ベット』『ゴリオ爺さん』)の作品をこのみ影響されました。
本作品もさながらドストエフスキーの『罪と罰』などを連想させられます。
他の作品では例えば冨樫義博『HUNTER×HUNTER』、ハメット『マルタの鷹』『血の収穫』、谷崎潤一郎『卍』、エドワード=ヤン監督『エドワード=ヤンの恋愛時代』などに近いですが、物語は偏に特定のテーマや目的に従うべくデザインされている訳ではなく、エージェントがそれぞれの選好、信念のもと合理性を発揮し、これが交錯する中でドラマが展開されていきます。このようなデザインは、現実社会における政治学・社会学(システム論、エスノメソドロジー)や制度論、国際関係論におけるリアリズム/リベラリズム/ネオリベラリズム/ネオリアリズムが想定する人間関係や国際関係に対するモデルと共通しますが、現実世界における実践に対する見通しとして経験的根拠の蓄積のある強固なモデルといえます。
メリメ、モーパッサンらの影響
ヘンリー=ジェイムズはモーパッサン(『脂肪の塊』『女の一生』)などから影響を受け、モーパッサンも枠物語構造をとりれた作品があって、それが永井荷風の『ふらんす物語』へ影響し、そこで「おもかげ」と呼ばれる作品をものしております。コンラッド『闇の奥』にもモーパッサンの影響があります。本作の非線形の語りはモーパッサン、それからメリメの影響が大きいでしょう。
メリメは『カルメン』のオペラ化が有名ですが、ゴシック文学を広く手がけております。伝聞による語りや翻訳文学のパロディなどを孕んだ、豊かな語り口が特徴の作風で、『カルメン』も枠物語の構造です。
ジェイムズの非線形の語りにはこうした作家の影響も関わります。
ロマン主義のパロディ
『アスペルン文書』は、詩人や恋愛、ヴェネツィア、そして過去への憧れといったロマン主義的な題材を、あえて反転させて描いています。
物語の中心にいる主人公(無名の語り手)は偉大な詩人の真実を知りたいという崇高な情熱を語るものの、読み進めるとそれが学問的欲望というより単純な所有欲でしかないことがはっきりします。語り手はアスペルンの手紙さえ手に入れば、どんな手段でも良いと考えており、そのためには他人の家に潜り込み、老婦人の猜疑心を利用し、その姪であるティナの好意を弄ぶことまで厭わないのです。ここに描かれるのはロマン主義が神聖化した芸術のためという理念が、ときに個人的欲望の正当化にすり替わるという皮肉です。
手紙を持つジュリアナがかつてアスペルンの恋人、つまりミューズだったという設定もまた、ロマン主義的伝説へのパロディになっています。通常ロマン主義では、詩人に愛された女性は永遠の美をまとって記憶されます。しかしジェイムズは、彼女を老い衰えた現実の人間として描き、かつての神話的イメージを淡々と解体します。ヴェネツィアという舞台も、本来なら浪漫と幻想に満ちた都市として描かれるはずが、ここではむしろ閉ざされた屋敷の内部での駆け引きの舞台にすぎません。主人公の策略や焦燥のせいで街の美しさはほぼ背景に退き、ロマンティックな旅情はパロディの材料になります。
ティナとの関係も、ジェイムズならではの反転があります。ティナは主人公に好意を抱き、彼の下心を知らないまま心を寄せるものの、主人公はそれを利用して手紙に近づこうとします。ロマン主義が大切にした「純粋な恋」のイメージはここでは徹底して裏返され、恋愛は利用と欺きの手段へと転落します。
そして最後に残るのは、芸術の真実を手に入れようとする者が、もっとも不誠実で醜い行動を取ってしまうというアイロニーです。芸術の価値を追い求めることが、倫理を踏みにじる根拠になってしまっています。
物語世界
あらすじ
名もなき語り手は、今は亡きアメリカの著名な詩人ジェフリー=アスペルンのかつての恋人、ジュリアナ=ボーダーローを探しにヴェネツィアへ向かいます。
語り手は老婦人に下宿人候補として自己紹介し、地味でどこか世間知らずな彼女の姪ミス=ティナに求婚する。ジュリアナが保管するアスペルンの手紙やその他の書類を見るためです。ティナは語り手とその出版パートナーに宛てた手紙の中で書類の存在を否定していたものの、語り手は彼女がジュリアナの指示で嘘をついているのを疑います。語り手は最終的にティナに自分の意図を打ち明け、ティナは彼を助けると約束します。
その後、ジュリアナは語り手にアスペルンの肖像画のミニチュアを法外な値段で売ると持ちかけます。彼女はアスペルンの名前は出さないものの、語り手は未だに彼女が手紙の一部を所有していると信じています。老婦人が病に倒れると、語り手は彼女の部屋に入り込み、机から手紙を盗もうとしたところをジュリアナに見つかります。ジュリアナは語り手を「出版界の悪党」と呼び、倒れ込みます。語り手は逃げ出し、数日後に戻ると、ジュリアナが亡くなっていました。
ティナは、もし自分と結婚すればアスペルンの手紙を譲るとほのめかします。語り手は再び逃げ出します。最初はこの申し出は受け入れられないと感じていたものの、徐々に考えを変え始めます。しかしティナ嬢のもとに戻ると、彼女は別れを告げ、手紙を一枚ずつ燃やしてしまったと告げます。語り手は貴重な書類を見ることはなかったものの、ティナ嬢から贈られたアスペルンの肖像画の代金としていくらかの金を彼女に送るのでした。














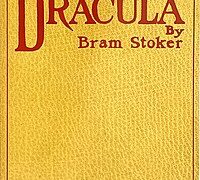






コメント