始めに
クヌート=ハムスン『飢え』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ハムスンの作家性
ハムスンの代名詞とも言える内的独白や、支離滅裂で複雑な人間の内面描写は、フョードル=ドストエフスキーの影響を強く受けています。
ニーチェの思想は、ハムスンの作品に通底する個人主義や既存の道徳への反抗の核となっています。弱者への同情を否定し、強靭な精神や生命力を肯定する姿勢が見えます。
ストリンドベリの主観的な自然主義や、既成の文学形式を破壊しようとする前衛的な姿勢に共鳴しました。他方でイプセンやビョルンソンの社会問題や教訓的テーマの物語にネガティブでした。
ハムスンは若い頃にアメリカへ二度渡り、肉体労働をしながら生活し、トウェイン、ホイットマンにも惹かれました。
語りの構造
この小説の最大の革新性は、外側の出来事よりも、主人公の内面に焦点を当てたことです。空腹によって精神が錯乱し、何でもないことに激怒したり、道ゆく人に嘘をついたりする、支離滅裂な心理状態を克明に描いています。
読者は、主人公が見ている歪んだ世界をそのまま体験することになります。ジョイスやカフカが完成させる意識の流れの手法を先取りしていました。
主人公は、貧乏で飢え死にしそうなのに、異常なほど高い自尊心を持っています。小銭を恵まれそうになると見栄を張って断ったり、逆に自分が持っているわずかな物を他人に与えてしまったりします。労働者として働くことを拒み、あくまで文筆家として認められることに固執します。この社会的な生存よりも自己の尊厳を優先する姿勢が、彼をさらなる破滅へと追い込みます。
舞台となるクリスチャニア(オスロ)は、主人公にとって非常に冷酷な場所として描かれています。街には人が溢れていますが、誰一人として彼の内なる苦悩に気づきません。都市という文明的な空間の中で、一人の人間が物理的に飢えて消える矛盾と孤独が浮き彫りにされています。
物語世界
あらすじ
19世紀末のノルウェー、クリスチャニア(現オスロ)。物語の主人公である「私」は、新聞社に寄稿してわずかな原稿料を得ることで生きている無名のライターです。
彼は才能を自負していますが、仕事はうまくいかず、下宿代も払えず、持ち物を次々と質入れして食いつなぎます。しかし、極限の空腹状態でも自分は高潔な芸術家であるというプライドだけは捨てられず、知人に会うと余裕があるふりをして見栄を張ったり、せっかく手に入れた小銭を浮浪者に恵んでしまったりします。
飢えが数日続くと、彼の意識は混濁し始めます。道ゆく老人のあとを執拗につけ回したり、見知らぬ女性に「イラヤリ」という架空の名前をつけて妄想の恋にふけったりします。
落ちている木片をしゃぶって空腹を紛らわし、自分の指を噛み切ろうとするなど、狂気じみた行動がエスカレートしていきます。
傑作を書こうとペンを握りますが、頭に浮かぶのは支離滅裂な言葉ばかり。ようやく書き上げた渾身の原稿も、編集者に今の時代には合わないと突き返されてしまいます。
家を追い出され、外で夜を明かし、文字通り死が目の前に迫ったとき、彼はふと港に停泊している船を目にします。
彼はそれまで固執していた文筆家としてのプライドを唐突に投げ捨て、イギリス行きの運搬船に船員として雇ってくれるよう頼み込みます。船に乗り込み、街が遠ざかっていくのを眺めながら、彼は自分を苦しめ続けたクリスチャニアという都市を去っていきます。




















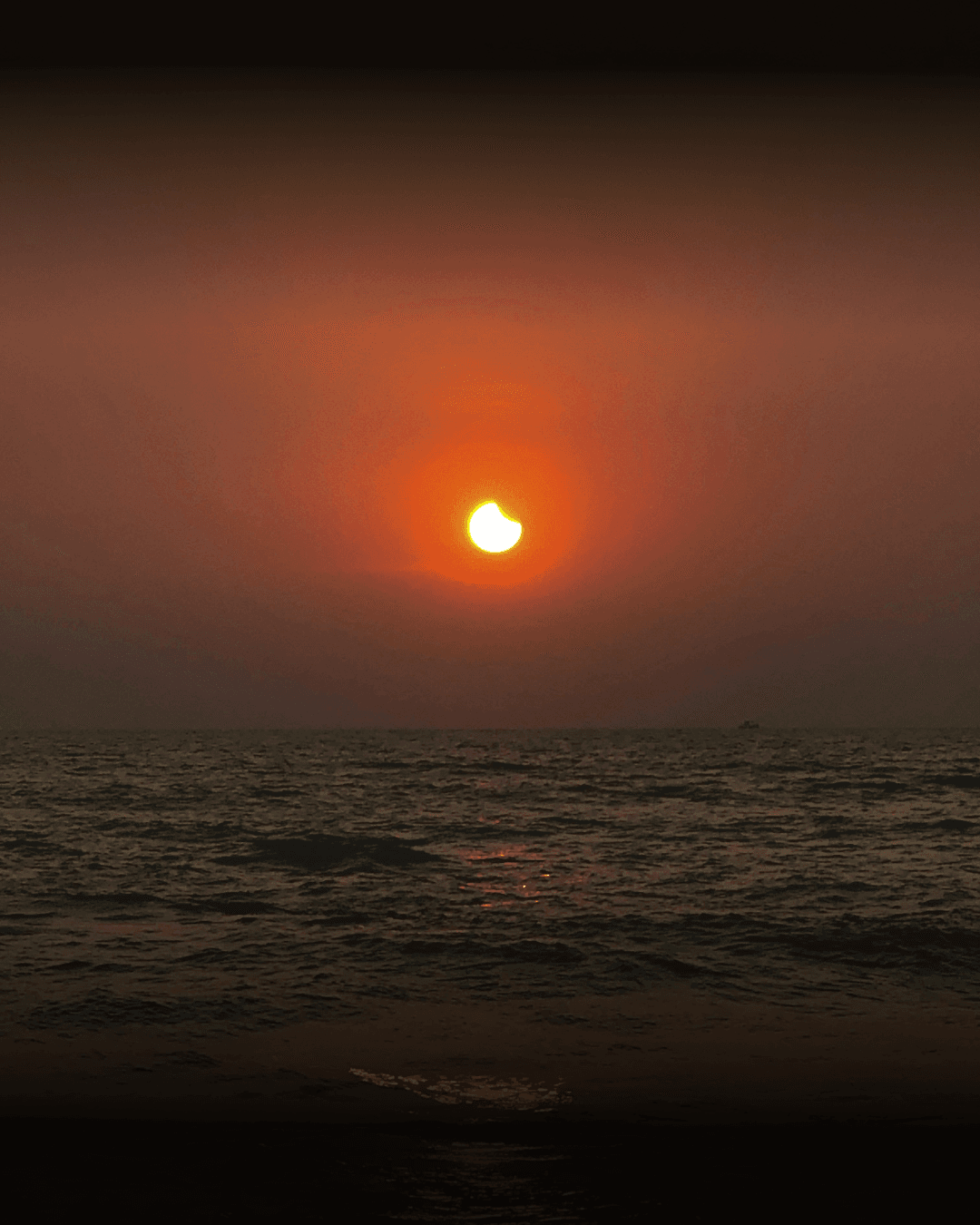


コメント