始めに
バージェス『1985』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
バージェスの作家性
ジョイスはバージェスにとって決定的な影響源です。ジョイスの『ユリシーズ』や『フィネガンズ・ウェイク』に見られる多言語を織り交ぜた言葉遊びや、意識の流れの手法は、バージェスの文体に深く刻まれています。
またエリザベス朝時代の文学、特にシェイクスピアには並々ならぬ愛着を持っていました。ほかにジェラルド=マンリ=ホプキンズという19世紀の詩人のスプラング・リズム(跳躍韻律)は、バージェスの散文のリズムに大きな影響を与えました。
カトリック作家であるグレアム=グリーン、イヴリン=ウォーなどからも刺激を受けました。
ナボコフの持つ言語的技巧、皮肉、そして言葉で世界を再構築するという姿勢にも共鳴していました。
オーウェル『1984』への風刺
『1985年』は、オーウェル『1984』へのオマージュであり、同時に鋭い反論でもある作品です。この本は「オーウェルを分析する評論パート」と、それを踏まえたバージェス流の近未来を描く小説パートの二部構成になっています。
主人公ベヴ=ジョーンズは、組合の横暴に抗い、古典的な教育を守ろうと孤軍奮闘します。『時計じかけのオレンジ』のアレックスが本能的自由を求めたのに対し、『1985年』の主人公は知的な自由」を守るために戦います。しかし、システムの前で知性がどれほど無力であるかという悲劇が描かれます。
バージェスは、オーウェルの描いたビッグ・ブラザーによる絶対的な恐怖政治は、もはや時代遅れだと考えました。国家による暴力的な支配よりも、無関心、文化の低俗化、そして無秩序な集団の力こそが自由を脅かすと説いています。
執筆当時のイギリス(1970年代後半)はストライキが頻発し、社会が麻痺していました。本作の小説パートでは、この状況が極端に描かれています。政府よりも強力な権力を持った「労働組合」が社会を支配し、ストライキに参加しない者は徹底的に排除されるサンディカリズム(組合至上主義)の恐怖が描かれます。
保守主義
バージェスが最も恐れたことの一つは、古典的な教養や言語能力が失われることでした。教育が実用性ばかりを重視するようになり、ラテン語やギリシャ語、高尚な文学が役に立たないものとして捨て去られた世界です。
オーウェルの「ニュースピーク(新語)」の代わりに、バージェスは語彙が極端に制限された、思考力を奪う労働者英語の危険性を指摘しました。
本作には、オイルマネーの流入によりイギリスが経済的にアラブ諸国に依存し、ロンドンがアル=ブリタニアと化していく様子が描かれています。
1970年代当時の社会情勢を反映し、イギリス独自の伝統が失われ、別の文化体系に飲み込まれていくことへの違和感がテーマの一つとなっています。
物語世界
あらすじ
第一部:評論
バージェスはまず、オーウェルの『1984』を1948年のロンドンを極端に描いたものに過ぎないと鋭く分析します。オーウェルが描いた配給制、質の悪いタバコ、崩壊したビルなどは、戦後直後のロンドンの光景そのものであり、未来予測としては不十分だと指摘しました。
オーウェルは言葉を削れば思考も制限できると考えましたが、言語学者でもあるバージェスは人間はどんなに言葉を奪われても、新しい隠語や表現を生み出す(ナッドサットのように)と反論します。
オーウェルが恐れたのは社会主義的な独裁でしたが、バージェスは過激化した労働組合と教養の崩壊こそが真の脅威になると予言します。ユートピアの反対はディストピアですが、バージェスはさらにひどい最悪の場所(カコトピア)という概念を提示し、それが自身の小説の舞台となります。
第二部:小説
舞台は1985年のロンドン。オーウェルが共産主義的な独裁を危惧したのに対し、バージェスは過激化した労働組合(ユニオニズム)が国家を実質的に支配するディストピアを描きました。
あらゆる職種がストライキを繰り返し、社会インフラは麻痺。「アラブ資本」がイギリスを買い叩き、街にはモスクが建ち並び、イスラム文化が浸透しています。英語はワーカーズ・イングリッシュという簡略化された言葉に書き換えられ、ラテン語などの古典教養は差別的で無用なものとして排除されています。
主人公ベヴ=ジョーンズは、かつて歴史と言語を教えていた元教師ですが、今は組合に従う労働者として生きています。
物語は、ベヴの妻が病院の火災で亡くなるところから始まります。悲劇的なのは、消防士たちがストライキ中だったため、消火活動が行われず見殺しにされたことです。ベヴは組合というシステムに激しい憎悪を抱きます。
怒りに震えるベヴは、自身の職場のストライキを拒否し、単身で仕事に向かいます。これは組合支配の社会では最大の罪とされ、彼は反社会的分子として再教育施設(Tu-duc)へ送られます。そこで待っていたのは、心理的な洗脳と屈辱でした。
出所後、ベヴは自由な個人として生きるために地下組織と接触したり、ホームレスの集団に加わったりしますが、どこへ行っても組合の網の目からは逃げられません。社会はストライキによる停止か組合による強制のどちらかしか選べない状況に陥っていました。
最終的に、ベヴは再び逮捕されます。しかし、彼がかつて必死に守ろうとした古典的な教養や歴史は、もはや誰にも理解されない死語となっていました。絶望した彼は、自ら命を絶つ道を選びます。






















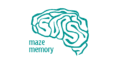
コメント