はじめに
クンデラ『無知』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ルネサンスとバロック
クンデラはルネサンスやバロック、ロマン主義の作家からの影響が顕著です。ラブレー(『ガルガンチュアとパンタグリュエル』)、セルバンテス、スターンなどで、セルバンテス『ドン=キホーテ』やスターン『トリストラム・シャンディ』のような形式主義的実験が本作にも見えます。
またロマン主義のルーツとなったフィールディングなどの艶笑コメディからの影響も本作に顕著です。
また幻想文学の影響も顕著で、カフカ(『変身』)からの影響は大きいです。カフカと重なるような黒い笑いとペーソスはクンデラの特徴です。
艶笑コメディ
本作はモラヴィア(『軽蔑』)や川端(『眠れる美女』『みづうみ』)、村上春樹(『ノルウェイの森』)などのような艶笑コメディになっています。性と愛をテーマとしながら、運命や人生についての思弁が展開されていきます。
また、本作は特にジョイス『ユリシーズ』と重なり、艶笑喜劇と絡めた神話的象徴の手法が展開されます。
こうした性愛と思索を絡めるデザインは、シュルレアリズムに影響したサド(『悪徳の栄え』)の文学を思わせます。サドが好んだフィールディングは、クンデラにも影響が大きいです。
新古典主義、神話的象徴の手法
モダニズム文学はT=S=エリオットの『荒地』などを皮切りに、フォークナー(『響きと怒り』)、ジョイス(『ユリシーズ』)、三島由紀夫(『奔馬』)、大江健三郎(『万延元年のフットボール』『取り替え子』)など、神話的象徴の手法を取り入れるようになりました。これは神話の象徴として特定の対象が描写され、新しい形で神話や特定の対象が発見される機知が喚起する想像力に着目するアプローチです。
例えば『ユリシーズ』では冴えない中年の広告取りレオポルド=ブルームを中心に、ダブリンの1904年6月16日を様々な文体で描きます。タイトルの『ユリシーズ』はオデュッセウスに由来し、物語全体はホメロスの『オデュッセイア』と対応関係を持っています。テレマコスの象徴となる青年スティーブン=ディーダラス、オデュッセウスの象徴としてのレオポルド=ブルーム、ペネロペイアの象徴としての妻モリーのほか、さまざまな象徴が展開されます。
本作もそんな『ユリシーズ』の影響が顕著で、様々な象徴的モチーフを設定していますが、中心的な象徴は『オデュッセイア』で、主人公オデュッセウスが故郷イタカに帰るまでの壮大な旅路、大いなる帰還を中心的なモチーフにしています。
タイトルの無知
作品のタイトルになっている「無知」とは、故郷や他者との関係において重要となるファクターです。
作品の中心的な主題として、「現代人は故郷を離れるか否かに関わらず、事実上、自らを亡命者としており、したがって”偉大な帰還”という概念は、大きな嘘であり、キッチュである」ということがあります。
故郷というものは幻想の産物で、記憶のなかの故郷はすでに、あるいは最初からなかったものです。それと離れれば離れるほど、故郷が美しく大切に、そして身近に感じられるようになります。それでも実際に故郷に帰れば、そこには記憶のなかの故郷はなく、そこに暮らす人たちは、故郷を離れた存在のことを忘れていたり、拒んだりします。つまり「無知」であれば故郷という幻想を保つことができるものの、知ってしまえばそれを維持できなくなります。
人間関係も同じです。プラハでヨゼフと出会ったイレーナは、過去にヨゼフと一緒にならなかったことを後悔します。スカンジナビア出身の夫グスタフとの現実の関係が悪化するにつれ、次第に理想のヨゼフに執着します。しかし最終的に、イレーナは二人の関係の可能性は幻想であり、ヨゼフは過去と亡き妻の思い出の中で生きたいだけなので、彼女との関係を望んでいないことを理解します。ヨゼフはある種の同情心からイレーナとの関係を持つことを考えたが、もはや誰かの役に立つだけの力は自分にはないことに気付きます。
つまり、イレーナはヨゼフについて無知であったから幻想を抱いていられたのに、知ってしまったからそれを維持できなくなってしまったのでした。
このような接近することで無知でいられなくなり、幻想を抱けなくなるジレンマを『オデュッセイア』におけるオデュッセウスの帰還をモチーフに描きます。
物語世界
あらすじ
主人公は、共産主義チェコスロバキアからの移民2人、ヨゼフとイレーナ。3人目の重要人物は、故郷を一度も離れたことのないミラダ。
3人ともそれぞれ過去に関係を持っていました。イレーナはヨゼフとの短い交流を大切に思っていたものの、ヨゼフは彼女のことを覚えていません。ヨゼフとミラダもかつて関係を持っており、ヨゼフは懐かしく思い出すものの、ミラダにとっては悲劇的な関係でした。ヨゼフが去った後、ミラダは山で凍死しようとして自殺を図っています。この自殺未遂の痕跡は、当時片耳を失ったため、彼女の残りの人生に残ったのでした。イレーナとミラダはお互いを知っており、ミラダはイレーナが帰国後に親しくしている数少ない人物の1人です。
イレーナは1989年の共産主義崩壊後すぐにプラハに戻り、会社の支店を開設しました。ヨゼフは長い間故郷への訪問をためらい、デンマーク人の妻の死後、ようやく故郷への訪問を決意しました。それは、妻を失った悲しみを紛らわすためでもあり、故郷への訪問を勧めていた妻を喜ばせるためでもありました。
ヨゼフは帰還先の国がいかに変化したかを感じ取り、馴染みのなさ、オデュッセウスがイタケーに抱いたような繋がり、故郷への帰還という感覚がないことに驚きます。
語り手は、急速に変化する現代社会においては、もはやこうした感覚さえも得られないと断言します。現代人は皆、故郷を離れるか否かに関わらず、事実上、自らを亡命者としており、したがって「偉大な帰還」という概念は、大きな嘘であり、キッチュであるとします。
キッチュは、デンマーク人の妻によって部分的に体現されるものの、主にイレーナのパリの友人シルヴィによって体現されます。シルヴィは、20年間の亡命生活の後、イレーナがなぜプラハへ行きたくないのか理解できず、テレビで数シーンしか知らないイレーナが失われた故郷へ帰還するという概念に心を動かされるのでした。
故郷の親戚や知人に会っても、ヨゼフは疎外感を覚えます。彼らはヨゼフを自分たちの生活から消し去り、二度と戻ってきてほしいとは思っていないのでした。ヨゼフは失った故郷を人々の中に見つけることができません。ヨゼフが不在の間、団地が発展した場所と同じように、彼らも変わっていました。
最終的にヨゼフはデンマークに戻ることを決意します。デンマークには家はないものの、故郷への思いはより強くなります。デンマークでは故郷の不在をより強く感じ、故郷という幻想をより強く感じられるため、彼は故郷という概念に近づいたのでした。デンマークでは故郷という幻想をより強く感じたといえます。
イレーナは、仕事の都合で以前故郷に戻っていたにもかかわらず、ヨゼフと同じような気持ちを抱いていました。亡命生活の20年間が今や失われた「故郷の生活」との間を埋めるだけのものになってしまったことに、彼女は嫌悪感を募らせます。
旧友に会うたびに、彼女の不安は募るばかりでした。亡命生活のことを口にすると、チェコ人の友人たちが彼女を無視することに気づきました。イレーナは、フランスでの生活を共有できないことを理解しただけでなく、友人らの行為を暴力行為、つまりイレーナの20年間の人生を切断し「故郷という牢獄」に引き戻そうとする試みだと感じます。
しかし同時に、イレーナはフランスでも同じ誤解に直面していたことにも気づいていました。こうしてイレーナは、プラハに行くかパリに行くかの選択を迫られ、その際に人生の一部を取り返しのつかない形で失ってしまうことを悟ります。最終的にイレーナはプラハに留まるものの、そこはもはや彼女の故郷ではなく、これからも決してそうなることはありません。イレーナの「大いなる帰郷」は「大いなる別れ」へと変わったものほ、それは二度目の出発には至りません。パリにも故郷は見いだせず、パリでは亡命者として生きることになり、それはプラハでも同じだからです。
イレーナとヨゼフは、その後すぐに出会います。ヨゼフは彼女のことを覚えていないものほ、覚えているふりをします。イレーナはすぐに彼だと気づくのでした。二人は共に移民であることを知ります。
時が経つにつれ、イレーナは過去にヨゼフと一緒にならなかったことを後悔します。スカンジナビア出身の夫グスタフとの現実の関係が悪化するにつれ、次第に理想のヨゼフに執着します。二人はプラハのホテルでヨゼフと一夜を共にします。この一夜は、チェコ語のエロチックな魅力にも導かれ、二人は再び恋に落ちたように見えます。帰国後、故郷のチェコ語は二人にとって遠く離れた、そして変化したように思えたからでした。これは、小説の中で唯一成功した「偉大な帰還」でした。
しかし最終的に、イレーナは二人の関係の可能性は幻想であり、ヨゼフは過去と亡き妻の思い出の中で生きたいだけなので、彼女との関係を望んでいないことを理解します。ヨゼフはある種の同情心からイレーナとの関係を持つことを考えたが、もはや誰かの役に立つだけの力は自分にはないことに気付きます。
ミラダはヨゼフとの関係から立ち直っています。ミラダは感情を交えずに過去を振り返り、自殺未遂を「無知の時代に犯した取り返しのつかない過ち」と捉えています。
ミラダは詩人ヤン=スカチェルの個人的な友人でもあります。





















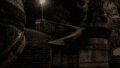
コメント