始めに
中上健次『千年の愉楽』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
シュルレアリスム、ロマン主義、セリーヌ、ジュネ。口語的世界、アウトサイダーアート
中上健次はシュルレアリスム(瀧口修造、稲垣足穂)の影響が当初から強く、ファンタジックな要素にその影響が見えます。またシュルレアリスムにおいて着目されたサド(『悪徳の栄え』)、ランボーなどの作家の影響も顕著です。グランギニョルな青春残酷物語としての性質にそれが現れます。
またセリーヌ(『夜の果てへの旅』)の影響も顕著です。セリーヌは大江健三郎も顕著な影響を受けたラブレーの伝統を継ぐフランスの作家で、その口語的で豊かな語り口はトウェイン(『ハックルベリー=フィンの冒険』)にも引けを取らぬほどエネルギッシュです。また艶笑コメディとしての性質もラブレー(『ガルガンチュアとパンタグリュエル』)、セリーヌに由来します。
シュルレアリスムは既成の芸術やブルジョア社会へのカウンターカルチャー、アウトサイダーアートとしての側面がありましたが、中上健次自身も部落出身というマイノリティ、アウトサイダーでありつつ、ジュネなどのアウトサイダーのモダニズムに惹かれました。
異質物語世界の語り手。オリュウノオバに焦点化
本作は異質物語世界の語り手が設定されつつ、焦点化はオリュウノオバに図られ、意識の流れの手法を用いてその一人称的な経験も展開されていきます。ウルフ『ダロウェイ夫人』やジョイス『ユリシーズ』、川端『みづうみ』などと近いでしょうか。また中上健次『奇蹟』と近いです。意識の一人称的なタイムトラベルなどを通じて土地の歴史が縦横に語られていきます。
このオリュウノオバは千年も生きたとされる特異な視点人物で、その一人称的経験により土地の歴史が語られます。
ここに意識の一人称的な視点から歴史を再現しようとするアナール学派的な発想が見え、フォークナー(『アブサロム、アブサロム!』『響きと怒り』)の影響が顕著です。
プラグマティックな歴史記述
フレイザー『金枝篇』がT=S=エリオット『荒地』に導入されて以降、作家は語りの手法に民俗学、社会学的アプローチをも積極的に取り入れるようになっていきました。中上に影響したフォークナー(『アブサロム、アブサロム!』『響きと怒り』)作品や本作でも用いられているアナール学派的な、中央の事件史に抗する心性史としての歴史記述のアプローチは、ポストコロニアルな主題を孕むガルシア=マルケス『族長の秋』『百年の孤独』などラテンアメリカ文学とモードを共有します。
旧来的な中央の事件史としての歴史記述においては、歴史の構造的理解に欠き、そこから捨象される要素が大きすぎましたが、アナール学派は特定のトポスに焦点を当てたり、ミクロなアクターの視点に注目したりして、歴史の構造的把握と、歴史を構成するアクターの単位の修正を図りました。本作も同様に、ミクロな歴史的アクターの一人称的視点に着目しつつ、その集積物として歴史を構造的にとらえようとするプラグマティックな歴史記述のアプローチが見えます。
歴史の中のミクロなアクターの視点、語りを通じて歴史を記述、再構築しようとするアナール学派的アプローチは、小説家にとっても強力な武器となったのでした。本作もオリュウノオバというミクロなアクターの一人称視点を通じて土地の歴史が語られていきます。
輪廻とモダニズム
T=S=エリオット『荒地』の下敷きとなった文化人類学者フレイザー『金枝篇』が、ネミの森の王殺しの儀式の伝統に対して、自然の象徴である森の王が衰弱する前に殺すことで、自然の輪廻と転生のサイクルを維持するためだという解釈を与えています。ここから以降のモダニズム文学に輪廻と転生のモチーフが現れるようになりました。
たとえばサリンジャー『ナイン=ストーリーズ』などにもその影響が伺えます。中上健次『千年の愉楽』、三島『豊饒の海』シリーズ(1.2.3.4)、押井守監督『スカイ・クロラ』などにも、モダニズムの余波としての転生モチーフが見えます。
三島は中上の好んだ作家で、本作も三島『豊饒の海』シリーズ(1.2.3.4)にあやかった「天人五衰」が章タイトルになっています。また三島由紀夫には郡虎彦を経由してニーチェからの影響があり、ニーチェの永劫回帰も、宿命論的な時間論で、時間軸の中での宿命の輪廻というか繰り返しを提唱し、『豊饒の海』シリーズ(1.2.3.4)の背景になっていましたが、本作もそこからの影響が見えます。
本作では、部落千年の歴史のなかで、繰り返される魂の輪廻の悲劇を描きます。「中本の一統」と称される穢れた血に生まれ早死にを宿命づけられた若者たちの残酷な死が、オリュウノオバの視点で描かれます。
マジックリアリズム
本作はマジックリアリズムと形容されます。このジャンルとされるガルシアマルケス『百年の孤独』も、カフカ(『変身』)やドストエフスキー(『分身』)からの影響と思しき幻想文学的な要素が印象的でした。
本作でもオリュウノオバは千年も生きたとされる特異な語り手ですが、全体的に幻想的設定やモチーフがあります。
マージナルなトポスとしての路地
中上健次が自身の出生も相まって部落のコミュニティや韓国、朝鮮を描いた背景にあるのは、オンタイムの社会学、歴史学の動向です。
国家や帝国の矛盾や不正義を暴き、中心化を妨げる存在に焦点を当てるアプローチは、アナール学派のような心性史的な歴史学の潮流の動向と相まって、ポストコロニアル文学、批評に影響しました。中上健次に影響した網野善彦の「聖/俗」(デュルケーム由来ですが)「無縁」概念、大江健三郎にも影響した山口昌男の「中心/周縁」概念などが典型的です。
網野善彦は「無縁」という概念でもって寺社などの聖なるトポスを世俗のシステムや権力からのアジールとして捉え、そこにおける固有の実践を評価しました。
山口昌男は「中心/周縁」と政治的世界を捉え、中心的な世界と周縁的な世界の相互作用のなかで政治のダイナミズムをとらえ、周縁的な世界が中心世界にもたらす文化的多様性に着目しました。
本作における「路地」は世俗のシステム、秩序から一定の独立性を持ち、「無縁」で開かれたトポスであり、それ故にさまざまなネーションの歴史が無秩序に流入する空間です。ちょうど大江健三郎『同時代ゲーム』やガルシアマルケス『百年の孤独』に描かれる世界に似て、中心と周縁的のマージナルな位置にあるトポスにおける無秩序な文化的な氾濫が展開されます。
ガルシアマルケス『百年の孤独』
本作はガルシアマルケス『百年の孤独』を意識した内容です。
ガルシアマルケス『百年の孤独』では、マコンドという村の興亡をブエンディア一族の年代記のなかで展開し、百年という長いタイムスケールでそれを展開しました。
本作では、オリュウノオバが千年も生きたとされる視点人物で、その視点から、部落差別の千年以上にもわたる歴史と、その中に生きる「中本の一統」と称される穢れた血に生まれ早死にを宿命づけられた若者たちのことを描きます。
ガルシアマルケス『百年の孤独』では、人間の普遍的な「孤独」と、中心世界からの無関心のなかにあってそんな孤独の中で地図の上から完全に姿を消すブエンディア一族とマコンドの孤独を描いていて、それがタイトルの由来でした。
他方で『千年の愉楽』では、タイトルに「愉楽」とあって、周縁的世界である路地と中本の一統の、カオスでアナーキーな、秩序転覆的エネルギーに言及するタイトルになっています。
アウトサイダーアート(シュルレアリス厶、サド、ジュネ、三島由紀夫)
本作はピカレスクのモードを踏まえる内容です。シュルレアリスムは既成の芸術やブルジョア社会へのカウンターカルチャー、アウトサイダーアートとしての側面があると書きましたが、本作も社会の中でのアウトサイダーの姿を描くグランギニョルなピカレスクになっています。
ピカレスクはスペインの文学ジャンルで、特徴としては自伝的な記述の一人称で書かれます。社会的地位が低いアウトローの主人公が機転を利かせて立ち回る、小エピソード集の形式です。平易な言葉やリアリズム、風刺などがしばしば見えます。「悪漢小説」と訳されるものの、ピカレスクの主人公が重大な犯罪を犯すことは少なく、むしろ世間の慣習や偽善に拘束されない正義を持ったアウトローとして描かれやすいです。主人公は性格の変化、成長はあまりしません。このピカレスクは英文学に影響し、その後の世界文学のモードに影響しました。
シュルレアリスムの周辺の作家であるサド、ジュネ、三島(『仮面の告白』)の影響が顕著で、ドンファン的なヒーローの破滅が綴られていきます。
物語世界
あらすじ
作品の舞台は和歌山県新宮市の「路地」と呼ばれる被差別部落です。「中本の一統」と称される穢れた血に生まれ早死にを宿命づけられた若者たちを産婆オリュウノオバの視点で描きます。
半蔵の鳥
中本の一統の中でも特に美しい半蔵は、突き動かされるままに女遊びを繰り返します。しかしそれで怨恨を買い、男に後ろから刺されて死にます。
六道の辻
中本の一統の三好は、盗人などで暮らしています。ヒロポンを打ち、遊び暮らすものの、ある時殺人を犯します。三好は身を隠すため飯場で働くものの、若くして失明し、絶望して縊死します。
天狗の松
子供の頃に天狗にさらわれ神隠しに遭った文彦は飯場で生計をたてています。あるとき巫女を「路地」に連れ帰りますが、文彦は情交中にその女を殺します。また飯場に戻るも、盗みの共謀者となってしまい、無気力になって自殺します。
天人五衰
戦時の中国大陸から引き揚げて「路地」に戻ってきたオリエントの康は地廻りの頭になります。新天地を求め南米に渡るものの、革命運動に巻き込まれて行方不明になります。
ラプラタ綺譚
盗人をして義賊のように盗品を「路地」の者に分け与えていた新一郎は、下駄直しや山仕事の人夫などをしていましたが、銀の河が流れているという南米ラプラタに渡ります。やがて路地に戻って来た新一郎は盗人を再開するものの、水銀を飲み自殺します。
カンナカムイの翼
達男は十五の年で北海道の鉱山に働きに行き、アイヌの若い衆と意気投合します。しかし鉱山の労働争議の交渉の最中に殺されます。
参考文献
・高山文彦『中上健次の生涯 エレクトラ』
・網野善彦『無縁・公界・楽』
・山口昌男『知の祝祭』











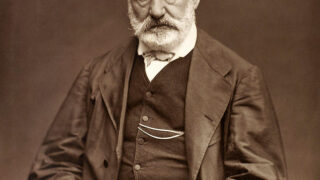










コメント