始めに
イアン・マキューアン『アムステルダム』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
マキューアンの作家性
マキューアンの初期作品に見られる、閉塞感や残酷なまでの冷静さはカフカ、ベケット、フロイトの影響をうかがわせます。
ヴァージニア=ウルフのモダニズム、ヘンリー=ジェイムズ、トマス=ハーディのリアリズムからの刺激もあります。
マキューアンは、1970年代以降のイギリス文学を牽引した黄金世代の一員であり、互いに切磋琢磨した友人たちからの刺激も公言しています。マーティン=エイミスは親友であり、文体に対する執着や皮肉な視点を共有していました。クリストファー=ヒッチェンズ、フィリップ=ロス、ベローなども同時代です。
また文学者だけでなくリチャード=ドーキンスやエドワード=O=ウィルソンといった科学者からも強い影響を受けています。
二人のすれ違い
物語の核となるのは、作曲家のクライヴと新聞編集長のヴァーノンが交わしたもし一方が心身を病んだら、もう一方が安楽死の手配をするという誓約です。これは一見、理知的で現代的な友情の証に見えますが、実際には自分の死までも完璧にコントロールしたいという傲慢さの表れとして描かれています。最終的にこの誓約が、相手を抹殺するための武器へと変貌する過程がこの小説の皮肉な部分です。
二人の主人公は、それぞれ芸術と報道の世界で成功を収めていますが、その内面は空虚です。クライヴは世紀末の交響曲を完成させるためなら、目の前で起きている犯罪を見逃しても構わないと考える芸術至上主義という名のエゴイズム。ヴァーノンは新聞の部数を伸ばすためなら、かつての友人のプライバシーを暴き、破滅させることも厭わないジャーナリズムの仮面を被った冷酷さ。 成功者がいかに容易に良心を捨て去るかというエリートの道徳的崩壊がテーマです。
タイトルの意味
かつて一人の女性モリーを愛した友人同士であるはずの二人が、些細な意見の相違や自己保身から憎しみ合い、互いを怪物と見なすようになります。マキューアンはここで、現代社会の知的な人々がいかに短気で、他者に対して不寛容になり得るかを冷ややかに描写しています。
タイトルにもなっているアムステルダムは、安楽死が法的に認められている自由の象徴として登場しますが、結末においてそこは理性的な合意に基づいた殺人が行われる殺伐とした場所へと転じます。良かれと思って始めたことが、最悪の形にねじ曲がっていくという運命の皮肉が、物語全体を貫いています。
物語世界
あらすじ
物語は、かつて多くの男を虜にした才女モリー=レーンの葬儀から始まります。葬儀に集まった元恋人たちのうち、中心となるのは二人の成功者、クライヴとヴァーノンです。クライヴは英国を代表する現代音楽の作曲家、ヴァーノンは大衆紙『ジャッジ』の編集長です。
変わり果てた姿で亡くなったモリーを目の当たりにした二人は、もし自分が病などで理性を失い、自分をコントロールできなくなったら、その時は安楽死を手助けしてほしいという誓約を交わします。これが悲劇の引き金となります。
ヴァーノンのもとに、モリーが隠し持っていた衝撃的な写真が持ち込まれます。それは、次期首相候補とも目される保守派政治家ガーマニー(彼もモリーの元恋人)が、女装をしている写真でした。
ヴァーノンは部数を伸ばし、大衆の知る権利に応えるという名目で、写真の掲載を強行しようとします。それにクライヴは死者のプライバシーを暴き、個人の趣味を攻撃するのは下劣だと猛烈に反対します。この対立をきっかけに、長年の友人だった二人の仲に亀裂が入り、互いへの軽蔑が募っていきます。
その後、二人はそれぞれ決定的な道徳的失敗を犯します。クライヴは湖水地方へ作曲のインスピレーションを得に散策中、女性が男に暴行されようとしている現場を目撃します。しかし今、最高のメロディが浮かんでいる、邪魔をされたくないという理由で見逃してしまいます。
ヴァーノンの罪はガーマニーの女装写真を公開しますが、世論は予想に反してガーマニーに同情し、ヴァーノンは卑劣なハイエナとして社会的に抹殺され、編集長の座を追われます。ヴァーノンは逆恨みから、クライヴが犯罪を見逃したことを新聞で暴露。クライヴの輝かしいキャリアも泥にまみれます。
二人は互いへの憎しみを爆発させ、相手を理性を失った狂人だと決めつけます。そして、かつて交わした安楽死の誓約を、相手を消すための手段として利用することを決意します。
舞台は、安楽死が合法化されているオランダのアムステルダムへ。二人は互いの祝杯の酒に毒を盛り合い、皮肉にも約束通り二人揃って死を迎えます。生き残ったのは二人から攻撃されていた政治家ガーマニーでした。彼は二人の死を悼むふりをしながら、自らの政治的地位を盤石なものにします。




















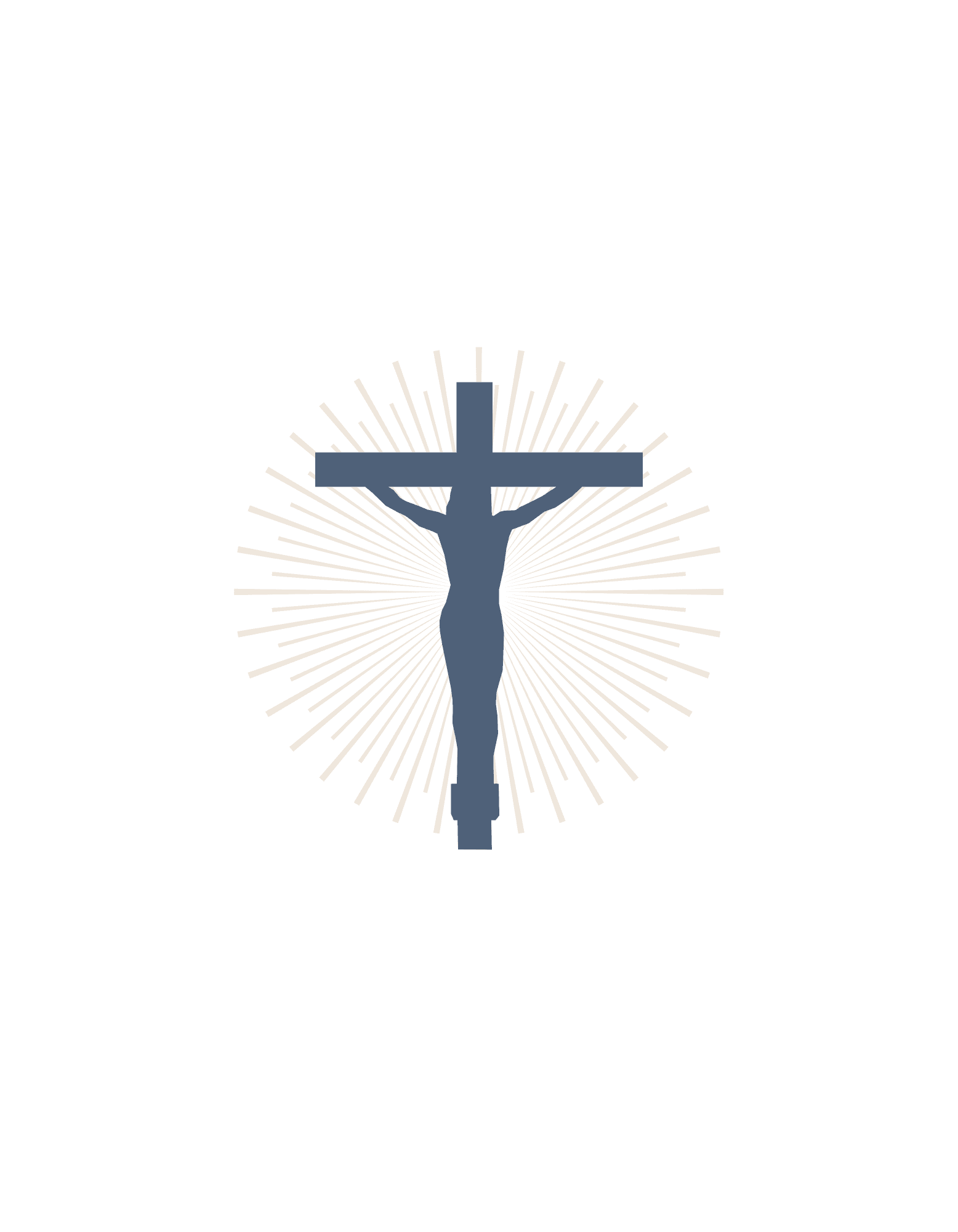


コメント