始めに
今日は、谷崎潤一郎『吉野葛』についてレビューを書いていきたいと思います。世間的には耽美主義の作家として知られる谷崎ですが、今回は谷崎のモダニスト、前衛文学作家としての側面を語っていきたいと思います。
背景知識、語りの構造
形式主義的実験(フランス文学、象徴主義、永井荷風『ふらんす物語』『あめりか物語』)、芥川、モダニズム
谷崎潤一郎は、モダニスト、前衛文学作家としての優れた手腕があります。谷崎は仏文学、象徴主義文学にその源流を負うところが大きく、また同様の背景を持つ永井荷風を一人の文学的師としています。本作品の手法も荷風『ふらんす物語』『あめりか物語』の形式主義的実験を踏まえるものです。
荷風『ふらんす物語』『あめりか物語』は、荷風の最初期の作品で、留学経験を踏まえた紀行文や枠物語などの小説作品を含んだ、形式主義的実験のスタイルが見えます。荷風のこれらの作品でも、等質物語世界の、作者の分身たる主人公の一人称的経験の記述がしばしば展開されますが、谷崎『吉野葛』はそれを受け継ぐものです。
コンラッド『闇の奥』における語りの実験が西洋のモダニスト(フォークナー、T=S=エリオット)を育てたように、谷崎というモダニストを育てたのは永井荷風と言って良いでしょう。荷風『あめりか物語』『ふらんす物語』に見える豊かな語り口は、『卍』『春琴抄』『蘆刈』『吉野葛』における『闇の奥』のような枠物語構造、『響きと怒り』『失われた時を求めて』のような『盲目物語』『過酸化マンガン水の夢』における一人称視点のリアリズム的手法などとして昇華されています。
また盟友の芥川龍之介も、『藪の中』『地獄変』など形式主義的実験を展開し、そこからの刺激もありました。また横光、川端のモダニズムも間近で経験しました。
泉鏡花の影響と口語的世界
本作にも見える豊かな口語的語りは谷崎文学の特徴ですが、谷崎のこうした語り口を生んだのは、まず泉鏡花(『高野聖』)の影響でした。
泉鏡花は、尾崎紅葉(『多情多恨』『金色夜叉』)の硯友社のメンバーで、そこから江戸文芸の戯作文学を参照しつつも、リズミカルな口語によって幻想的で性と愛を中心とする世界を描きました。
江戸文芸にあった洒落本ジャンルは、遊郭における通の遊びを描くメロドラマでしたが、鏡花も洒落本を継承して、花柳界におけるメロドラマを展開しました。また読本的な幻想文学要素、人情本的な通俗メロドラマからも影響されて、幻想文学、メロドラマをものした鏡花でした。戯作文学の口語的な豊かな語りのリズムを鏡花は継承しました。
谷崎にもこうした部分における影響が顕著で、本作も口語的語りと幻想文学趣味が特徴です。本作では南朝を題材に、中国文学風(志怪、伝奇、白話)の幻想小説、歴史小説を書こうとする構想の頓挫までが描かれ、こうした実録タッチや伝聞による展開スタイルも、泉鏡花も参照する伝奇小説の文脈を連想します。
等質物語世界の語り手「私」の創作をめぐる作品
本作品は特異な形式となっており、等質物語世界の語り手「私」を設定し、これが作者の分身のような存在で、「津村」と吉野を舞台とする作品の取材旅行をしながら、その構想の頓挫と、「津村」が語る母への思慕の物語に惹きつけられる様や、彼の結婚の顛末が綴られていきます。また、取材を通じて土地の歴史が縦横に掘り下げられていきます。
本作はゴダール監督『ゴダールのリア王』、大江健三郎『水死』『憂い顔の童子』などのような創作のプロセスそれ自体を創作の対象とする作品となっています。
また、本作品は谷崎にしては明朗な喜劇的性質が強く、津村のこの旅行の真の目的がある女性への求婚のためだと明かされます。これは創作を通じて社交の洗練が促され、恋愛が成就するという、谷崎の愛した王朝文学とその時代のモードを踏まえる作品となっています。
意識とは何か。意識と創作
本作は意識の流れと重なる手法が取られていますが、人間の「意識」とは、そもそもなんでしょうか。
現代の心の哲学では、意識や心というものの機能主義的、道具的定義がいろいろに考えられており、大まかに言ってそれは複数のモジュールの計算、表象の操作を統合し、シュミレーションから推論を立て環境に適応的な行動変容を促すツールであるとの見通しが立てられています。そこではインプットされたさまざまな表象を操作し、過去にインプットされた表象との関連性が発見されたり、環境の構造化にあたって認識が修正されたりしていきます。
本作における全体的なコンセプトにも、そのような意識の特性が伺えます。語りの主体は知覚から得た情報からマインドワンダリングを働かせ、主観的なタイムトラベルの中でさまざまな過去の記憶や知識の表象を統合しつつ、時間軸の中でそれを構造化し、創作のためのモデルを絶えず改訂していきます。けれどもそれが、現実の恋愛の成就の前に敗れてしまうまでが描かれます。
意識の流れを用いたモダニスト、プルースト『失われた時を求めて』でも、意識が可能にする創作という営為のプロセスについて描いています。
また、それと並行してこの意識によって、語り手と津村のコミュニケーションという営為が可能になっています。知覚から得た情報からマインドワンダリングを働かせ、主観的なタイムトラベルの中でさまざまな過去の記憶や知識の表象を統合しつつ、時間軸の中でそれを構造化する、という意識の働きは、実際の恋愛や友情におけるコミュニケーションの前提になっています。
アナール学派以後の歴史記述のアプローチのその後の展開
本作は多くの文学者を刺激し、後藤明生『吉野太夫』があるほか、花田清輝『室町小説集』があります。
本作品はフォークナー『響きと怒り』のような、一人称的視点を生かしたフィールドワークによる、文化人類学的歴史記述のアプローチが取り入れられており、そうした側面が戦後のモダニストを刺激したのでした。また批評や小説の創作プロセスを『横しぐれ』『樹影譚』において小説とした丸谷才一、丸谷の私淑した吉田健一(『酒宴』)も谷崎を愛好していました。
他方、谷崎『吉野葛』は鏡花の伝奇文脈や荷風のゴシック的枠物語・戯作文脈を踏まえて、一人称的現象的視点のリアリズムから創作の創造と歴史の記述・解釈のプロセス自体を創作の対象としつつ、その実践的基盤となる認知をベースに並行して結婚をめぐる心理劇を展開する高度な前衛文学の白眉で、後藤明生『吉野太夫』とか花田清輝『室町小説集』とかオマージュはあるものの、『室町小説集』は例えばプレモダニズムの『白鯨』やモダニズムの『ユリシーズ』の源流であるルネサンス文学、ロマン主義文学の形式主義的実験のスタイルがベースになっている感じで、谷崎のコンセプトとちょっと違って筒井康隆のメタパロディみたいなこれはこれで面白いけど別枠、みたいな感じで谷崎がやろうとしたのはビネ『HHhH』みたいなことです。
プラグマティズム(ラスキン、ベルクソン)
またモダニズム文学作家にはプルーストなどプラグマティズムからの影響が顕著な作家が多いですが、谷崎にもベルクソン(翻訳も著している)、それからラスキンといったプラグマティズム的思想家(プラグマティズムの影響があったり、類似のモデルを構想したり)の影響が顕著です。
社会、公共圏における実践に対するモデルとして、一人称視点のリアリズムからその集積物として世界を捉える見通しは、プラグマティズムにおよそ共通すると言えますが、このような発想がモダニズム文学を育てたのでした。
物語世界
あらすじ
「私」は、後南朝を題材に小説を書こうとしています。「私」は旧友の津村に吉野を案内してもらい、取材します。
津村は、幼い頃に亡くした母親のルーツを探り吉野に来たのだと言います。津村は母の生家が吉野にあることを調べました。そして初めて母の生家を訪れたとき、若い娘が紙をすいていました。彼女はお和佐といい、冬に吉野の紙すきの手伝いをしていました。
津村の吉野旅行の本当の目的は、お和佐への求婚でした。津村はめでたくお和佐と結ばれます。しかし、小説の創作の構想はとん挫します。
関連作品、関連おすすめ作品
・大江健三郎『憂い顔の童子』:母物語。創作プロセスを創作の対象とする作品。
参考文献
・小谷野敦『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』(中央公論社.2006)
・伊藤邦武『経済学の哲学 19世紀経済思想とラスキン』
・戸田山和久『哲学入門』(筑摩書房.2014)『恐怖の哲学 ホラーから人間を読む』(NHK出版.2016)



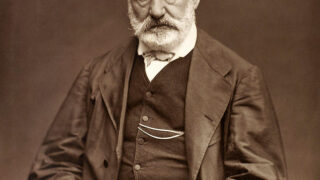







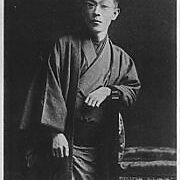










コメント