始めに
イアン・マキューアン『贖罪』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
マキューアンの作家性
マキューアンの初期作品に見られる、閉塞感や残酷なまでの冷静さはカフカ、ベケット、フロイトの影響をうかがわせます。
ヴァージニア=ウルフのモダニズム、ヘンリー=ジェイムズ、トマス=ハーディのリアリズムからの刺激もあります。
マキューアンは、1970年代以降のイギリス文学を牽引した黄金世代の一員であり、互いに切磋琢磨した友人たちからの刺激も公言しています。マーティン=エイミスは親友であり、文体に対する執着や皮肉な視点を共有していました。クリストファー=ヒッチェンズ、フィリップ=ロス、ベローなども同時代です。
また文学者だけでなくリチャード=ドーキンスやエドワード=O=ウィルソンといった科学者からも強い影響を受けています。
タイトルの意味
物語の前半、少女ブライオニーが犯す罪は、悪意によるものではなく、未熟な想像力によるものです。彼女は大人たちの複雑な恋愛関係を、自分が読み耽っていた通俗的なロマンスや勧善懲悪の物語の枠組みに無理やり当てはめて解釈してしまいました。噴水での出来事や図書室での情景を見たブライオニーが、それを自分の都合の良い文脈で解釈し、取り返しのつかない嘘をつきます。一人の少女の勝手な思い込みが、他者の現実の人生を破壊してしまう恐ろしさが描かれています。
タイトルの通りテーマは犯した罪をどう償うかです。嘘によって引き裂かれたロビーとセシリアの時間は、二度と戻りません。小説の終盤で明かされる通り、ブライオニーは神を信じない作家として、自らのペンで物語を書き直すことで償おうとします。しかし、現実を書き換えても過去の事実は変わりません。作家という創造主にとっての赦しとは何かという重い問いが投げかけられます。
メタフィクション
物語が物語を語るというメタフィクションになっています。現実では救われなかった恋人たちを、小説の中でだけは結ばせるのはブライオニーなりの慈悲であり、唯一できる償いです。読者は最後に、自分が読んでいた美しい再会シーンが実は嘘であったと告げられます。ここで読者は、ブライオニーと同じように物語を信じたいという誘惑と、残酷な現実の間で揺さぶられることになります。
個人的な悲劇の背景には、当時のイギリス社会の強固な階級制度と、すべてを押し流す第二次世界大戦の影があります。ロビーが簡単に犯人に仕立て上げられた背景には、彼が使用人の息子であり、エリート層のよそ者であったという階級的偏見があります。
戦争の描写は、個人の倫理や反省が通用しない、圧倒的な暴力と混沌を象徴しています。
物語世界
あらすじ
1935年、イギリスの壮麗なカントリー=ハウス。13歳の少女ブライオニーは、作家を夢見る想像力豊かな少女です。
ある暑い夏の日、彼女は姉のセシリアと、使用人の息子で幼馴染のロビーが庭の噴水で言い争い(のように見えるやり取り)をしているのを目撃します。大人たちの複雑な恋愛感情を理解できないブライオニーは、自分の物語のフィルターを通して、ロビーを不審で危険な男だと思い込んでしまいます。その後、親戚の少女ローラが何者かに暴行される事件が発生。ブライオニーは暗闇の中で犯人をはっきりと見ていないにもかかわらず、犯人はロビーだと断定的な証言をしてしまいます。
1940年。ロビーは刑務所から釈放される条件として軍に入隊し、第二次世界大戦の最前線(ダンケルクの撤退戦)にいました。一方、セシリアは家族と縁を切り、ロビーの帰りを信じてロンドンで看護師として働いています。ブライオニーもまた、自らが犯した罪の重さに気づき、大学進学を諦めて過酷な看護兵の道を選びます。
ブライオニーはセシリアとロビーに再会し、謝罪します。二人は彼女を冷たくあしらいますが、ブライオニーは自分の証言を撤回し、真犯人を告発すると誓います。
物語の最後、現代(1999年)に戻ります。今や老年の有名作家となったブライオニーが、自身の人生を振り返ります。ここで読者は真実を知ることになります。実は、ロビーはダンケルクの海岸で敗血症により戦死しており、セシリアもまた同じ年、地下鉄駅の爆撃による浸水事故で亡くなっていました。
つまり中盤で描かれた二人の再会とブライオニーの謝罪は、すべてブライオニーが書いた小説の中の出来事だったのです。現実では、彼女は二人に謝罪することも叶わず、二人の恋を成就させることもできませんでした。




















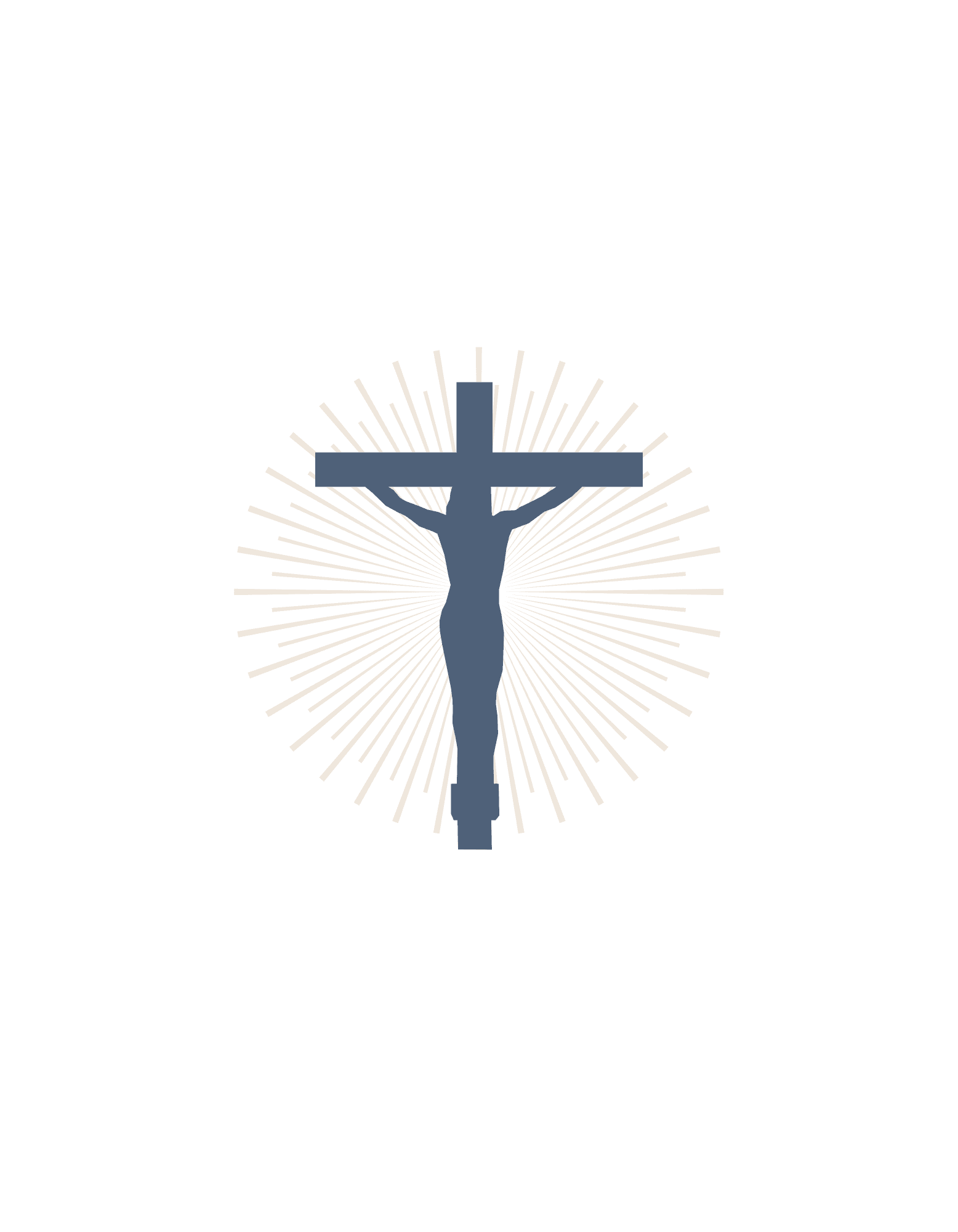


コメント