始めに
ジュネ『泥棒日記』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ジュネの作家性
ジャン=ジュネは、泥棒であり放浪者、そして作家という特異な経歴の持ち主です。
ジュネの才能を最初に見出したのがコクトーです。刑務所の中で書かれた詩『死刑囚』を読み衝撃を受けたコクトーは、ジュネを「黒い天使」と呼び、サルトルらと共に大統領への恩赦を求める運動を行いました。
ジュネは刑務所に収監されている間、プルーストの『失われた時を求めて』を読み耽っていました。プルーストのモダニズム、意識の流れには影響が見て取れます。
フランソワ=ヴィヨンは15世紀のフランスの詩人で、実際に犯罪を犯し、絞首刑の宣告を受けたこともある無頼派の元祖で、ジュネは強い同族意識を抱いていました。
サルトルはジュネについて『聖ジュネ――役者と殉教者』という膨大な評伝を書きました。サルトルはジュネを存在論的なヒーローとして定義し、ジュネ自身はこの本が自分を鋭く分析しすぎていたためショックを受け、一時期筆を折りました。
悪の崇高さ
ジュネはこの作品の中で、世間一般では悪や恥とされる要素を、自らの魂を救済するための聖なる道標へと昇華させています。盗みは生きるための手段ではなく、社会との絶縁を確認するための儀式です。男色は男らしさへの渇望と、選ばれなかった者同士の連帯と孤独です。裏切りは究極の孤独に到達するための行為で、仲間を売ることさえも、自己を純化するプロセスとして描かれます。
ジュネの最大の特徴は、泥沼のような現実を、宝石のような壮麗な文体で描き出すことにあります。牢獄、浮浪、裏切りといった悲惨な状況を、あたかも宗教的な受難のように描写します。あえて社会から軽蔑される道を選ぶことで、逆説的に聖者になろうとしました。どん底にこそ真の自由と美がある、という生の哲学です。
ジュネは捨て子として生まれ、社会に居場所を持たなかった自分を受け入れるのではなく、社会が自分を拒絶するなら、自分も社会を徹底的に拒絶してやるという反骨精神をテーマに据えています。
物語世界
あらすじ
物語の出発点は、バルセロナのスラム街「バリオ・チノ(中国街)」です。
ジュネは、隻腕の美男で泥棒のスティリターノに出会います。ジュネにとって彼は「悪の神」のような存在であり、彼のために盗みを働き、彼が他の女を抱くのを許し、自分は物乞いをして彼を養うという、徹底した「屈辱と服従」に喜びを見出します。
そのスティリターノとの関係が破綻した後、ジュネはヨーロッパ中を放浪します。ここから、彼の悪の探求はより深まります。ベルギーのアントワープでは、泥棒のギュイと出会います。二人はコンビを組んで盗みを繰り返しますが、ジュネはそこで「友情」や「連帯」すらも、悪を極めるためには捨て去るべきものだと考え始めます。
ジュネは仲間を警察に売るという行為にさえ、ある種の神聖さを見出そうとします。彼は、他人と繋がるための道徳をすべて断ち切り、究極の孤独に到達することを目指します。
1936年のナチス・ドイツを訪れた際、ジュネは奇妙な体験をします。当時のドイツは、国全体が軍事化され、ある種の犯罪的な暴力に満ちていました。周囲が皆「悪」である世界では、泥棒である自分こそが平凡な市民のように見えてしまうという皮肉に直面します。
ジュネは、自分が求める「悪」は国家のような集団的な暴力ではなく、あくまで社会の秩序を前提とした、個人的で孤独な反逆であることを再認識します。
舞台はフランスに戻り、彼は何度も刑務所に収監されます。監獄は社会から隔離された場所ですが、ジュネにとっては自分の美学を完成させるための「修道院」となります。彼はそこで、自分を虐げる看守や、冷酷な犯罪者アルマンとの関係を通じて、苦痛を恍惚へと変容させます。
ジュネは獄中で自らの過去を書き始めます。現実の惨めな泥棒体験を、華麗な言葉で装飾し、神話へと作り変えていく作業です。
ジュネは一つの結論に達します。自分が「泥棒」であり「男色者」であり「裏切り者」であることを、社会に謝罪するのではなく、むしろその極北まで突き進むことで、日常的な道徳を超越した「聖者」になったと宣言します。




















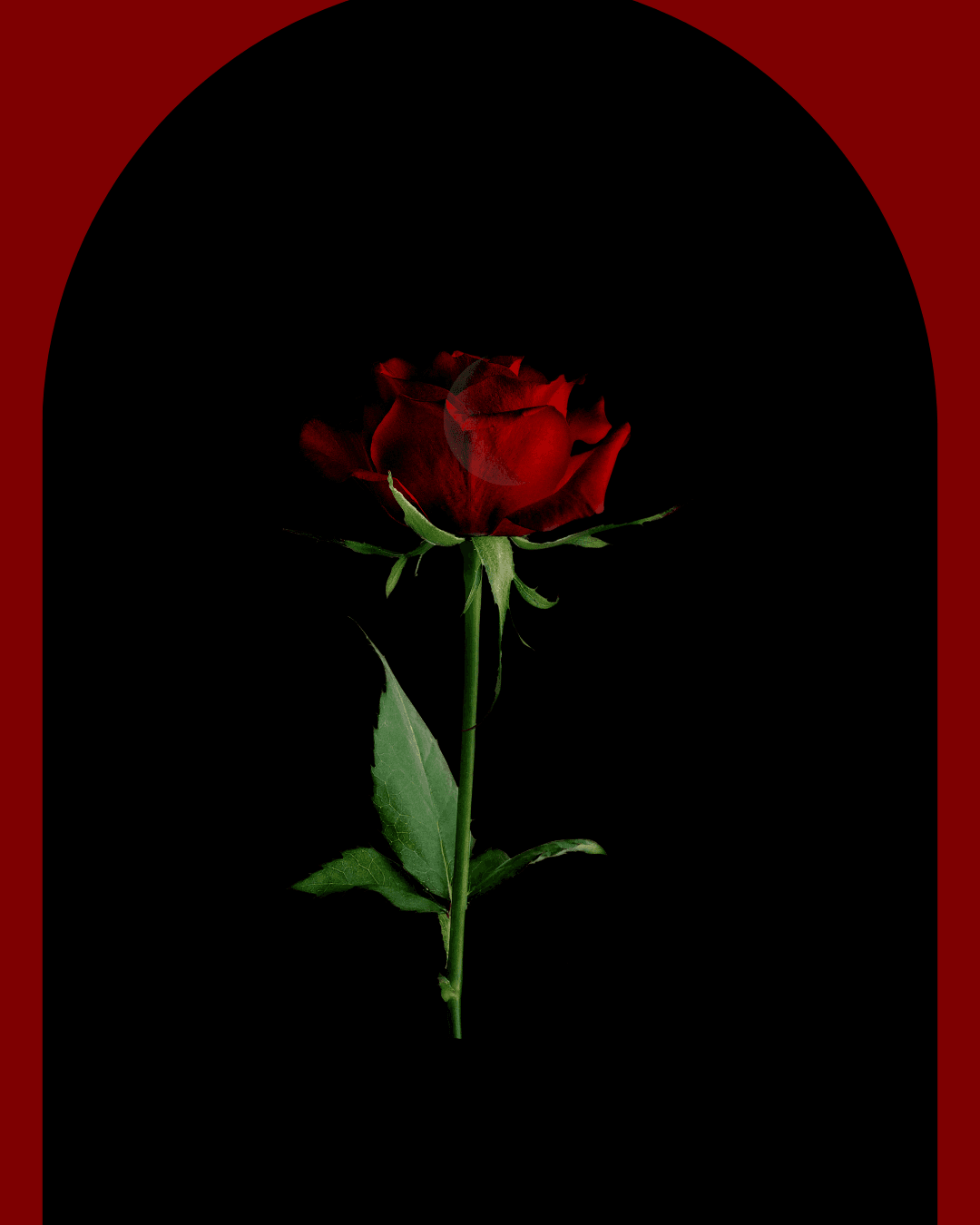


コメント