始めに
ピエール・ガスカール「死者の時」解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
ガスカールの作家性
ガスカールは、第二次世界大戦中のナチス・ドイツによる捕虜収容所での過酷な体験を文学の核に据えた作家です。ガスカールの作品に見られる不条理の感覚は、カフカの影響を強く感じさせます。人間が非人間的な状況に置かれ、動物に近い存在へと還元されていく過程を描く視点などが重なります。
ガスカールはフランスの伝統的な地の文学の流れも汲んでおり、特に初期のジャン=ジオノとの親和性が指摘されます。
ガスカールは、自身の文体においてスタンダールのような明晰さと正確さを重んじていました。人間の魂が極限状態においてどのように変容するか、というテーマにおいてドストエフスキーからの精神的影響も見られます。
タイトルの意味
この作品において、死は宗教的哲学的な儀式ではありません。死は、重い遺体を運び、穴を掘り、土をかけるという肉体労働として描かれます。死者の尊厳よりも、死体の重さや数、あるいは冬の凍土の硬さといった、徹底して即物的な側面が強調されます。
タイトル通り、収容所の中では生者の時間ではなく死者の時間が流れています。生きている捕虜たちは、ただ死を待つか、死者の後片付けをするだけの存在です。ここでは死者の方が数が多く、確固たる存在感を持ち、生きている人間の方が影のように希薄な存在として描かれます。墓を掘る主人公は、毎日死者に触れることで、自分自身も半分死者の世界に足を踏み入れているような感覚に陥ります。
死が事務的に処理される不条理性も大きなテーマです。ナチスによる管理体制下では、死ですらも帳簿上の数字に還元されます。ガスカールは、膨大な数の死が淡々と処理されていく様子を描くことで、戦争の非人間性を告発しました。死者たちは何も語らず、ただ土の中に積み重なっていきます。遺体が風景の一部となっていく描写は、個人のアイデンティティが消滅し、広大な忘却の中に飲み込まれていく恐怖を表現しています。
物語世界
あらすじ
物語は、第二次世界大戦中、ウクライナのラヴァ=ルスカにあったドイツ軍の捕虜収容所から始まります。そこは、脱走を繰り返したフランス人捕虜たちが送り込まれる懲罰収容所であり、飢えとチフスが蔓延する死の淵でした。
主人公のピエール(作者自身がモデル)は、数人の仲間とともに墓掘り人の任務を命じられます。彼らの仕事は、毎日収容所で死んでいく仲間の捕虜たちの遺体を収容所外の墓地に運び、穴を掘って埋葬することでした。
最初は仲間の死にショックを受けていた主人公たちですが、あまりに大量の死に接するうちに、感情が麻痺していきます。遺体は悼むべき人ではなく、運ぶのが大変な重い物体へと変わります。硬い地面を掘る苦労、遺体を隙間なく穴に並べる効率性など、死が徹底的に物理的で事務的なプロセスとして記述されます。
ある時、さらに悲惨な状況に置かれたソ連軍の捕虜たちが大量に送り込まれてきます。彼らはフランス人捕虜以上に過酷な扱いを受け、バタバタと死んでいきます。主人公たちは、自分たちと同じ人間が、まるで壊れたモノのように次々と穴に投げ込まれていく光景を目の当たりにします。
ここで、死の規模があまりに巨大になり、生者の世界が死者の世界に飲み込まれていく感覚、死者の時が決定的なものになります。
主人公は、収容所の中で監視されている生者である自分たちよりも、土の中で沈黙している死者たちの方が、むしろこの土地の本当の主役であると感じ始めます。
墓掘りという作業を通じて、主人公の精神は次第に生者の世界から離れ、死者たちの静寂な時間へと深く同化していきます。ただ、圧倒的な数の死者を埋葬し続けた記憶が、主人公の心に消えない刻印を残します。戦争が終わっても、彼の中に流れる時間は生者の時間ではなく、あの過酷な冬のウクライナで死者たちと共有した死者の時であるという深い孤独感とともに物語は閉じられます。




















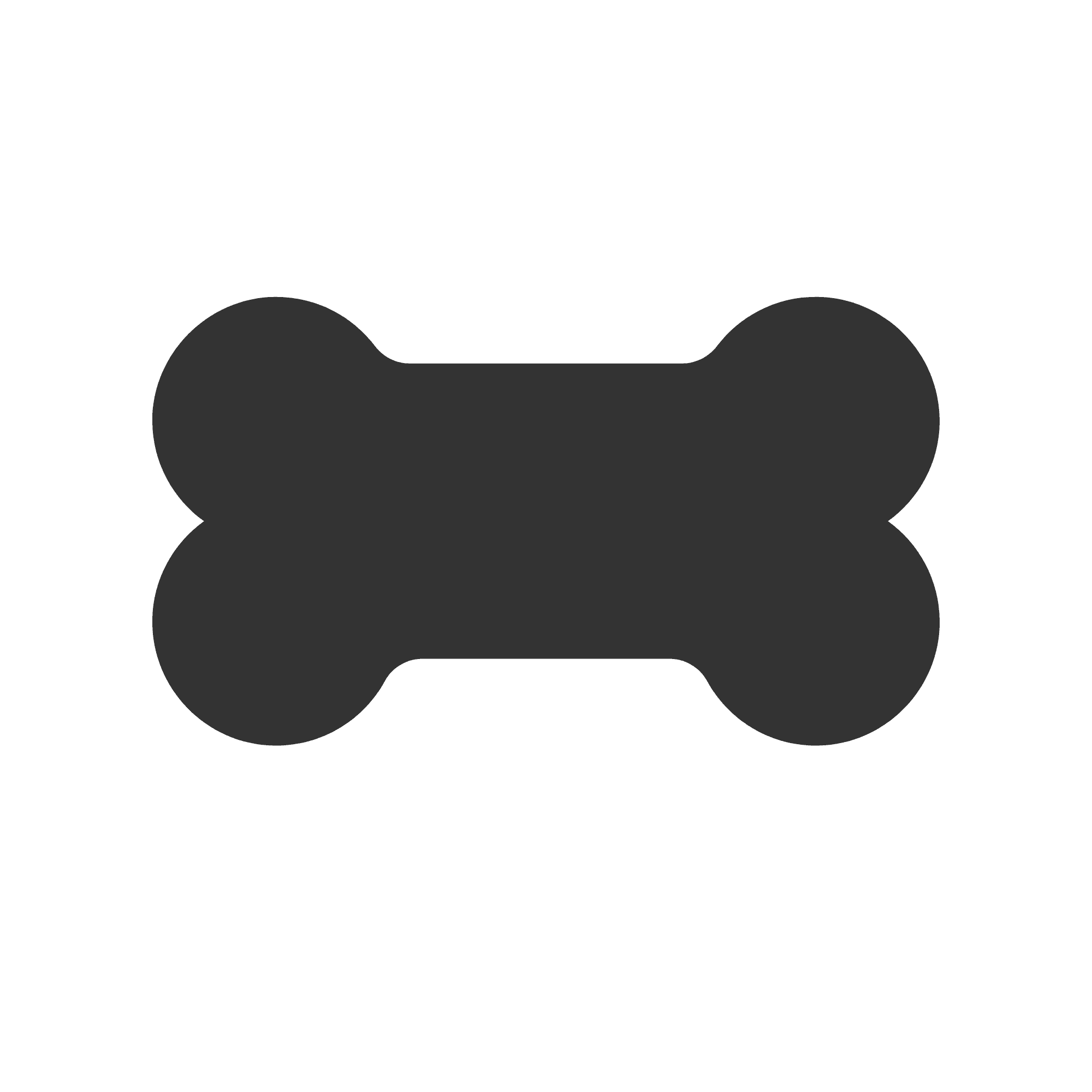


コメント