始めに
今日はジョセフ=コンラッド『闇の奥』のついてレビューを書いていきます。T=S=エリオット『荒地』、フォークナーのサーガなど、後世への影響が計り知れない作品です。
語りの構造、背景知識
船員としてのキャリア
コンラッドの創作の背景に船員としてのキャリアがあります。
1873年にルヴフのギムナジウムに通うものの、健康上の理由で進級できず、伯父に船乗りになりたいという希望を伝えます。やがてそのつてからマルセイユへ渡って、フランス商船の船員となります。西インド諸島のマルチニックなどへ航海し、時にコロンビアやベネズエラに密輸物質の運搬にも関わります。その後密貿易への投資話に騙され、モンテカルロで賭博に手を出して一文無しになります。
1878年、流刑囚の子に課されるロシアの兵役を忌避したと見なされてフランス船には乗れなくなり、英国船に勤務し、マルタ島、イスタンブール、アゾフ海などを経て、イギリス本土のサフォーク州ロースロフトに着き、石炭運搬船に乗り込み、ロンドンの訓練学校に通って二等航海士の資格を得て、インド、シンガポールなどに航行します。
1884年には一等航海士の試験に合格、1886年には船長試験に合格し、イギリス国籍を取得します。
さらにコンラッドは1891-93年にトレンズ号の一等航海士としてロンドンからアデレードまで2度航海します。1889年に帰国して『オルメイヤーの阿房宮』の執筆を始めます。
リヴィングストンやスタンリーの探検によりアフリカへの注目が集まると、1890年にベルギーの象牙採取会社の船の船長となり、コンゴ川就航船に乗り、さらに陸路でレオポルドヴィルまで行き、別の船でキサンガニに到達するものの、病により1891年にブリュッセル経由でロンドンに戻ります。また痛風、神経痛、マラリアで数ヶ月入院し、伯父のアドバイスに従ってスイスの温泉で療養、その後は旅客船での仕事など、船員以外の仕事をします。1893年にオーストラリアとニュージーランドから戻る船に、ジョン=ゴールズワージーとエドワード=ランスロット=サンダーソンの二人の若いイギリス人がいて親しくなります。
このような経験から、創作を手掛けたコンラッドでした。
モダニズム、リアリズムの影響
コンラッドはゴールズワージー、F=M=フォード、H=ジェイムズ、フローベール、ド―デ、モーパッサンの影響を受けました。
ゴールズワージーの社会階級や人間関係を冷静に描くリアリズムは、コンラッドの観察力や人間社会の構造的な描写と重なります。
フォード=マドックス=フォードはモダニズムの作家で、叙述技法や視点操作の工夫において影響されます。ヘンリー=ジェイムズもモダニズムにつながるリアリズム作家で、『ねじの回転』などの非線形の実験的語りをコンラッドも展開するようになります。
フローベールのリアリズム、写実主義からも影響が大きいです。モーパッサンの自然主義の文明批評、語りの工夫はコンラッドに影響しています。
等質物語世界の語り手。複層的な枠物語的構造
この作品を特徴づけるのは、何と言ってもその特異な語りの構造です。この作品の語り手は最初「私」と呼ばれる船員なのですが、そこへ船乗りのチャールズ=マーロウが、仲間たちに向けて自分の過去について語り始め、彼がクルツという男に関連して見聞きしたことを語り出します。こうして「私」はマーロウによる第二次の語りの聞き役へと交代します。このようなボッカチオ『デカメロン』のような枠物語的構造が特徴です。
コンラッドは等質物語世界の語り手を設定するヘンリー=ジェイムズ(『ねじの回転』)の影響を受けていました。ジェイムズ『ねじの回転』でも等質物語世界の語り手・「私」が設定され、「私」はある屋敷に宿泊した一人で、そこで開かれた怪談の集まりに加わっているのですが、そのうち一人(ダグラス)が、かつて自分の家庭教師(ガヴァネス)だった女性について、彼女から来た手紙の朗読などを通じて語ります。最初に現れた「私」はもっぱら聞き手になっています。
また、コンラッドの私淑したモーパッサン「隠者」も、同種の枠物語で、永井荷風がこの影響で「おもかげ」(『ふらんす物語』)をものしています。
コンラッドの手法の展開
『闇の奥』ではマーロウが語りの主体となると、焦点化されるマーロウがかつて伝聞したことなどがさまざまに物語られ、クルツという男を巡って見聞きしたことが縦横に綴られていきます。こうした語りの主体を聞き手の設定やその他第二次の語り(書簡体小説、作中作など)によって複数導入する手法はT.S.エリオット『荒地』やフォークナー『アブサロム、アブサロム!』『響きと怒り』などに影響しましたし、昨今では浅田次郎『壬生義士伝』、宮部みゆき『火車』など、エンタメ小説でも広く見られる手法です。
コンラッド『闇の奥』も植民地制度の不正義に言及する内容ではありますが、このような手法はもっぱらポストコロニアルな主題を孕みつつ継承されていきました。大江健三郎『万延元年のフットボール』の記事でも書きましたが、フレイザー『金枝篇』がT=S=エリオット『荒地』に導入されて以降、作家は語りの手法に民俗学、社会学的アプローチをも積極的に取り入れるようになっていきました。特にアナール学派的な、中央の事件史に抗する心性史としての歴史記述のアプローチは、ポストコロニアルな主題を孕みつつ、ガルシア=マルケス『族長の秋』『百年の孤独』などラテンアメリカ文学などへと継承されていきました。歴史の中のミクロなアクターの視点、語りを通じて歴史を記述、再構築しようとするアナール学派的アプローチは、小説家にとっても強力な武器となったのでした。
コンラッドの手法は、その歴史記述戦略の先駆であったと言えます。
栄光と破滅のリアリズム
コンラッドはフローベール(『ボヴァリー夫人』『感情教育』)やその弟子モーパッサン(『脂肪の塊』『女の一生』)のリアリズム文学、自然主義文学を好みました。フローベール『ボヴァリー夫人』的な、ブルジョワ社会における自己実現をめぐった栄光への野心と破滅の主題は、『闇の奥』においてもクルツの絶頂と破滅という形で継承されています。ブルジョワ社会の頽落への批判的なテーマはT=S=エリオット『荒地』にも見えます。
暴君の孤独な栄光と破滅はフォロワーのフォークナー『アブサロム、アブサロム!』、そのさらにフォロワーのガルシア=マルケス『族長の秋』『百年の孤独』にも見えます。オーソン=ウェルズ監督『市民ケーン』も、本作の影響が知られます。
映画『地獄の黙示録』との違い
F=F=コッポラ監督『地獄の黙示録』は本作を原作としていますが、舞台をコンゴからベトナム戦争時代のベトナムに改めています。
また『金枝篇』やエリオット『荒地』からの影響が顕著で、儀礼的な場面の映像のモンタージュを通じて、神話的な象徴としての物語になっています。森の王、司祭であるマーロン=ブランド演じる・カーツの栄光と破滅が描かれます。コンラッドの原作では、後続のエリオットやフォークナーと異なり、神話的主題が前面に出るわけではありません。
物語世界
あらすじ
この作品の語り手「私」は船員なのですが船にいて、そこへ船乗りのチャールズ=マーロウが、仲間たちに向けて自分の過去について語り始め、彼がクルツという男に関連して見聞きしたことを語り出します。
マーロウは、各国を回った後でロンドンに戻っていたものの、アフリカに行くことを思い立ち、親戚の伝手でベルギーの貿易会社に入社します。ちょうど船長の1人が現地人に殺され、欠員ができていました。
マーロウは、船で出発しアフリカの出張所に着きます。そこでは、黒人が象牙を持ち込んで来ると、木綿屑やガラス玉などと交換しています。鎖につながれた奴隷もいました。ここで10日ほど待つ間に、奥地にいるクルツという代理人の噂を聞きます。クルツは優秀で、将来は会社の幹部になるだろうといわれます。マーロウは隊商とともに、中央出張所を目指して出発し、目的地に着いたのでした。
中央出張所の支配人から、上流にいるクルツが病気らしいと聞きます。蒸気船が故障し、修理までの間に、再びクルツの噂を聞きます。クルツは、象牙を乗せて奥地から中央出張所へ向かってきたものの、荷物を助手に任せ、1人だけ船で奥地に戻ったそうです。
ようやく蒸気船が直り、マーロウは支配人、使用人4人、現地の船員と川(コンゴ川)を遡行します。クルツの居場所に近づくと、突然矢が降ってきます。銃で応戦していた舵手でしたが、腹を刺されて死にます。
奥地の出張所に着いてみると、25歳のロシア人青年がいました。青年は、クルツの崇拝者で、青年から、クルツが現地人から神のように思われていたこと、手下を引き連れて象牙を略奪していたことなどを聞きます。
一行は、病気のクルツを担架で運び出し、船に乗せます。やがてクルツは、”The horror! The horror!”という言葉を発して死にます。
関連作品、関連おすすめ作品
・ローラン・ビネ『HHhH (プラハ、1942年)』:アナール学派以後の歴史小説
・オーソン=ウェルズ監督『市民ケーン』:栄光と墜落。非線形の語り。
・『十三機兵防衛圏』『428 封鎖された街で』:非線形の語り、焦点化の実験
参考文献
・武田ちあき『コンラッド 人と文学』(2005.勉誠出版)









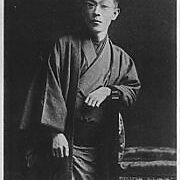





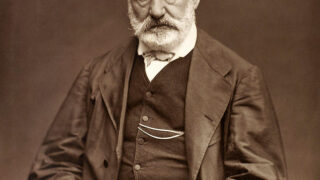






コメント