始めに
イシグロ『わたしたちが孤児だったころ』解説あらすじを書いていきます。
背景知識、語りの構造
セルバンテス、ドストエフスキー流のバロック喜劇。サヴォイオペラ、バーレスク
イシグロのステレオタイプがもたらすグロテスクな笑いは、イシグロが私淑したドストエフスキー(『罪と罰』『悪霊』)などのロシア作家に加え、それに影響したセルバンテス(『ドン=キホーテ』)、セルバンテスを水源とするバーレスクやサヴォイ=オペラを連想させます。
たとえばサヴォイ=オペラの代表作『ミカド』のように、誇張されたエスニシティ、ステレオタイプを駆使してグロテスクな風習喜劇が展開されます。
探偵小説パロディ
本作は探偵小説のパロディになっています。また特に、異国オペラに影響されたエキゾチックな舞台装置を設定する点において、アガサ=クリスティのミステリーと類似しています。あとディケンズのミステリー色の強い作品とも重なり、終盤には『大いなる遺産』へのオマージュが見えます。
探偵小説の典型的なプロットは、主人公が痕跡を集めて推理によって真相を明らかにするという展開ですが、本作もそうしたプロセスを展開しつつ、イシグロらしいベクトルにまとめています。
1900年代初頭、語り手のクリストファー=バンクスは中国の上海租界で幼少期を過ごしましたが、 10 歳くらいのとき、アヘン商人の父親とそれに反対する母親が数週間のうちに失踪します。クリストファーはイギリスの叔母のもとに預けられます。成長してその事件について探ろうとする、というのが大まかなあらすじです。
信頼できない語り
本作は多くの作品同様に、信頼できない語りとして設定されています。自身のルーツをテーマにする物語という点では『私を離さないで』などと重なり、個人のアイデンティティの物語として、大英帝国のアイデンティティをも問いただします。
物語の展開のなかで明らかになっていくのは、主人公の思い出や記憶が美化されていて、美しかったはずの少年時代は多くのベールで周囲が覆われていて、周りには植民地世界におけるさまざまな歪んだ欲望や思惑が交錯していた、ということです。また探偵としての自分が誇っていた認識や推論の正しさについても、クリストファーは自信をなくしていきます。
このあたりはポストコロニアルな主題を展開するイシグロ作品において、大英帝国の国民たちの、植民地世界に向けるロマンチックな眼差し、美化の傾向、そこで自分たちがしていることへの盲目性などに批判的に言及するデザインになっているといえます。クリストファーが次第に自分への自信がなくなっていくのも、第二次大戦後の植民地主義の崩壊などをふまえるものと解釈できます。
最終的にクリストファーは、後見人のフィリップから、父親が新しい恋人と香港に逃げたこと、そして数週間後に母親が中国の軍閥である王九を侮辱し、王九に妾として奪われたことを知ります。フィリップは、クリストファーがイギリスで学生だった頃の生活費と学費について、王九に連れ去られた母親は、息子のために経済的援助を引き出していたことを伝えます。1958 年、香港でクリストファーは母親と再会しますが、母親は彼を認識できません。彼は子供の頃のあだ名「パフィン」を使い、母親はそれは覚えています。彼は母親に許しを乞うものの、母親はなぜ許しが必要なのか困惑していました。
こうしたラストの展開において、主人公は自分の生活を支えていたのが母と植民地世界だったと知ります。再会を果たしたものの母親は記憶がおぼつかなくなっていて、クリストファーを認識できません。記憶がおぼつかなくても、クリストファーの幼いころのあだ名は確かに覚えていて、息子への愛情をずっと母が持っていることは、物語にとってほのかな救いになっています。
物語世界
あらすじ
1900年代初頭、語り手のクリストファー=バンクスは中国の上海租界で幼少期を過ごしましたが、 10 歳くらいのとき、アヘン商人の父親とそれに反対する母親が数週間のうちに失踪します。クリストファーはイギリスの叔母のもとに預けられます。
やがて彼は探偵として成功し、今度はその腕を両親の失踪事件の解決に生かします。サラという若い女性と親しくなるものの、クリストファーは結婚せず、イギリスで孤児になったジェニファーという少女を養子にします。
両親について調査するものの、当時の中国でクリストファーは上海の外国人居住区にまで及ぶ日中戦争に巻き込まれます。彼は老刑事を通じて、両親が監禁されていた家を突き止めて向かいます。
その途中で、中国の警察署に入り、誘拐された両親の家へ案内するよう司令官に説得しますが、しばらくして司令官はクリストファーをそれ以上連れて行くことを拒否したので、彼は一人で向かいます。
クリストファーは、幼なじみのアキラだと思われる負傷した日本兵に出会います。やがて彼らがあの家に入ると、両親はいませんでした。
クリストファーは、後見人のフィリップから、父親が新しい恋人と香港に逃げたこと、そして数週間後に母親が中国の軍閥である王九を侮辱し、王九に妾として奪われたことを知ります。フィリップは共産党の二重スパイで、誘拐に加担しており、誘拐が行われた際にクリストファーがその場にいないようにしていました。
彼はクリストファーに銃を差し出して殺すよう頼むが、クリストファーは拒否します。また父親は腸チフスで亡くなったが、母親はまだ生きているかもしれないことを知ります。フィリップは、クリストファーがイギリスで学生だった頃の生活費と学費について、王九に連れ去られた母親は、息子のために経済的援助を引き出していたことを伝えます。
1958 年、香港でクリストファーは母親と再会しますが、母親は彼を認識できません。彼は子供の頃のあだ名「パフィン」を使い、母親はそれは覚えています。彼は母親に許しを乞うものの、母親はなぜ許しが必要なのか困惑していました。
参考文献
・「ノーベル文学賞 カズオ・イシグロが語った日本への思い、村上春樹のこと」.文春オンライン.2017/10/06.
・新井潤美『不機嫌なメリー=ポピンズ』(平凡社.2005)










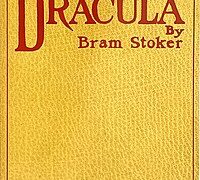









コメント