はじめに
金井美恵子『文章教室』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
映画の影響
母子家庭で、幼少の頃より映画好きで知られる金井美恵子です。
傾向としてはアート映画のヌーヴェルバーグからの感化が先ず大きく、ヌーヴェルヴァーグのジャンリュック=ゴダール、フランソワ=トリュフォー、エリック=ロメールのほか、ジャン=ルノワール、ルイス=ブニュエル、ロベール=ブレッソン、フリッツ=ラング、エリック=ロメール、ジョン=フォード、エルンスト=ルビッチ、ジャン=ヴィゴ、アッバス=キアロスタミなど、ヌーヴェルヴァーグの方面からの評価の高い、作家主義的傾向をはらむ監督を好む傾向があります。
本作もゴダール(『ゴダールのリア王』)のフィルムに似た、引用のコラージュ、モンタージュによる形式的実験を展開します。
モダニズム作家
金井美恵子はモダニズムの作家です。
ギュスターヴ=フローベールの他、クロード=シモンなどヌーヴォー=ロマンの作家、ロラン=バルトなどの評論家、モーリス=ブランショ、ウラジーミル=ナボコフなどの形式主義的実験からの感化が顕著です。
本作も文芸批評のパロディという点においてナボコフ『青白い炎』を連想させます。
語りの構造
本作は地の文と絵真が文章教室に通ってから書き出したノート「折々のおもい」からの引用文(〈〉内)、現役作家の著作や他の書籍からの引用文(《》内)とをコラージュして構成されています。
ゴダールのフィルムを連想させる、既存のテクストの引用によるコラージュとモンタージュが展開されていきます。
こうした手法によって、佐藤絵馬の痛々しいロマンティシズムを風刺すると同時に、ニューアカ時代の批評言語を風刺します。何者にもなれず何者でもない主人公たちが、借り物の言葉や賢しらな振る舞いで誰かになろうとして失敗する様がコミカルに描かれます。
他方で佐藤絵馬の通う文章教室の講師たる現役作家は、『ボヴァリー夫人』のオメーの如き俗物的したたかさで、業界で生き残ります。これはもともと丸谷才一『文章教室』への当てつけなので、丸谷を風刺するものでしょうか。
ニューアカとスノビズム
本作は1985年発表で、ニュー=アカデミズム全盛の時代を背景にしています。
ニュー=アカデミズムとは1980年代中頃に浅田彰、中沢新一の著作がベストセラーとなり、アカデミズムから外れた潮流をマスメディアが名付けた造語です。思想的潮流としては、記号論、プラグマティズム、構造主義、ポスト構造主義、ポスト=モダニズムを参照しつつ展開され、浅田彰はドゥルーズ、中沢新一はレヴィ=ストロースの影響が大きいです。
ニュー=アカ全体の傾向として、身も蓋もないこともいうとスノビズムによるフカシやハッタリが多く、良く言えば伝統的な学究の枠に囚われない、悪く言えば極端なホーリズムで厳格な真理追求のプロセスを重視せず、マジックワードと戯れ遊ぶ哲学エッセイに終始する潮流で、彼らはアカデミズムよりもマスコミやジャーナリズム方面で影響力を持っていて、似たようなハッタリやスノビズム、マジックワード遊びは、さまざまなメディアに氾濫しました。
本作はそうした知の虚人の跋扈する時代を、フロベール『ボヴァリー夫人』『ブヴァールとペキュシェ』などのリアリズムを参照にしつつ風刺します。『ブヴァールとペキュシェ』さながらに、生半可な学問でそれっぽいことをやろうとするものの実のあることは全くできないニューアカ時代の批評のモードを風刺しています。
物語世界
あらすじ
物語は夫と大学生の娘と三人で暮らす主婦の佐藤絵真が現役作家の開講する文章教室に通うことから始まります。
夫は会社の部下と浮気をし、絵真は絵本作家と不倫、一度妊娠までさせられた男に捨てられた娘は、今度は大学の研究室で英文学を研究する男にひかれ結婚を望みます。この男の両親は離婚し、母親の手で育てられるものの、彼にはイギリス留学中に知合ったイギリス人の恋人がいます。彼女の両親も離婚していて、精神を病む老いた母の面倒を彼女がみています。
絵真の通う文章教室の講師をしている現役作家は新宿の文化人が集まる酒場の若い娘に夢中になります。一度は娘に結婚する気はないといった男も、イギリスの女に別の男がいることがわかり、結局は娘と結婚し、平凡な夫に不満を持って実家へ家出をした妻も、不倫の相手から縁を切られ、現役作家は女に逃げられてその顛末を小説にしたて、文学賞をとります。













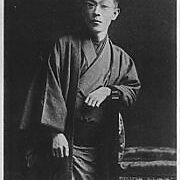


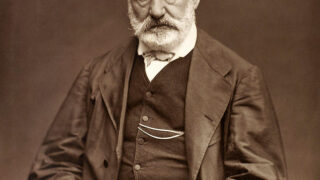





コメント