始めに
松浦理英子『最愛の子ども』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
語りの構造
神奈川県にある私立玉藻学園が舞台です。ここでは男女が別々のクラスに分けられ、高等部の2年4組には、日夏、真汐、空穂の仲睦まじい3人組がいます。3人組のクラスメイトである〈わたしたち〉は、日夏のことを〈パパ〉、真汐のことを〈ママ〉、空穂を〈王子様〉と呼んでいます。〈わたしたち〉は、日夏、真汐、空穂の3人組を〈わたしたちのファミリー〉と呼んで眺めています。
この〈わたしたち〉の視点から、〈わたしたちのファミリー〉の関係と、その解散までが描かれていきます。
一人称複数の語りは春樹『アフターダーク』と重なります。
語りの効果
このような語りの構造によって、クラスの誰にもなれない〈わたしたち〉が、〈わたしたちのファミリー〉に理想の役割を投影し、期待し、それに憧れるさまを描いています。
〈わたしたち〉は、無個性で主体性がありません。それは、おそらく、クラスや社会のなかで期待される適切な振る前に応えようとしていて、アウトサイダーとしてのレッテルを貼られることを恐れているからです。
アウトサイダーとして、個性的な存在としての期待の眼差しを向けられたくないために、私たちはクラスの関係性のなかに埋没して、主体性を損なっています。そして、〈わたしたちのファミリー〉の三人に、わたしたちの望む役割を期待し、彼女らの存在に自分たちのアイデンティティを背負わせています。
最愛の子ども
そんな〈わたしたちのファミリー〉という幻想は、日夏と空穂が肉体関係を持ったことが空穂の母に知れ、母のクレームによって日夏が停学になったことで終わりを告げます。そこで、空穂の母は、自らの最愛の子どもであるところの空穂を汚されたと思い、日夏を咎めたのでした。それによって、〈わたしたち〉は最愛の子どもである日夏を損なってしまいます。
しかしここで、〈わたしたち〉も空穂の母も、相手に最愛の子どもとしての役割を期待し、そのフレームを通して相手をみているから、二人の間で正確に起こったことや二人の心情を正確にとらえきれて居ないのではないか、という疑いが起こります。
〈わたしたち〉は〈わたしたちのファミリー〉という役割を期待して、そのフレームから三人を観察しています。空穂の母も、〈最愛の子ども〉という役割を空穂に担わせ、一方的に日夏にそれを侵害する役割を背負わせ、糾弾します。〈最愛の子ども〉という役割は、空穂の母にとって〈母〉としてのアイデンティティの基盤となっているものです。そして、〈最愛の子ども〉である空穂が逸脱者となることは、〈母〉として避けなくてはいけないことです。
〈わたしたち〉同様に、テクストの外部にいる読者も、性に関する相互的な役割期待を持ち、規範を身につけてそれにコミットメントして暮らしています。〈わたしたちのファミリー〉は、より強固な外部の伝統的な家族や性的なモラルといった規範と衝突したことで、消滅してしまいます。
空穂の母は、社会の相互的な役割期待の網の目のなかで、規範に規律されて、〈母〉としての役割を果たしたのでした。
私たちと読者
〈わたしたち〉は読者の存在と重なります。
〈わたしたち〉は、共同体の規範に規律されて主体性を失い、〈わたしたちのファミリー〉というフレームで三人を観察します。〈わたしたち〉は主体的な逸脱者となることを恐れ、一方でそれに憧れ、そんな三人を〈わたしたちのファミリー〉と呼んで、〈わたしたち〉自身のアイデンティティにします。
読者は、基本的にこの〈わたしたち〉の視点というフレームに囚われて、物語世界内の事実を観察します。読者も共同体のなかで相互的な役割期待のなかで疎外され、テクストの中のキャラクターたちに、何か役割を期待します。主人公3人の振る舞いを物語として捉え、そうしたフレームを通じて、テクストと向き合い、美的な経験を体験します。
〈わたしたち〉は、主体性を失い、〈わたしたちのファミリー〉に理想の役割を背負わせますが、それは抑圧的・権力的な営みで、またそれと同様の原理に阻害されることで、私たちは個性を失っているものともいえます。
読者も〈わたしたち〉も、そのような相互的な役割期待のなかで、〈わたし〉を生きることができず、誰かの物語に縋って、それをアイデンティティの拠り所にしていると言えます。
舞台と玉藻前
舞台は私立玉藻学園で、ここでは男女が別々のクラスに分けられています。この玉藻は、玉藻前から取っていると思われます。
玉藻前は、平安末に鳥羽上皇の寵姫だったとされる伝説上の人物です。妖狐の化身で、正体を見破られた後殺され、下野国那須野原で殺生石になったとされます。
このように、玉藻前は自分でない誰かの役割を生きようとしてそれになりきれず見破られて殺され、他者を傷つける殺生石になってしまったのでした。
物語の舞台となる私立玉藻学園でも、男女別学的な制度によって、〈わたしたち〉には、〈女〉としての役割、規範が刷り込まれていきます。〈わたしたち〉は、〈女〉にならなくてはいけませんが、それになりきれなければ見破られて、疎外されることになり得ます。
だから〈わたしたち〉はだれでもない〈女〉になって、〈わたしたちのファミリー〉の関係を物語としてのラベルに還元し、その物語に縋って生きています。
結局、玉藻前は、誰かの役割を期待されてそれになり切れず、呪詛の中で生きるようになってしまったという点で〈わたしたち〉の疎外と危うさを象徴します。
物語世界
あらすじ
神奈川県にある私立玉藻学園では、男女が別々のクラスに分けられています。高等部の2年4組には、日夏、真汐、空穂の仲睦まじい3人組がいます。日夏は真汐に対して態度や喋り方が常に優しく、また真汐は日夏に対して素直で信頼を置いているため、3人組のクラスメイトである〈わたしたち〉は、日夏のことを〈パパ〉、真汐のことを〈ママ〉と呼んでいます。さらに、空穂が日夏と真汐に挟まれて、2人に懐いているために空穂は〈王子様〉と呼ばれていました。
〈わたしたち〉は、日夏、真汐、空穂の3人組を〈わたしたちのファミリー〉と呼んで眺めています。
しかし、そのような関係は終わりを迎えます。日夏と空穂が肉体関係を持ったことが空穂の母に知れ、母のクレームによって日夏が停学になってしまったのでした。
こうして、〈わたしたちのファミリー〉の関係は離散することになり、それぞれの道へと進むことになります。



















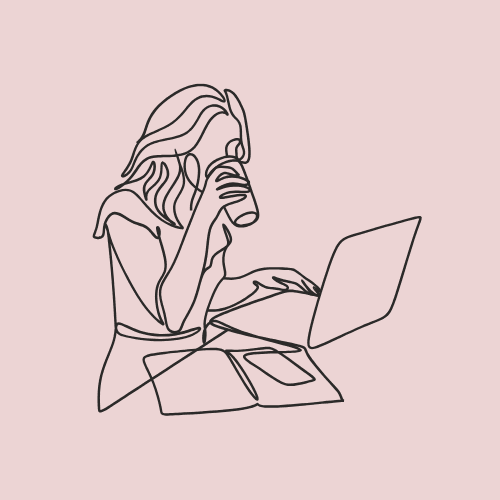
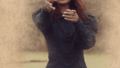
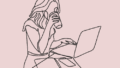
コメント