はじめに
漱石『門』解説あらすじを書いていきます。
語りの構造、背景知識
英露のリアリズム
夏目漱石は国文学では割と珍しく(露仏米が多い印象です)、特に英文学に創作のルーツを持つ作家です。特に好んだのは、英国のリアリズム作家(オースティン[『傲慢と偏見』]、ジョージ=エリオット、H=ジェイムズ[『ねじの回転』『鳩の翼』])でした。『三四郎』『それから』『こころ』『行人』『明暗』などの代表作も、そのような英国の心理リアリズム描写を範としますし、本作も同様です。
またロシア文学のリアリズムからも影響され、ドストエフスキー(『罪と罰』)などに似た心理リアリズムが展開されます。
プラグマティズム
また、漱石はH=ジェイムズの兄ウィリアムなど、プラグマティズムからも影響されました。これは極めてざっくりいうと、日常言語や日常的実践の世界を分析的に捉えようとする潮流です。現代でも推論主義や消去主義のような形で継承されています。こうした哲学的潮流に触れることが、日常的な実践への鋭敏な感性を培ったと言えます。
宗教という制度とその中での実践
本作品はモラルを逸脱した男が安寧を求めて参禅するなど、宗教という制度の中での実践が描かれています。『それから』においては公共圏で期待される役割から逃れるべく姦通という行為が用いられていましたが、参禅という行為も公共圏における役割から逃れるためのトポスとして機能しています。日本における前近代文学における仏教、寺院が果たしていたのもそのような役割でしたが、俗な世界の絆を逃れることを可能にする制度、トポスとなっています。
モラルからの逸脱と日常の中の義務
本作品は『それから』のある種後日談のような内容で、『それから』で描かれたのは、姦通に至るまででしたが、本作はそれからのドラマを描いた物語です。『それから』では姦通が公共圏で期待される諸々の感情労働やら義務やら責任から逃れつつアウトサイダーとして経済的社会的に自立するツールとして姦通が使われ、主人公を繋ぎ止めていた社会的絆が損なわれるまでを描きました。
本作では過去に姦通というモラルからの逸脱行為をしたことでそのレッテルを貼られ、その役割に応えることが要求されているのに辟易し、寺へと参禅することでそうした縁から逃れようとするも得られるところはなく、日常的実践の中へとコミットメントし、社会的な責任に応えていくまでが描かれます。最終的なその結末はヘミングウェイ『日はまた昇る』を思わせ、終わりなく続く日常で課される義務への諦念が描かれています。
物語世界
あらすじ
宗助は、かつての親友である安井の妻である御米を得て、その罪に苛まれています。そのため父の遺産にもあまり関心を示さず、小六と取り共に暮らします。しかし弟との同居のストレスなどから、御米は寝込みます。
宗助は救いを求め鎌倉へ向かい参禅したが、結局あまり得るところもなく帰宅します。すでに安井は満州に戻り、小六は坂井の書生になることが決まります。御米は春が来たと喜ぶも、宗助はじきに冬になると答えます。
参考文献
・十川信介『夏目漱石』
・佐々木英昭『夏目漱石』














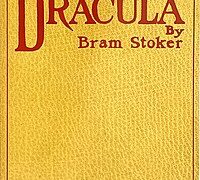






コメント